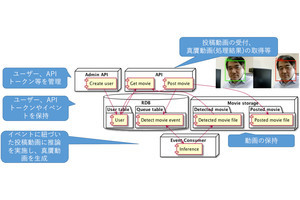東京大学(東大)は9月28日、ヒトの認知機能を脳全体の神経回路を参照しながら再現する人工知能(AI)ソフトウェアを実装する際の仕様情報となる「脳参照アーキテクチャ」データ形式と、それを用いた開発方法論を標準化したことを発表した。
同成果は、東大大学院 医学系研究科 脳神経医学専攻の山川宏客員研究員(東大工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任研究員/NPO法人 全脳アーキテクチャ・イニシアティブ代表/理化学研究所 生命機能科学研究センター 客員主管研究員兼務)らの研究チームによるもの。詳細は、ニューラルネットワークを扱う学術誌「Neural Networks」にオンライン掲載された。
深層学習が発展した2010年代、主に機械学習を組み合わせることで、ヒトのような汎用性を備えたAIが実現できるのではないかという期待が高まったが、実際にはその多様な計算装置を組み上げる設計空間が膨大であるという課題があった。
さまざまなAIに関するプロジェクトが日本国内でも進められており、そうしたプロジェクトを推進している組織の1つが、山川客員研究員が代表を務める全脳アーキテクチャ・イニシアティブであり、同組織が2014年から推進しているのが、「脳全体のアーキテクチャに学び人間のような汎用人工知能を創る(工学)」ことで、設計空間を制約する「全脳アーキテクチャ・アプローチ」(WBAアプローチ)だという。
-

全脳アーキテクチャ・アプローチの基本コンセプトを簡略化した図が改訂された基本概念図。(左)脳内の大きな器官の主な例が示されている。また、それらの器官の間の結合によって、さらなる脳の構造が形成されている(画像には示されていない)。(右)機械学習を利用するものを含む計算モジュールが、脳の構造を参考にして配置・接続されている。このようにして、身体を介して環境と相互作用しながら動作するAIソフトウェアシステムを構築していくという (出所:東大プレスリリースPDF)
プロジェクト開始当初は、現状の神経科学の知見に基づいて、脳のようなソフトウェアを構築する方法論は明らかではなかったとするが、数年を経て3つの主要な課題が明らかとなったとする。1つ目は、脳科学とソフトウェア開発の両方に精通した人材が少なく、その育成が困難であること。2つ目は、脳全体をカバーする神経科学知見は膨大であり、個人の認知能力に頼って脳全体の機能を統合したソフトウェアを設計することには無理があること。そして3つ目は、脳の認知機能をソフトウェアに適切に反映させるためには、参照する脳の記述粒度を適切に選択する必要があるということ、だという。
今回、山川客員研究員らは、これら3点の課題を踏まえ、脳型ソフトウェア開発を、脳参照アーキテクチャ(BRA)を共同で描く設計作業と、BRAに基づいてソフトウェアの実装と統合を行う開発作業に分けることによる「BRA駆動開発方法論」を提案することにしたという。
BRAとは、脳型ソフトウェアの仕様情報として標準化されたデータ形式で、主に、メゾスコピックレベルの解剖学的構造を記述した「脳情報フロー」(BIF)形式のデータと、それに付随する1つまたは複数の「仮説的コンポーネント図」(HCD)で構成されているという。この方法論は具体的には、まず神経科学の論文やデータを収集・整理してBIFデータを作成。BIFは、脳内におけるさまざまな粒度の「サーキット」をノードとし、それらの間の軸索投射にあたる「コネクション」をリンクとする有向グラフだというが、割り当てられた計算機能は仮説であるため、いずれのサーキットに対しても複数のHCDが割り当てうるものとなっているとする。
-

脳参照アーキテクチャ(BRA)は、脳情報フロー(BIF)と仮説的コンポーネント図(HCD)で構成されている。BIFは、解剖学的構造におけるメゾスコピックレベルの情報の流れを提供する。HCDは、ある回路の解剖学的構造と一致するように機能が整理された図。BIFでは、1つの回路に対して複数のHCDを使用することができる。すべてのソフトウェア開発プロジェクトは、基本的に特定のHCDに基づいている (出所:東大プレスリリースPDF)
こうした特徴により、必ずしも脳を深く理解していない開発者であっても、HCDを仕様として参照することで、脳型ソフトウェアの実装に携われるようになるとするほか、作成されたソフトウェアの生物学的妥当性は、その構造と動作がBRAと一致しているかどうかによって評価され、BRA自体の信憑性は、神経科学の知見の裏付けによって評価されるという仕組みとなっているという。
-

脳のメゾスコピックレベルの解剖学的構造における情報の流れを記述するBIF。(左)BIFは、回路とその回路間の接続からなるグラフ。回路とは、脳内の任意の器官や領域と、それらが接続されたグラフ。接続の起点となるのは、機能的に同じ種類の意味をコード化すると考えられるユニフォームサーキット。(右)BIFデータの各回路を記述する属性。一様回路に特有の属性がいくつかあるという (出所:東大プレスリリースPDF)
研究チームでは、蓄積されたデータは、脳の計算論的理解、認知モデルの開発、脳を利用した人工知能やヒューマノイドロボットの開発、精神医学やヒューマン・エージェント・インタラクションなどへの応用などに波及することが期待されるとしている。また、全脳アーキテクチャ・アプローチの目標である汎用AIの実現に関しては、BRA駆動開発をベースにしたロードマップを提案。この目標の達成には、脳のほぼ全体をカバーするシステムを構築する必要があるとしており、ロードマップの初期段階では、脳全体のBIFとそれに対応するHCDを構築することが、中間目標としては、脳全体を統合した初期ソフトウェアを実装することが掲げられている。さらに、開発工程においては、異なるプロジェクトで設計・実装されたソフトウェアモジュールを統合しつつ、チューニングを行う作業が中心となっていくが、その際には、ソフトウェアモジュールがBIFに準拠して作成されていれば、統合すべき対象が互いに明確であるため、統合作業の効率化が期待できるようになるとしている。