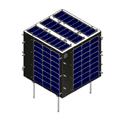欧州宇宙機関(ESA)は2018年4月25日、位置天文衛星「ガイア」の観測データをもとに作成した、史上最も詳細な銀河系の立体地図を公開した。
地図には約17億個もの星の位置などが記されており、私たちの住む銀河系(天の川銀河)の星々だけでなく、その外の銀河の星々や、太陽系内の小惑星などの、さまざまな情報も含まれている。
この新たな星図によって、太陽系の中から銀河系の外に至るまで、宇宙への理解がさらに進むかもしれない。
銀河系の地図を作る「ガイア」
ガイア(Gaia)はESAが開発し、2013年12月に打ち上げられた衛星で、天の川銀河の詳細な立体地図を作ることを目的としている。
星の位置や距離、運動を観測・研究することを「位置天文学」と呼び、そのための衛星のことを「位置天文衛星」と呼ぶ。ESAは1989年に、世界初の位置天文衛星「ヒッパルコス」(Hipparcos)を打ち上げ、約11万8000個もの星の位置を精密に測定。その星図は「ヒッパルコス星表」や「ヒッパルコス・カタログ」と呼ばれ、天文学の基礎となるデータベースとして、世界中の天文学者が利用している。
ガイアはその後継機として、ヒッパルコスよりもさらに高性能な観測装置を搭載し、さらに全天の観測に適した、太陽-地球系のラグランジュ第2点に打ち上げられた。
ガイアは2014年7月から科学観測を開始し、打ち上げから1000日目となる2016年9月14日に最初の星図を公開。ヒッパルコスの成果を大きく超える、約200万個の星についての距離と運動(固有運動)を記録した。
そして今回公開された星図「GaiaDR2」は、2014年7月25日から2016年5月23日までに、前回の1000倍以上もの広さの、ほぼ宇宙全体を観測して得られたデータをもとに作成されたもので、約17億個もの星について、その位置の情報が記されている。またそのうち13億個以上については、その星までの距離、固有運動、色も正確に記されている。
さらに、1億個の星の表面温度、8700万の星間塵の情報も含まれている。
こうしたデータを分析することで、銀河系にある星団の構成や、星々の動きが詳しくわかり、銀河系がどのように形成され、進化をしてきたのかということを調べるための重要な手がかりになるという。
計画に参加しているESAのGunther Hasinger氏は「ガイアによって得られた観測データは、天文学の基礎を再定義するでしょう」と語る。ESAによると、このデータの公開から数時間で、世界中から3000人ものユーザーがダウンロードを始めたという。
他の銀河の星々や太陽系の小惑星のデータも
今回公開されたデータにはさらに、遠方にある50万個ものクエーサーについて、明るさと色が時間経過とともにどのように変化するのかという情報も含まれている。また、球状星団や小マゼラン雲や大マゼラン雲といった矮小銀河の動きもわかり、銀河系とその周辺環境の進化の歴史や、重力の作用、ダークマターの分布などの研究に役立つという。
さらに、1万4000個を超える太陽系の小惑星の位置情報も含まれており、それを使うことで軌道を正確に調べることも可能だという。
ガイアのプロジェクト・サイエンティストを務める、ESAのTimo Prusti氏は「ガイアは、宇宙への理解を非常に大きく進歩させるでしょう」と語る。「私たちがこれまで、深く理解していると考えてきた太陽の近くのことでさえ、ガイアはより新しく、そして興奮するような姿を見せてくれます」。
またガイアのミッション・マネージャーを務める、ESAのFred Jansen氏は「ガイアは最高の天文学です」と誇らしげに語る。「科学者たちは長年にわたって、このデータを使って忙しい日々が続くでしょう。私たちの住む銀河系の謎を解き放つ発見の連続に、驚く準備ができています」。
さらに詳しい地図の作成を目指すガイア、日本でも位置天文衛星の開発が進む
ガイアは現在も観測を続けており、2020年にはさらに新しいデータの公開も予定されている。
今年2月には技術的なトラブルで、衛星が一時「セーフ・モード」になったものの、ESAによると現在は解決し、順調に運用されているという。
運用を担当するESAのTimo Prusti氏によると、ガイアにはまだ十分な燃料が残っており、「ESAがミッションの延長を決定するなら、2024年まで運用できるでしょう」と語っている。
ちなみに日本でも、国立天文台などが独自の位置天文衛星「Nano-JASMINE」(ナノ・ジャスミン)の打ち上げを計画している。
Nano-JASMINEは質量35kgほどの小型衛星ながら高い性能をもち、ガイアとは別に独立して全天観測を行うことで、ガイアの観測結果を検証したり、ガイアが観測できない6等以上の明るい星を観測し不足分を補ったりすることができる。さらにヒッパルコスやガイアの観測したデータと組み合わせることで、さらに精度が高く詳細な星図も作れるという。
衛星自体はすでに完成しているものの、打ち上げるロケット側の都合で足踏みする状態が続いており、現在のところ打ち上げ時期は調整中だという。またNano-JASMINEの次には、400kg級の「Small-JASMIN」や1.5トン級の「JASMINE」といった後継機の計画もある。
参考
・Gaia creates richest star map of our Galaxy - and beyond / Gaia / Space Science / Our Activities / ESA mobile
・Gaia’s sky in colour / 04 / 2018 / Images / ESA Multimedia / ESA Online Videos
・Gaia / Space Science / Our Activities / ESA
・Billion-star map of Milky Way set to transform astronomy
・JASMINE
著者プロフィール
鳥嶋真也(とりしま・しんや)宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。国内外の宇宙開発に関する取材、ニュースや論考の執筆、新聞やテレビ、ラジオでの解説などを行なっている。
著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)など。
Webサイトhttp://kosmograd.info/
Twitter: @Kosmograd_Info