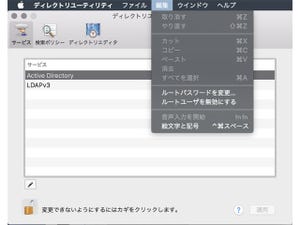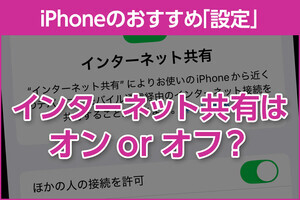対してGoogleは、Googleアシスタントという「賢さの象徴」が据え置かれており、文字や画像、声の主の判別までこなしてしまう人工知能のパワフルな成長は、分かりやすい「未来」の提示といえる。
Googleアシスタントによる未来を感じられるスマートフォンがPixelであり、スマートスピーカーがGoogle Homeであり、ラップトップがPixelBookであるというマーケティングは、非常に利にかなっているし、何より分かりやすい。HTCの部門買収で他のAndroidメーカーのことを考えなくなったことも、こうしたメッセージを打ち出しやすくするため、と指摘できるかもしれない。
Steve Jobs氏が亡くなった年に発表されたiPhone 4Sには、すでに人工知能を導入した音声アシスタント「Siri」が搭載されていた。現在はiPhone、iPad、iPod touch、Mac、Apple TV、Apple Watch、HomePodといったあらゆるハードウェアにSiriが搭載されている。
ここまであらゆる製品にSiriが搭載されているのであれば、Siriをコンピューティングの中心的な存在として打ち出していくことで、Googleに対抗することができるのであるが、Appleはプライバシー情報を端末外に持ち出さない、というスタンダードを各デバイスに適用しているため、Googleアシスタントのようにクラウドを使ってさらに賢く、という方法論を用いることはできない。そこは、Appleらしい手法を採る必要がある。
現在もそうだが、SiriはiOS自体の機能として用意されており、Siri Kitと呼ばれるAPIを通じて、一部のアプリが、Siriからアプリの機能を利用することができるようになっている。通話、メッセージ、配車アプリ、写真検索、メモやリマインダー、個人間送金、ワークアウト、スマートホームなどが、Siriを活用できる代表的なアプリだ。
AppleはSiri Kitについては、筆者が想像している以上に慎重に事を運んでいるという印象がある。2016年にiOS 10でSiri Kitが6つのアプリカテゴリ向けに開放され、2017年のiOS 11ではそうしたカテゴリの制限が撤廃されると思っていたが、実際にはカテゴリ制限が撤廃されたり、大きく緩和されることがなかったからだ。
そんな按配で、慎重路線で進んでいるが、Siriのキャラクターを立たせたり、Siriがより便利に活用される未来についても、やはりアプリ開発者次第、というのが現状なのだ。

|
松村太郎(まつむらたろう)
1980年生まれ・米国カリフォルニア州バークレー在住のジャーナリスト・著者。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、キャスタリア株式会社取締役研究責任者、ビジネス・ブレークスルー大学講師。近著に「LinkedInスタートブック」(日経BP刊)、「スマートフォン新時代」(NTT出版刊)、「ソーシャルラーニング入門」(日経BP刊)など。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura