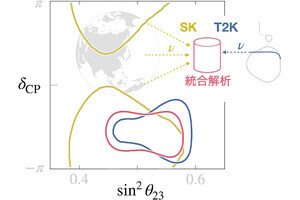理化学研究所(理研)は11月22日、DNAの損傷を修復して細胞ががん化することを防ぐ酵素「MutL」の、機能制御に重要な箇所を新しく発見したと発表した。発見は理研放射光科学総合研究センター飯野均特別研究員や倉光成紀グループディレクターらによるもので、成果は米科学雑誌「The Journal of Biological Chemistry」12月9日号に掲載される予定で、それに先だち日本時間12月3日付けのオンライン版に掲載される。
紫外線や放射線などの外的要因や、細胞分裂の際の複製エラーといった内的要因によって絶えず損傷を受けているのがDNAだ。そのため、DNAはさまざまな種類の損傷修復機構を備えている。
中でも、複製コピーでの間違えた組み合わせを見つけ出して除去することで修復する「ミスマッチ修復系」が機能しなくなると、大腸や子宮内膜、卵巣、胃など多臓器でのがんの発症リスクを高める遺伝性疾患の「リンチ症候群」になることが知られている。
DNAは、相補的2本鎖構造により、その遺伝情報を保っているが、複製エラーが起こると、遺伝子配列にミスマッチな部分が生じてしまう(画像1)。ミスマッチ修復系には、DNAのミスマッチ部分を見つけ、どちらが正しい配列かを判別し、エラー配列を持つDNAだけを切断し、正しい配列のDNAを相補鎖に合わせて合成するという複数の能力が必要となる。そのため、複数種類の酵素が協調して働く巧妙なメカニズムが存在するものと推測されている次第だ。

|
|
画像1。DNAの複製エラーによってミスマッチ部分が生じる仕組み。正常なDNAは相補的2本鎖構造を取っており、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4種類の塩基は相補的塩基対(A-T、G-C)を形成している。しかし、DNAの複製エラーによって、画像中のG-Tの例のようにミスマッチな塩基対が生じる場合がある。これを除去し修復するのがミスマッチ修復系だ |
MutLはミスマッチ修復系の中で中心的な役割を担っている酵素であることから、ミスマッチを見つける酵素や正しい配列を判別する酵素と相互作用しながら、エラー配列を持つDNAだけを切断していると予測されている(画像2)。MutLは通常、正常なDNAを切断してしまわないように抑制され、適切な場合だけ働くように制御されているはずだが、その仕組みが不明な点が多い。

|
|
画像2。ミスマッチ修復系におけるMutLの働き。MutL(青)は、DNA上のミスマッチ部分を見つける酵素(緑)と、2本鎖DNAの内どちらがエラー配列なのか認識する酵素(黄)と連携しながら、エラー配列のDNAだけを切断する。MutLのDNA切断活性は、通常は抑制されているが、適切な場合(4の状況)にのみ機能を発揮するように調節されていると考えられている |
これまで、MutLやミスマッチ修復系の研究は、主に大腸菌やヒトの酵素を用いて進められてきたが、大腸菌のミスマッチ修復系は他の生物とはMutLの機能が異なるという問題があり、一方のヒトの酵素は不安定で壊れやすく生化学的な実験に向いていないという問題があった。
そこで研究グループは、全生物の共通先祖に近いといわれ、1998年にゲノム解析が終了した超好熱性細菌「アクイフェックス」のMutLの機能解析を行うことにしたのである。アクイフェックスのMutLは、ヒトと基本的な機能が同じ上に、安定していて壊れにくいことから、選ばれたというわけだ。
MutLは2つの分子が結合した形を取る酵素だ。1分子中にATP(アデノシン三リン酸、生体内で用いられるエネルギーのほとんどを媒介する)が結合する部分を持つ「ATP結合ドメイン」とDNAを切断する役割を担う「エンドヌクレアーゼドメイン」の2つのドメインを持つ。そして、エンドヌクレアーゼドメインを介して2分子が結合している(画像3)。ドメインとは、酵素などのタンパク質は約20種類のアミノ酸が直線上に連結しているが、それらがヒトかマリになった単位のことを呼ぶ。

|
|
画像3。MutLの分子構造モデル。MutLは1分子中にATP結合ドメインとエンドヌクレアーゼドメインを持ち、2分子(赤と紫)がエンドヌクレアーゼドメインを介して結合した形を取っている。ATP結合部分(オレンジ)にATPが結合したり、外れたりすると、ATP結合ドメイン全体の形が変わり、亜鉛結合部分(黄緑)を介してDNA切断活性部分(水色)を制御すると考えられている |
これまでに研究グループでは、ATP結合ドメインがATPの結合をスイッチにしてエンドヌクレアーゼドメインのDNA切断活性を制御していること、すなわち「ATPが結合しているとDNA切断活性が抑制され、ATPが外れた時(外れている時)に逆にDNA切断活性が促進されること」、「ATP結合に伴ってATP結合ドメインの形が構造変化していること」、「エンドヌクレアーゼドメインには亜鉛結合部分があり、この部分がATP結合ドメインとの仲介に必要なこと」を明らかにしてきた(画像3)。
研究グループはMutLにATPが結合することによってDNA切断活性が抑制される仕組みをさらに詳細に知るため、重水素交換法と質量分析法を組み合わせた手法を用いて、ATP結合が引き起こす構造変化が2つのドメイン間の接触をどのように変化させるかを解析。その結果、機能に関わると思われる新規領域の特定に成功したのである(画像4・A、B)。
さらに、ATP結合ドメイン中の領域(画面4・A)の周辺と、エンドヌクレアーゼドメイン中の領域(画像4・B)の一部に、ヒトを含めた多種生物のMutLが共通に持っている推定機能箇所をそれぞれ発見した。
これら2つの推定機能箇所は、ATP結合ドメインとの仲介に必要であるとされる亜鉛結合部分(画像3・黄緑)と、DNA切断活性部分(画像3・水色)に近接しており、これまでに研究グループが明らかにしてきた知見を裏付ける結果となったのである。
続いて、2箇所の推定機能箇所を欠いた、もしくは異なる種類のアミノ酸に置換したMutL変異体を作成して評価したところ、ATP結合ドメインが持っているはずの制御機能やエンドヌクレアーゼドメインが持っているはずのDNA切断活性が失われることを確認した。
MutLの2分子は、エンドヌクレアーゼドメイン中の推定機能箇所で交差しながら結合していたことから、DNA切断活性を発揮するためには、2分子が結合する必要があることも明らかになったのである(画像4の丸囲み)。このことは、どのようにしてMutLが2本鎖DNAの内のエラー配列を持つ方だけを切るのか、というミスマッチ修復系メカニズムの本質と関わりがある可能性を持つ。
また、実際にリンチ症候群の原因になった遺伝子異常箇所と照らし合わせたところ、この推定機能箇所(画像4のB)に生じた遺伝子異常がリンチ症候群の原因の1つであることも判明した。つまり、この箇所の異常はMutLのDNA切断活性を失わせ、DNA修復系を機能不全に導き、結果的にリンチ症候群を引き起こすものと考えられている。
研究グループは、今回の発見でMutLの活性制御機構で重要な役割を持つ箇所が明らかになったことから、今後はMutLが具体的にどのようにエラー配列を持つDNAに結合して切断するのかについて、分子機構レベルで解明を目指すという。そしてミスマッチ修復系で協調して働くMutL以外の複数酵素トドのように関係しているのかを明らかにし、ミスマッチ修復系のシステム全体を解明していく。それらの研究の過程で、リンチ症候群の新しい予防法や治療法の発見も期待できるとした。
さらに、DNA修復機構は全生物が共通に持っている生命現象の根幹的なシステムの1つであることから、仕組みの全体を解明することで、原初の生命からヒトまで全生物の基盤的な仕組みを深く理解できるようになるともしている。