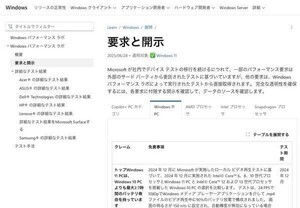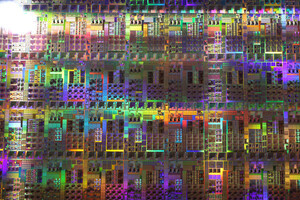健康管理機器が相互接続

|
|
インテルの代表取締役社長である吉田和正氏 |
ガイドラインを取り巻く状況として、インテルの代表取締役社長である吉田和正氏は、「2006年6月から作業を開始したガイドラインもようやく2009年1月に完成した。これにより、ICT技術と各種健康管理機器の相互接続や相互運用を確保できるようになり、普段使っているPCや健康器具が簡単に繋がるようになるわけで、これは非常に大切なマイルストーンとなる」と語る。

|
|
健康管理機器は、現在はスタンドアロンでの管理だが、今後はネットワークを介して一元的にそれぞれから集めたデータを管理することができるようになる。そのため、「今後はインターネットを活用して、その中のサービスと組み合わせることも可能となる」(吉田氏)とし、「目的を持って楽しく自分で健康管理ができるようになるための始まりの時だ」(同)と語る |
すでに日本市場に向けて、ガイドラインに準拠した製品やサービスの開発が14社で行われており、その種類も 歩数計や血圧計などの健康管理機器、PCなどのデータ管理機器、データ管理ソフトやコンサルサービスといったソフト・サービスと多岐に分かれている。

|
|
シャープ 研究開発本部 健康システム研究所 eヘルスケア研究室長 花田恵太郎氏 |
具体的なガイドラインの中身だが、「Continuaは、標準化を行う団体ではないため、世の中にある規格を選定したにすぎない。ただし、その実装方法も規定したことで、機器を設計・製造する上での負担を軽減することが可能になる」(シャープ 研究開発本部 健康システム研究所 eヘルスケア研究室長 花田恵太郎氏)とのことで、実際にはIEEEで規定されている健康に向けた規格を各種取り入れ、それをBluetoothならびにUSBに組み込んだ形となっている。
ワイヤレスではBluetoothが用いられるが、これに「Bluetooth Health Device Profile Specification」と呼ばれるIEEEで規定したフォーマットを取り込むことで健康器具との接続が可能となる。
なお、パーカー氏によれば、ContinuaではBluetoothやZibBeeなど5種類のワイヤレス規格の認証が進められているとのことなので、将来的にはBluetooth以外のネットワークで接続もできるようになるかもしれない。また、Wi-Fiでの接続に関しては、消費電力の問題などはあるものの、すでに技術としては一般的なものであり、わざわざ認証する必要もないから除外しているとのことである。
ちなみにUSBに関しては、「USB Personal Healthcare Device Class Specification」を採用しているとのこと。
また、対象となる機器としては、「パルスオキシメータ」「血圧計」「体温計」「体重計」「血糖値測定器」「フィットネス機器」「生活活動モニタ」の7種類であり、「機器もIEEEで規定されており、その中で家庭内で使用されている頻度の高いものを選んだ。こうした機器間でのデータの相互活用も可能となる」(花田氏)という。
認証プログラムの運用も開始

|
|
パナソニック AVコア技術開発センター ヘルスケア開発室長 南公男氏 |
Continuaでは、2009年1月より、「コンティニュア認証プログラム」を開始、これにより「ガイドラインに準拠した製品やサービスであることを認証し、ユーザーがコンティニュア準拠を確認できるような認証ロゴの添付などを推進する」(パナソニック AVコア技術開発センター ヘルスケア開発室長 南公男氏)という。
また、今後のガイドラインの改訂については、「健康管理機器の範囲の拡大を目指すほか、より低消費電力の無線技術の実用化、PCなどでのデータ管理からインターネットサービスを活用するための接続規格の規定などを進めていく」(同)とする。
なお、日本市場については、Continua準拠の製品、サービスの早期提供に向け、参照用のソースコードなどの提供や開発者向けコミュニティの形成を図っていくほか、ブランド認知度向上のためのプロモーション活動や慢性疾患の予防の管理での利用に向けた政府機関への協力などを行っていくとする。