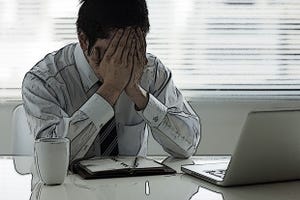若い世代のビジネスマンにとって、社内外でのコミュニケーションが悩みの種である人は多い。そんな人にもってこいなのが『お笑い』のスキルである。
ここでは、芸人として6年活動するもトリオを解散。その後、新たな人生のスタートとして企業コンサルや人事業務の経験を積み、芸人向けの人材サービスやお笑いを取り入れた企業コンサルを行う「芸人ネクスト」の代表取締役社長・中北朋宏氏に『スベらない仕事術』を聞いてみた。第1回のテーマは「『お笑い』は仕事に使える!」。
そもそも、ビジネスと『お笑い』の相性は良い
お笑いに関わる職業といえば何? そう、聞かれれば、お笑い芸人と答える人が多いはず。だが「スカブラ」が頭に浮かんだ人は、どれほどいるだろうか。
「かつて炭鉱業が盛んだった時代、屈強な炭鉱夫たちが集う職場に、ヒョロヒョロとした見かけの人々が共に働いていたそうです。その人々は『スカブラ』と呼ばれ、炭鉱内で労働を行うのではなく、炭鉱夫たちに話を披露することを生業にしていました」と、中北氏は話す。
スカブラの人々は、炭鉱夫たちが危険な現場から休憩にくると、そこで笑い話や猥談をする。そうやって愉快な話を通じて、労働者たちのストレスを抜くのが彼らの役割だったそうだ。だが炭鉱業が下火になったとき、経営者からみて生産性がないスカブラの人々は真っ先にリストラされたという。そして、スカブラがいなくなった現場の生産性はどんどん下がってしまった。
一見、役立たずに見えるスカブラ、つまり『お笑い』は現場になくてはならない存在だったのだ。これは炭鉱業だけに適用される話ではない。中北氏は笑いとビジネスの関係性を次のように語る。
「月並みな言い方ですけど、『イノベーティブな発想は笑いがあると起こりやすい』と言われています。笑いがある職場では、心理的安全性が高まって本音が出やすくなり、オープンマインドになる。意見を述べやすい空気が生まれます」
『お笑い』筋トレで誰でも面白くなれる
とはいえ、テレビで活躍する芸人たちのように面白い話をするのは、なかなかハードルが高いように思える。「お笑い」スキルを身につけるにはどうすればよいのか。
「実は、笑いには『伝える順番』があります。その仕組みを知れば、誰でも『笑い』のスキルを習得できると考えています。例えば、テレビ番組でも有名なお笑い芸人さんたちの『スベらない話』の構造を分析すると非常に分かりやすいと思います」と、中北氏が笑いの仕組みについて話す。
ここでいう仕組みとは「フリとオチ」と呼ばれるものである。
また、中北氏は「お笑いのスキル習得は筋トレに似ています」と例える。人によって、筋肉の付き方が違うように、面白くなりやすさにも違いがある。しかし、ちゃんとトレーニングをすれば、誰でも筋肉を鍛えられるように、人は面白くなれるのだという。
『お笑い』が潤滑油となるビジネスシーンは多彩
お笑いスキルは、どのようなビジネスシーンで使えるのだろうか。中北氏は「お笑いスキルは様々なシーンで活用することができると考えています」と話す。以下の通りだ。
・上司部下の関係性の質の向上
上司と部下の関係性をより良いものにできる。関係性の質が低いと、たとえ1on1ミーティングのように対面で話し合いをしても空回りしてしまうことが多くある。ピリピリとした空気では、伸び伸びとした議論はできない。だが笑いを活用し、関係性の質を高めることができれば本音を引き出すことができる。
・営業成功率の上昇
もちろん、対外にも笑いはその力を発揮する。商談やプレゼンテーションであっても、フリとオチの構造を理解した流れを作れば、ただ真面目な話展開よりも相手の興味を喚起することができる。
・チームワークの向上
笑いには、チームの団結力を強める力もある。営業チームだけでなく、エンジニアチームやデザイナーチームに実践して効果を発揮した例もある。アイスブレイクによって、緊張状態ではなく、和やかな空気でチームを動かす。チーム内で上手に「イジり」と「返し」の応酬をさせることで、笑いのあるチームを築ける。
次回からは、お笑いのメカニズムを応用した実践的な『スベらない仕事術』を紹介していく。自分のビジネススタイルに取り入れれば、『お笑い』スキルのレベルを格段に上げられるに違いない。