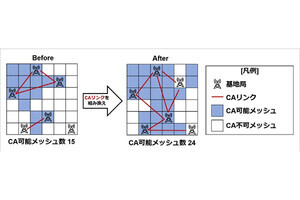DXの波に乗れず「DX漂流者」となってしまった中小企業の方を助けるソリューションを紹介する本連載。第2回ではクラウド型のビジネスフォンシステム「Dialpad」をピックアップする。
いま、日常業務のさまざまな部分でクラウド移行が進んでいる。その一方で、日々のビジネスに不可欠でありながらクラウド化がまだ進んでいないものとして、電話がある。中小企業がDXに向け着実な一歩を踏み出す足がかりとして電話のクラウド化はどのような効果をもたらすのだろうか。
「Dialpad」を提供するDialpad, Inc.の日本およびAPACのGMである安達天資氏と、国内で同システムの販売を独占的に手掛けるソフトバンクのビジネスアライアンス本部 営業支援統括部 ソリューション企画部 担当部長 遠藤裕和氏、ソリューション企画部 ソリューション企画課 遠藤寛和氏に話を聞いた。
自宅からでも会社電話に対応できるクラウドPBXという選択肢
企業における電話は、PBXと呼ばれる構内電話交換機を介して電話回線と接続し、外部とのやりとりを社員個々の机の上にある固定電話で行うのが当たり前だった。いうまでもなく、社員は電話を受ける際、電話機の前にいる必要がある。ところが、今は物理的な電話回線とPBX、そして固定電話機を使うことなく、インターネットを通じ、パソコンやスマートフォンから通話できるようになっている。つまり電話のクラウド化だ。
電話がクラウド化することで、何が可能になるのか。簡単にいえば、社員が自宅や外出先などどこにいたとしても、会社にかかってきた電話に応答できる。要するに、社員が固定電話のある場所に縛られなくなるわけだ。こうした動きはいまグローバルのトレンドとして進んでおり、日本でも導入企業が着実に増えているが、この流れが加速したのはやはりコロナ禍の影響が大きかったという。
「緊急事態宣言が出て会社に行けない事態になるなか、誰もいないオフィスで電話が鳴り、その電話に誰かが出なければビジネスが止まる、といったことが日本中で起きました。そのため、一部社員は電話を受けるためだけに出社しなければならなかったのです」(安達氏)
これを機に、どこにいても会社の電話に対応できるクラウド電話のソリューションが注目を浴び、大手から中小まで多くの企業でDialpadの導入が進んでいった。
当初はパンデミック下における緊急対応の側面が強かったが、リモートワークが多くの企業で浸透すると、Dialpadは多様で柔軟な働き方にマッチするソリューションとして注目度が高まった。新たな働き方を模索する企業においては、デジタル化による課題解決の手段としてこのDialpadを採用している。
その一方で、中小企業では情報システム部門で働く社員が一人や数人しかいなかったり、ほかの部署の業務と兼任していたりするのが実情。ほかにも解決すべき課題が山積している状態で「出社して固定電話を手に取れば受発信できる電話は、課題としての優先順位が低い、もしくはデジタル化で便利になることに気づいていないケースが多いのではないでしょうか」と安達氏は指摘する。
これについてはソフトバンクでソリューション企画や販売パートナーとの協業推進を担当する遠藤裕和氏も「デジタルのツールを導入しDXを実現することで何ができるようになるか、ソリューション提供側の私たちも経営者のみなさんを惹きつけるストーリー性を持った提案により力を入れていかなければ、DX漂流者をなくすことにはつながっていかないと考えています」と話し、デジタル化が進まない理由は企業側のみにあるわけではないとの認識を示した。
エンドユーザーの社員はもちろん経営者・管理者目線でもメリットが
Dialpadは、会社の代表番号や各部署の番号を使った電話をクラウド上で提供するクラウドPBXのサービスだ。社員それぞれのパソコンやスマートフォンから会社のさまざまな番号にかかってくる電話に応対できるので、わざわざ出社することなく、どこにいても会社の電話を利用することが可能になる。
このクラウドPBX機能を提供するのがDialpad Talkというツールだ。音声以外にビデオ通話やチャットも同じ画面内で利用でき、さらにはGoogle WorkspaceやSalesforceといった多種多様なビジネスツールとも連携して、電話に関わる業務の生産性を高める。
加えて、オフィスの電話だけでなく、コールセンター宛ての電話や、営業/インサイドセールスの電話に自宅等で対応できるツールも提供している。コールセンター向けツールのDialpad Ai Contact Centerは、スーパーバイザーがオペレーターのやり取りやパフォーマンスをダッシュボードから確認できる機能やモニタリング等一般的なコールセンターに必要な機能を網羅。また営業向けツールのDialpad Ai Salesは、SFA/CRMとの連携や、通話データを基にした分析、社員向けのトレーニングなどが可能だ。いずれももちろんインターネットとスクリーンさえあれば利用でき、場所を問わず生産性を高めることができる。
Dialpadの最大の特徴は、「シンプルかつ直感的に使えるインターフェース」だと安達氏。「使いやすく、わかりやすいのがポイントで、エンドユーザーの社員に便利なだけでなく、管理者も専門知識なしで設定できますし、グローバルのクラウドインフラで提供されるため冗長性・可用性を確保でき、災害時でも継続して利用できる点が強みです」と話す。
管理者目線では、社内のレイアウト変更や部署移転を行う際の配線作業をベンダーに発注すると高額の費用が必要だったところ、クラウド化することでそのコストやメンテナンスの手間がなくなる点もメリット。また経営者目線でも、従来、PBXの購入や工事には高い費用を要したが、クラウドPBXなら大幅なコスト削減が可能になるところは魅力になるだろうと語った。
ソフトバンクは独占販売の総代理店的位置づけにあり、自社の直販部門で販売するほか、販売パートナーからもDialpadを販売している。ソフトバンクで法人営業や販売パートナーとの取り組みを前出の遠藤裕和氏とともに進める遠藤寛和氏は、顧客対応における“スピード感”もDialpadの強みだと話す。
「たとえば会社の代表番号を1つ用意したいとの要望があれば、1週間程度ですぐに提供できます。また、DialpadはクラウドPBXサービスなので、ユーザー数の増減にも柔軟に対応ができます。販売面ではDialpadの営業の方がとにかく素早く対応しますし、お客さまとのコミュニケーションも遠隔からきめ細かく行ってくれるので、当社の直販部門も販売パートナーさまも本当に助かっています」(遠藤寛和氏)
ソフトバンクと力を合わせてクラウド電話の高度化に突き進む
これまでの具体的な導入成果としては、前出の「どこにいても会社の電話に対応できる」点や「従来のPBX装置利用時におけるコストや保守・メンテナンスの負荷が下がる」点のほか、安達氏は次のような事例も挙げる。
「ある企業では会社に注文の電話がかかってきたとき、これまでは担当者がその場にいないと受注できず機会損失につながり、結果的に顧客満足度も下がっていたといいます。Dialpadを導入することで、そうした事態を防ぐことができたとの声をいただいています。また、ある企業で東京に単身赴任していた社員の方が、Dialpadのおかげで在宅勤務でも電話を取れるようになったため、家族の住んでいる北海道に戻って仕事を続けているという喜びの声もお聞きしています」(安達氏)
そのほか、Dialpadは通話をすべて録音できるので、社員がコンプライアンスに反する電話やハラスメントにつながる電話をしていないか確認できたり、営業効率を高めるため録音内容をもとに指導したりといったケースもあるようだ。
今後については電話のクラウド化をさらに広げるとともに、それをベースとして、AIによる日本語通話内容の文字起こしとテキスト分析結果の活用、コールセンターにおける顧客の声からの満足度判定やオペレーターのパフォーマンス評価などを進めていきたいと安達氏は語った。これらのAI活用はすでに英語では高いレベルで実現できており、日本語での実用化が待たれるところだ。
こうした未来を実現していくうえで、「AIやコミュニケーション、サイバーセキュリティなどさまざまな分野に積極的に取り組むソフトバンクの存在は、本当に頼もしいですね」と安達氏。
DX漂流者となっている中小企業に向けては「当社Dialpadも含め、SaaSとも呼ばれるクラウドサービスの良さはすぐに導入でき、いつでも解約できること。いくらでもトライアンドエラーできます。日々のお仕事の中で『これなんとかならないの?』、『もっとこうできたらいいのに』と感じたときは、それを解決し改善するチャンスですし、それがDXで漂流しないというマインドセットなのだと思います。どんな課題でも、世の中にはそれらを解決・改善できるクラウドサービスが必ずあるので、まずは一歩踏み出し、ぜひチャレンジしていただきたいですね」とメッセージをくれた。
ソフトバンクもDialpadとの協業をさらに高度化し、中小企業の生産性や業務効率、人材不足など多種多様な課題の解決をサポートするため、今後もより力を入れて取り組んでいく考えだ。
[PR]提供:ソフトバンク