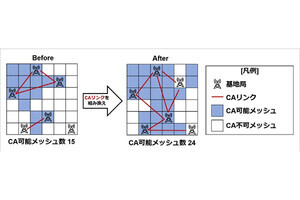阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から14年が経過した。それでもなお、2024年1月の能登半島地震の被災者の多くは、今も仮設住宅での生活を余儀なくされている。災害大国日本において、なぜ地域防災は進まないのか。
豊富な研究成果や先進的なソリューションが存在するにもかかわらず、それらが地域に根付かない現実。この課題に正面から挑むべく、NTT東日本は2025年4月に地域防災の新たな仕組みを研究する「防災研究所」を設立した。同研究所が掲げる究極の目標は「『防災』という言葉をなくすこと」。災害時だけの特別な対応から脱却し、平時の暮らしに有事への備えを自然に組み込んだ社会システムの構築を目指す。防災研究所所長の笹倉 聡氏とビジネスイノベーション本部の苫米地 崇之氏に、その全貌を聞いた。
平時から有事までの途切れない支援を通じて得た、現地現場の経験
NTT東日本グループにおける防災の取り組みは、一朝一夕に築かれたものではない。その根底には、通信インフラを死守し、被災地の情報をつなぎ続けるという、指定公共機関としての使命感がある。ビジネスイノベーション本部で防災ソリューションを担当する苫米地氏は、防災への基本姿勢をこう語る。
「我々ビジネスイノベーション本部は、防災ソリューションの提供を通じて地域レジリエンスの強化を目指しています。特徴的なのは、平時から有事まで、つまり災害発生前、発生直後、そして復旧・復興に至るまで、あらゆるフェーズに対応したソリューションを幅広くラインナップしている点です。直接的な災害の軽減は難しいものの、被害の最小化や地域住民の方々の早期生活再建を支援するという観点で、自治体のオペレーション効率化や意思決定の迅速化をサポートしています」(苫米地氏)
たとえば、同社が提供する「被災者生活再建支援システム」は、現在300以上の自治体で利用され、人口カバー率は50%に迫る勢いだ。能登半島地震でも活用された。災害時には可能な限り人員を派遣し、同システム運用を支援。ドローンを活用した被害判定にも取り組むなど、被災した住民の早期生活再建に貢献すべく、現地での支援も行ってきた。
「発災時には我々も現地に駆けつけ、システムの運用を支援してきました。こうした現地現場での自治体の皆さまとの経験こそが、我々の強みです」と苫米地氏は語る。
現場で見えてきたのは、「社会システムそのものの限界」という根本的な課題
しかし、近年の災害は激甚化・頻発化し、その様相も複雑化している。少子高齢化や地方の人口減少といった社会構造の変化も、地域防災のあり方に大きな影響を与えている。苫米地氏は、こうした現状に対する課題意識が、防災研究所設立の背景にあると指摘する。
「現在の社会システムや自治体の課題を前提としたソリューション提供が我々の基本ですが、社会課題や災害の状況が変化するなかで、NTT東日本が持つ災害対応の経験や地域の皆さまとのつながりを活かし、社会システムそのものへアプローチが必要だと感じていました」(苫米地氏)
深刻なのは、日本の地域防災が長年にわたって本質的に変わっていないという現実だ。「災害対策基本法が制定された約70年前から、地域の防災のあり方はほとんど変わっていません。素晴らしい研究成果や防災に使える実装ソリューションがありながら、それが地域に根付いていないのです」──こう指摘するのは、防災研究所の所長を務める笹倉氏だ。
災害に屈しない暮らしを日常に——防災研究所が目指す究極の目標
こうした現場の課題意識と、経営トップの「長年培った知見を地域に早期に実装したい」という強い思いが結実し、2025年4月、NTT東日本 防災研究所が設立された。
笹倉氏は、その究極の目標を「『防災』という言葉をなくすこと」だと語る。
「『防災』と一口に言われがちですが、たとえば医療や交通といったものと並列に『防災』が独立しているのは少し違和感があります。社会の基盤となっているすべての分野に防災の要素を埋め込む社会にしていくことが、研究所の究極の目的です」(笹倉氏)
これは、災害時だけの特別な対応という従来の概念から脱却し、平時から有事への備えが自然に組み込まれた「フェーズフリー」な社会システムを構築していこうという発想だ。
「たとえば、高齢者の方々が普段からスマートフォンを使いこなせる環境をどう整備するか。災害に対応した暮らしの形を実装するための社会変革を促す組織として立ち上がったのが、防災研究所です。こうした変革を実現する鍵は、民間企業が持つデジタル技術です。私たちはデジタルで解決できることはデジタルで解決するという方針のもと、地域の暮らしに還元されるところまで責任を持ちます」(笹倉氏)
15年の災害対応経験が裏付ける実践的アプローチ
笹倉氏は15年にわたる災害対応経験を持ち、東日本大震災では、NTTの災害対策室で統括者として従事した。「政府とは、燃料調達や原子力発電所周辺エリアの復旧順序、また首都圏で多発した計画停電において、対象となる通信局舎の停電を回避するための調整などを行いました」と振り返る。
この経験から得た重要な教訓は、民間企業連携の必要性だった。「通信事業者だけでなく、電力会社や高速道路会社、報道機関など民間企業との連携を図りながら、途絶しているエリアを集中的かつ段階的に復旧していく」(笹倉氏)という発想は、現在の防災研究所の活動にも受け継がれている。
NTT東日本グループ全体としても、指定公共機関として災害発生時の通信復旧責務を負ってきた企業としての経験を蓄積。現在では、災害対策本部のデジタル運営や意思決定に資する情報インテリジェンス化に磨きをかけ、迅速かつ高度な判断ができる状態としている。
「地域やライフラインの情報などをすべてデジタルで収集する仕組みを構築し、分析を行い、ボトルネックになっているエリアはどこなのかを明確にできる状態にし、意思決定が速やかにできる仕組みを作ってきました」(笹倉氏)
3つの重点研究で、いのちを守る仕組みを構築する
防災研究所では現在、3つの重点研究テーマに取り組んでいる。いずれも避難における初動の迅速化と、命を失うリスクが高い高齢者や障がい者の方々をいかに守っていくかという点に重きを置いた取り組みだ。
1.人流データを用いた避難状況予測に関する研究
東京大学 先端科学技術研究センター 廣井悠教授との共同研究では、気象データ、インフラ状況、人の動きといった過去の災害発生時の地域データや平時・有事の人流データなどをAIに学習させ、特定のエリアで災害が発生した場合の人々の避難行動を予測することを目指す。この予測結果をもとに、発災初期段階から防災リソースを最適に配置し、命を守る体制を構築することが目的だ。
2.自治体の災害対策本部運営の最適化に関する研究
東京大学 生産技術研究所 沼田宗純准教授との共同研究では、自治体が作成する災害対応検証報告書をAIに学習させ、過去の災害対応から課題を抽出し、発災時の各フェーズで求められる意思決定と必要情報をサポートする。これにより、災害の種別や規模・時系列に応じた自治体の行動パターンを標準化し、訓練や教育を通じて本部運営の実践力を高める。
3.要配慮者救済社会の創造に向けた研究
大阪公立大学大学院 文学研究科 菅野拓准教授との共同研究では、高齢者や障がい者といった、災害時において特に命を失うリスクが高い要配慮者をいかに守っていくかに焦点を当てている。自治体、福祉専門職、自主防災組織などによる支援体制や活動状況を調査・分析し、日ごろから誰がどのようなサービスで見守っているかを明確にするとともに、デジタルとアナログを組み合わせたフェーズフリーな地域支援ネットワークの構築を進めていく。
防災研究所では、官民連携でこれらのモデルを作り上げていくことが最優先事項として位置づけられている。「このモデルが確立されない限り、その先の避難所運営の質の向上や物資供給の最適化の効果は最大化されない」と笹倉氏は強調する。
これらの研究の具体的な実証フィールドとして注目されるのが、横須賀市を含む三浦半島での取り組みだ。能登半島地震を受けて横須賀市長が主導し、三浦半島4市1町の防災を一体的に強化するための協定を2025年5月に締結した。
この取り組みでは3つの大きなテーマを設定している。1つ目は、通信事業者としての責務である通信の応急対策の強化。2つ目は、三浦半島を仮想的に1つの街と考え、災害対策本部運営や避難行動・物資調達を半島全体で最適化するなどの次世代防災DXの推進。3つ目は、自治体の業務DXによる防災力の強化だ。「三浦半島発で『半島の防災はこうあるべき』という提言につなげていきたい」と笹倉氏は意気込む。
「30点でも良いから、まずはやってみる」——実装重視で社会変革を加速
従来の研究機関と一線を画すのが、実装を重視する姿勢だ。
「我々は研究者だけの集団ではありません。仮説を立て、地域のご理解を得て、とにかく実証を繰り返す。そこで得られるのは学術的なエビデンスだけでなく、現場の生の声です。それを国に提言し、多くの民間企業に賛同していただく。最初から100点満点を目指すのではなく、30点でも良いからまずはやってみる。それがNTT東日本の防災研究所らしさだと考えています」(笹倉氏)
単独での取り組みではなく、業界全体での協調領域の構築も重視している。現在、民間事業者・自治体などで構成される「防災DX官民共創協議会」において、初動の避難誘導を一連のプロセスとして標準化するワーキンググループが新たに立ち上がり、防災研究所が責任の一端を担っている。
"縦割り"の壁を越えて
防災研究所が描く未来の社会では、「防災」は特別なものではなく、あらゆる社会活動に自然に組み込まれている。医療、交通、物流、福祉——それぞれの分野が、平時から有事の継続性を見据えた仕組みを持つ。
「たとえば、医療と道路は密接に関係しています。いくら病院の機能が優れていても、道が寸断されれば薬は届きません。こうした依存関係を平時から意識し、有事にも機能するデジタル社会を構築していくために、『災害時のシステム』ではなく『フェーズフリーなシステム』を提案していきたい」と笹倉氏は展望を示す。
このビジョンを実現するうえでの最大のハードルは"縦割り"だと笹倉氏は指摘する。省庁間、自治体の部局間、あるいは官民の壁。これを乗り越えるためには、エビデンスに基づいた効果の提示と、関係者を巻き込んだ合意形成の場づくりが不可欠だ。NTT東日本の役割について、笹倉氏は「自治体を中心にさまざまなステークホルダーが協調できる『器』を作り、ともに理想的な社会の実現を目指していく。我々は、黒子としてその下支えをしていければ」と語る。
防災研究所の挑戦はまだ始まったばかりだ。しかし、その視線は明確に日本の未来を見据えている。デジタルの力と人々を融合させ、地域社会とともに、災害に屈しないしなやかで強靭な社会を築き上げていく。その先に、「防災」という言葉が必要なくなる日が来ることを信じて。
関連記事
関連リンク
[PR]提供:NTT東日本