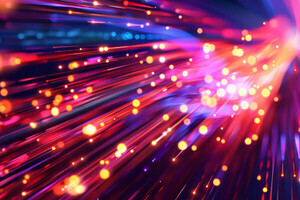クラウド利用が当たり前となりつつある昨今、クラウドへの移行やクラウドシフトの方向性を考えることは企業にとって大きな課題だ。そのようななか、NTTデータグループとして豊富な経験と実績を持ち、クラウドネイティブでのアプリケーション基盤構築を得意とするのがNTTデータ ニューソンだ。本稿では、クラウドインテグレータとしてユニークなポジションにいる同社に、クラウド移行やクラウド開発のポイントを聞いた。
クラウドが事業に不可欠となるなか、課題に直面する企業が増加
日々の業務はもちろん、事業を進めるうえでも今や不可欠な基盤となったクラウド。従来オンプレミスで稼働してきた多くのシステムをパブリッククラウドに移行させる取り組みが活発化している。顧客管理や営業支援などフロント系のシステムだけでなく、生産管理や販売管理といった基幹システムをクラウドに移行するケースも増えてきた。
一方で、クラウドに移行したものの期待した効果が得られないというケースも増えている。例えば、利用コストが想定以上に増えたり、運用できる人材やスキルが不足したりといった課題に直面しやすい。その結果、オンプレミスに一部を戻そうという動きや、最適解としてのハイブリッドクラウドを選択しようという動きも目立つようになった。
ただ、ハイブリッドクラウドにすれば、コストや人員不足といった課題が解消されるわけではない。むしろ、オンプレミスとクラウドという複数の環境を管理しなければならず、事態がより一層複雑化するケースも増えている。
いったい何がクラウドの「正解」なのか。そんな問いに対して「あえてパブリッククラウドへの全面的な移行を推奨したい」と訴えるのが、NTTデータ ニューソンの江成洋一氏だ。江成氏はこう話す。
「クラウドに移行しても期待した効果が得られない、オンプレミスに戻したりハイブリッドクラウド構成にしたりしても事態が改善されない──。そうした問題が起こる最大の原因は、クラウドに適したアーキテクチャ、システム構成、組織体制になっていないことにあります。オンプレミスとまったく同じシステムをクラウドに構築しても、コストは下がりませんし、効率化も難しい。クラウドのメリットである柔軟性や拡張性、俊敏性なども得られません。クラウドに適したかたちにシステムを変え、企業としての組織や文化もクラウドに適したかたちに変えていくことが重要です。そうした取り組みをしやすいのがパブリッククラウドへの全面的な移行なのです」(江成氏)
あえて「パブリッククラウドへの全面的な移行」を推奨するワケ
江成氏が指摘する「クラウドに適したかたち」とは、クラウドネイティブと呼ばれるクラウドでシステム構築やアプリケーション開発・運用をすることを念頭に置いたアプローチだ。クラウド移行には、オンプレミス環境で構築・運用しているさまざまな業務システム・社内システムをクラウドの環境へ乗せ換える「クラウドリフト」とクラウドの環境に適したかたちでゼロからシステムを構築する「クラウドシフト」があるが、シフトのフェーズでクラウドネイティブ開発をしていくという。
「クラウドネイティブを実現するための重要な技術要素として、コンテナやマイクロサービス、サーバレス、APIなどがあります。クラウドに単にリフトするだけでなく、それらを使ってクラウドに適したかたちにシフトしていくことで、クラウドの課題を解消し、メリットを享受できるようにします。既存環境を仮想マシンなどの従来型技術でリフトするだけでは、クラウドの課題を根本的に解決することはできません」(江成氏)
クラウドの課題を根本的に解決するには、5つの取り組みが重要になる。この取り組みは企業が直面する「想定を超えた利用コストの増加」「開発スピード、移行性の低下」「アプリケーションの古いアーキテクチャからくる柔軟性や拡張性の欠如」「パブリッククラウド要員確保の難しさ」「運用負荷の増加」といった課題に真正面から対応していく取り組みとなる。
「利用コストを減らすには、クラウド特性を損なわずにシステムを安定稼働させるための高度な運用が必要です。また、開発スピードを上げるためには、迅速なサービス提供を可能にするプロセスの自動化がカギとなります。古いアーキテクチャに対しては、柔軟性と拡張性を最大限に活用したアプリケーション開発の仕組みを整備します。要員確保のポイントは、アプリケーション開発とオンプレミスの仮想化基盤プロジェクトを経験したフルスタック技術者を中心にしたプロジェクト体制を組むことです。こうした取り組みを通して、サービス全体の運用負荷を下げ、安定稼働を実現していきます」(江成氏)
NTTデータグループで唯一「クラウドネイティブ開発」を得意とする企業
システム規模が小さい場合や新規にシステムを構築する場合は、コンテナやマイクロサービスを活用したシステム開発にも現実味がある。実際、多くの企業が、新サービスや特定業務など対象を絞ってクラウドネイティブで開発をしている。
一方、基幹システムのように、システム規模が大きく、長時間のシステム停止を許容できないシステムをクラウドネイティブに移行することは極めて困難だ。安定稼働している既存システムに手を加えることで全体が影響を受けかねず、移行にも時間がかかる。移行できたとしても後戻りができないリスクが残る。退路を断って移行する決断をすることは、既存ビジネスが順調な企業ほど難しい。
「そのため、クラウドネイティブで大規模なシステム移行やシステム開発をする場合、段階的にクラウドネイティブな環境に移行していくことをお勧めしています。実際、われわれがサポートしているお客様の多くは、移行後のビジョンや移行の際のロードマップを策定し、長期にわたる取り組みのなかで、クラウドネイティブを社内に根付かせながら移行を進めていらっしゃいます。移行期間は、ハイブリッドクラウドのようなシステム構成になりますが、最終的なゴールは、全面的なパブリッククラウドへの移行です。そうした要件定義から設計構築、導入、運用保守までワンストップにて対応できる点がわれわれの強みです」(江成氏)
NTTデータ ニューソンは、NTTデータグループのクラウドインテグレータとして、金融、公共、医療、社会インフラなどの大規模システム案件を多数こなしてきた実績と経験がある。認定スクラムマスターなどの資格保有者が多数在籍しているためアジャイル開発を得意としており、クラウド技術についてもAWSパートナー企業としてAWS認定ソリューションアーキテクトなど認定資格保有者が多数在籍する。
「提供するサービスは、クラウドネイティブ開発、クラウド基盤構築、データ分析基盤構築、オンプレミス・仮想化基盤構築です。NTTデータグループとして唯一、クラウドネイティブ開発に特化してお客様を支援できることが特徴です」(江成氏)
スタート地点として「アプリケーション開発基盤」構築に取り組む
クラウドネイティブ開発のなかでも特にニーズが多いのがアプリケーション開発基盤の構築だという。 「全面的なクラウド移行を見据えて、まずアプリケーション開発基盤をクラウドネイティブで構築したいというお客様が増えています。開発基盤を整備するなかで、利用コスト増や人材確保、アーキテクチャ刷新、運用負荷低減といった課題に対応しつつ、クラウドならではの機能を最大限に生かしたサービスや組織、文化を作っていきます。われわれとお客様が一体となったプロジェクト体制のもと、お客様と一緒に取り組みを推進していきます」(江成氏)
こうしたワンチーム体制のもと、例えば、利用コストについては、知識と経験を持つSRE(サイト信頼性エンジニアリング)技術者が、クラウドサービスのコスト構造やコスト分析ツールの活用方法などを支援する。また、開発スビードや移行性を実現するために、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デプロイ)パイプラインやDevOpsなどのアプリケーションとIT基盤を円滑に連携する仕組みを構築する。古いアーキテクチャについては、マイクロサービスやAPI化などによるクラウド基盤を意識したアプリケーションのモダナイズを行う。チーム全体で対処することで人材不足やスキル不足という課題にも対応できる。その際には、NTTデータのガイドライン策定や技術者育成施策などを通じた組織体制づくり、技術力の強化、技術者の育成に貢献できる。
「金融業のお客様に対して、AWSを活用したブロックチェーンSaaS基盤を構築した事例があります。アプリケーション実行基盤としてKubernetesコンテナオーケストレータを活用し、Lambdaによるサーバレス基盤で運用作業を効率化しました。また、リリースやテストを自動化するためのCI/CD環境構築とアプリケーションチームへの技術支援も行ないました。これにより、基盤障害からの回復やリソース使用状況に応じた柔軟なスケーリング、開発スピードとリリース頻度、品質の向上を実現しました。 」(江成氏)
クラウド利用が当たり前になるなか、クラウドへの移行やクラウドシフトは大きな課題だ。そんななか、NTTデータグループとして豊富な経験と実績を持ち、クラウドネイティブでのアプリケーション基盤構築を得意とするNTTデータ ニューソンは、クラウドインテグレータとして極めて貴重かつユニークなポジションにいる。
「ソフトウェア開発技術を強みとして持ち、数多くのアジャイル開発手法を用いたパブリッククラウド上でのアプリケーショ開発を手掛けてきました。クラウドの導入をこれから検討している企業はもちろん、クラウドの活用に関して課題を抱えていらっしゃる企業はぜひお気軽に相談ください」(江成氏)