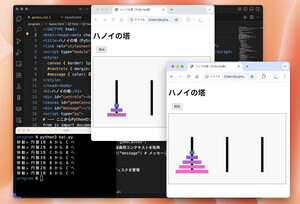頻発する自然災害や南海トラフ地震などのリスクを受け、防災の意識が高まる一方、地方自治体では避難所の整備や防災業務のDX化、体制構築、予算の確保など、少子高齢化や人手不足が進む中でさまざまな課題が山積している。NTT東日本グループはこうした自治体に向け、数々の災害復旧活動で培ったノウハウをもとに、地域レジリエンス強化を目指した包括的な支援を実施している。「地域循環型社会の共創」をパーパスに掲げる同社の防災事業について伺った。
-

(左) 東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 担当課長 田中 誉幸氏
(中央) 東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 担当部長 苫米地 崇之氏
(右) 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー 社会インフラデザイン部 地域あんしん推進部門 あんしんデザイン担当 担当課長 防災士 福田 祐大氏
頻発する自然災害、自治体の防災力が弱まっていることが浮き彫りに
2024年1月1日に発生した能登半島地震では、土砂崩れや液状化で交通インフラが寸断され、救助や支援が届かずに多くの集落が孤立した。また、情報通信インフラにも影響が及び、テレビやラジオが最大3週間停波したことは記憶に新しい。
こうした災害発生時に、災害用伝言ダイヤル(171)の無料提供や通信設備の復旧作業など、先陣を切って被災地支援にあたってきたのが、NTT東日本グループだ。長年取り組んできた復旧活動を通して、各自治体の防災に関する課題が浮かび上がってきたとNTT東日本 苫米地氏は語る。
「近年、これまでに比べ広域化・激甚化する災害に対応する体制を整えることが難しくなっています。地方においては、少子高齢化や都市部への人口集中の影響で自治体の防災担当職員の数が減るほか、すぐに対策を打ちたくても『何から手をつけるべきか分からない』、その結果どこから予算を措置し対策していくかといった点などに悩まれている状況です。災害ボランティアやリエゾン職員の受け入れ体制を整備するリソースも限られています。特に課題だと感じるのは、災害が頻発化・広域化など変化していく中で、自分たちの地域に防災力がどれくらいあるのか、各自治体の評価が十分ではないのではないか、という点です」(苫米地氏)
防災力とは、災害による被害を最小限に抑えるために、地域社会が備えている力のことだ。地震や台風、集中豪雨など前例のない自然災害に対し、十分な防災力が備わっていないがために、被害がより甚大になり、復旧に時間を要したケースもあるという。
-

東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 担当部長 苫米地 崇之氏
災害を自分ごととして理解するための「防災力の可視化」
いざという時に地域の防災力を高めるため、国や自治体はさまざまな防災・減災への呼びかけを行っているが、着実な成果を出している例は依然として少ない。この理由について、NTT東日本 田中氏は「災害を自分ごと化することの難しさが壁となっている」と語る。
「全ての自治体が災害を経験しているわけではないので、実際に被災して気付くことがあるのは当然です。私たちNTT東日本グループも、国営時代を含めて100年以上にわたり災害復旧活動に取り組んできましたが、2011年の東日本大震災で初めて経験することが多くありました。それは、発災時の情報収集や情報共有、情報機器が失われた中での業務の継続の難しさです。対応にあたった現場の社員は、救えるはずの命を救えなかったという辛さを、身をもって実感しています。こうした悔しい経験をどのように防災対策に落とし込むか。グループ全体で自治体サービスのレジリエンス強化に本格的に取り組むようになったのも、この頃からです」(田中氏)
実際に東日本大震災で復旧対応にあたったエヌ・ティ・ティ・エムイー 福田氏は、災害を自分ごと化するポイントの一つとして「防災力の可視化」を挙げる。
「防災と一口に言っても、取り組むべきことは多岐にわたります。そのため、ほとんどの自治体が『どこから手をつけていいかわからない』『予算をつけたいが明確な根拠がわからない』といった悩みを抱えています。まずは客観的な視点で自分たちの自治体の現状を確認し、災害対策においてどこがウィークポイントなのか評価することが重要です。そのうえで、明らかになった課題への対策に取り組むことがベストでしょう」(福田氏)
-

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー 社会インフラデザイン部 地域あんしん推進部門 あんしんデザイン担当 担当課長 防災士 福田 祐大氏
105個の質問項目からなるリスクアセスメント調査で弱点を知る
こうした防災力の可視化を実現するためにエヌ・ティ・ティ・エムイーが提供しているのが、独自のリスクアセスメント調査だ。
「NTT東日本グループはこれまで数々の被災地で支援を行ってきました。このリスクアセスメント調査では、そこで得た知見を災害対策プロセスに基づく105個のヒアリング項目としてまとめています。安否確認の方法や情報収集がきちんと行えるか、備蓄品の備えは十分か、避難所の運営方法が整備されているかなど、災害発生時のさまざまなリスクを洗い出すことが可能です」(福田氏)
この105個のヒアリング項目を通して、各自治体は自分たちの「備え力」と「実践力」を可視化することができる。これまで120以上の自治体が同社のリスクアセスメント調査を行ってきたが、多くの自治体において、命を守る観点での「備え力」が弱点となっていることが分かったという。
「備蓄品の管理は十分か、避難所まで住民を避難させる取り組みができているか、さらには避難所に誰がいるのかといった情報把握など、災害発生後における住民サポート面での防災力はまだまだ十分とはいえません。これらの効果的な改善策はないか、NTT東日本が4月に設立する防災研究所で研究を行っていきます」(福田氏)
調査結果をフィードバックするだけに留まらず、マニュアルの改定、ソリューションの提案など、自治体を包括的に支援できることもNTT東日本グループならではの強みだ。田中氏はその理由についてこう説明する。
「私たちは情報通信事業者であると同時に、ITベンダーでもあります。さまざまなICT導入やDXを推進してきた経験から、調査結果のフィードバックだけでなく、それを踏まえた対策の策定やソリューションの提供など、一気通貫でサポートできる点は強みといえるでしょう。こうした包括的な支援を実現できるのは、NTT東日本グループが国営時代から防災・減災に取り組んできた歴史があるからです。私たちのミッションは『地域の課題解決と価値創造、レジリエンス向上』であり、これまでの災害支援で培った知見を各地域にお返ししたいという思いは、社員一人ひとりに根付いています」(田中氏)
実際、NTT東日本の社員は各自治体で行う防災訓練に参加し、災害が発生した際は、各自治体と連携を図りながら被災地へ赴くという。能登半島地震でも、設備の復旧はもとより、自治体職員のサポートを現地で実施した。
-

東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 担当課長 田中 誉幸氏
NTT東日本グループが持つ防災のノウハウを「5つのフェーズ」で展開
苫米地氏は、こうした社風について「防災はNTT東日本のDNAだ」と表現する。
「私が新入社員の時に驚いたのは、災害が発生すると先輩方の表情がサッと変わり、自分ができることを確認して、その場ですぐに行動に移していたことです。災害が発生した時、誰ひとり取り残さない仕組みをどうすれば実現できるのか。さまざまな災害に向き合ってきた社員の思いが、DNAとして経営層から新入社員まで根付いていると思います」(苫米地氏)
同社のDNAは、技術やアセットなどのノウハウとともに脈々と受け継がれ、現在では「災害対応の5つのフェーズ」として、自治体向けの災害DXソリューションに活用されている。災害発生の前後のみならず、「事前の備え」「情報収集・予測」「意思決定支援」「情報配信」「災害復旧の下支え」と5段階に細分化されている点が特徴的だ。
上述したリスクアセスメント調査などの「事前の備え」や、同社のICT技術やAIなどの先端技術を活用した「情報収集・予測」は、地域の防災・減災の一助となるソリューションである。
また、「意思決定支援」では、情報が錯そうする災害発生時に、被害状況の可視化や災害関連情報の一元管理、関係者間での情報共有を支援する「総合防災情報システム」を提供している。
この5つのフェーズの中で、自治体はもちろん、地域住民の心強い味方となるのが「情報配信」と「災害復旧の下支え」だ。災害対応は社会インフラの復旧だけでなく、避難所での生活支援、住宅供給など、広域での長期にわたる地道な取り組みが求められる。
「自治体向けの災害対応と同時に、地域住民が安全に避難し、いち早く自分たちの生活を取り戻すサポートも必要です。『情報配信』ではアプリやメールはもちろん、高齢者でも情報をキャッチできるソリューションや、『災害復旧の下支え』では自治体の罹災証明証発行業務の効率化を図り、被災者の生活再建の迅速化を支援するソリューション等も提供しています」(田中氏)
少子高齢化など社会的な課題も残される中、未曾有の自然災害の発生が今後ますます懸念される。苫米地氏は「災害発災時は、地域住民も自治体職員も疲弊します。技術力はもちろん、これまでの災害対応で培ったノウハウをソリューションとして活かし、防災における地域レジリエンスをより一層強化していきます」と意気込む。
事前の備えから復旧対応まで、一気通貫で災害対策を支援するNTT東日本グループへの期待は高まるばかりだ。
[PR]提供:NTT東日本