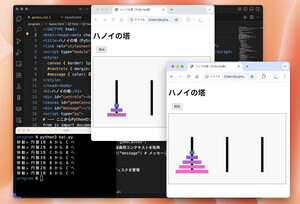多くの企業で「社員のパフォーマンスを十分に発揮できていない」という声を聞く。社員が本来求められている業務に専念し、高いレベルを発揮するためには、テクノロジーの力を借りてどのような仕組みを構築すべきか。さまざまな企業でCRM(顧客関係管理)を中心としたコンサルティングや、生成AI活用推進に携わってきた株式会社NTTデータ GenAIビジネス推進室長 奥田 良治氏に、NTTデータが構想する生成AIの未来像「SmartAgent™」の可能性を伺った。
-

株式会社NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 デジタルサクセスコンサルティング事業部長 兼 GenAIビジネス推進室長 奥田 良治氏
社員のパフォーマンス向上で、顧客に選ばれるビジネスを生み出す
社員のパフォーマンスを発揮できていない最大の要因について、奥田氏は「社員が抱える仕事の幅が広がっているにもかかわらず、その全てで高いレベルを求められるようになったことが挙げられます」と語る。
例えば製品メーカーに置き換えて考えてみよう。テクノロジーの進歩とともに「いかに消費者に製品を選んでもらうか」が重要となった今、企業は消費者に興味を持ってもらい、実際に購入に至った後もフォローしていく一連のCX(顧客体験価値)の取り組みが不可欠になった。社員は限られた労働時間内で、ビジネスの競争力強化につながるさまざまなアクションを求められているのだ。
加えて、人手不足という大きな社会課題だけでなく、コンプライアンスの遵守など、企業における社会的責任も重視されている。こうした背景を踏まえ、「社員が本来のコア業務にリソースを割くことができない労働環境が生まれている」と奥田氏は指摘する。
ただ、企業と顧客を結ぶのは製品やサービスであるとはいえ、顧客側の意思決定に影響を与えるのも、企業への共感を生むのも、結局は"人"だ。
「単にサービスを提供するのではなく、サービスを知ってもらい、実際に利用して得られる価値の創出、その後のフォローまで伴走する"人"のパフォーマンスが、良いCXを生み出す鍵となります。ビジネスの根幹を成すのは"人"なのです。一人ひとりがコア業務に集中できる環境をつくることで、顧客に選ばれるビジネスが生まれ、企業の競争力が加速するでしょう」(奥田氏)
では、社員のパフォーマンス向上を実現するために、企業はどのような仕組みを構築すればいいのか。
「まずは個々人が背負っているさまざまな業務プロセスを整理し、それぞれのタスクで役割分担することが必要です。その上で、必ずしも人が行わなくていいものはテクノロジーの力を借りることが最適です」(奥田氏)
-

株式会社NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 デジタルサクセスコンサルティング事業部長 兼 GenAIビジネス推進室長 奥田 良治氏
AIエージェントが"一人のプレイヤー"として社員をサポートする未来
CXの観点で考えた際、ビジネスに価値を生む仕掛けは3つに分けて考えられる。
まず1つ目は、徹底的な顧客理解。2つ目は、自社を選んでもらえるよう、顧客に良い体験を提供するためのデザイン設計と業務の整備。そして3つ目が、描いたデザインを着実に実行するためのサポートだ。
とくに顧客の意思決定を大きく左右するのは、"人と人とのコミュニケーション"であることから、3つ目の「着実に実行するためのサポート」について「顧客タッチポイントと社員の業務を強固に支える仕組みが重要」と奥田氏は指摘する。
このサポートを実現する上で注目すべきは、やはり「生成AI」だ。生成AIサービスを導入する企業も増えているが、社内でのFAQや要約、チャットボットなど単一業務での活用に留まっているのが現状である。実際にNTTデータが2023年度に国内で実施した生成AIプロジェクトも、ほとんどが日常業務で活用されているという。ただ、奥田氏はこの状況を「ある意味、当然」として、次のように語る。
「生成AIは大きな驚きをもたらすテクノロジーですが、業務で採用するには、信頼性に対する不安や懸念があります。ですから導入してもまずは日常業務、それもバックオフィス業務から試すというのは当然の動きといえるでしょう。しかし企業での活用が広がった今、あらゆる課題を洗い出して『生成AIは使える』という感触をつかめた企業の間で、顧客接点となるフロントオフィス業務で活用するフェーズに入り始めました」(奥田氏)
続けて「生産・物流などクリティカルな基幹業務の抜本的変革や、顧客への新たな価値創出といった部分での活用も始まっていくでしょう」と、生成AIの可能性についてこう述べる。
「生成AIは、人の意思決定とアクションを助ける"究極のコンシェルジュ"といえるでしょう。人はまず情報をインプットし、それを噛み砕くプロセスを経て、アウトプットを生み出します。この中で、生成AIの出現によって大きく変わるのがアウトプットです。これまでのデータドリブンの世界では、資料を作る、営業をかけるといった実際のアウトプットは人間が行うものでした。今後はその部分も生成AIが担うようになり、"一人のプレイヤー"へと進化していきます」(奥田氏)
この"一人のプレイヤー"として注目度が高まっているのが、「AIエージェント」だ。コア業務以外をAIエージェントが担うことで、社員のパフォーマンス向上、ひいては企業の生産性向上が期待できる。これこそが、NTTデータが描く生成AI活用の理想像だ。
-

株式会社NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 デジタルサクセスコンサルティング事業部長 兼 GenAIビジネス推進室長 奥田 良治氏
3種類のAIエージェントが業務効率化を実現する「SmartAgent™」
NTTデータは、生成AIを活用した未来像として、2024年に「SmartAgent™」というコンセプトを発表した。
SmartAgent™の世界観では、3種類のAIエージェントが登場する。 まずは、社員一人ひとりに専属し、オフィス業務を自律的に判断し行動する「パーソナルエージェント」だ。このパーソナルエージェントは、単独で社員をサポートするだけでなく、経理、人事、営業、法務といった特定の専門知識を持つ「特化エージェント」とコミュニケーションを取り、適切な意思決定をサポートしていく。その上で、これまで人手で行っていた単純かつ定型タスクを「デジタルワーカー」がこなしていくのだ。
「SmartAgent™により、圧倒的な業務効率化を実現するほか、社員がコア業務に集中できることでビジネスの質が向上する効果も期待されます。加えて、専門知識やベテランの知見、ノウハウを蓄積した生成AIのサポートによってさらに業務の質が向上します」(奥田氏)
同社ではSmartAgent™のコンセプトに基づき、業務領域ごとにサービス化を進めており、第1弾として2024年11月に営業領域を対象とする「LITRON® Sales(リトロンセールス)」の提供を開始した。今後はマーケティング、カスタマーサービス、CX/CRM、経理・人事といったバックオフィス業務の領域でもソリューションの展開を検討しているという。 これらのソリューションはクラウドベースの設計だが、オンプレミス環境で稼働する未来も見据えている。さらには、他社のAIエージェントと連携し、SmartAgent™の世界観をベースとしたエコシステム構築も目指しているとのことだ。
大手各社がNTTデータの生成AIを用いてCX向上を実現
NTTデータは、すでにマーケティング領域で生成AI/AIエージェントの活用事例をいくつも生んでいる。CXの観点でビジネスに価値を生みだす仕掛けとして先述した「顧客理解」、「体験/業務デザイン」、「着実な実行サポート」の3つのうち、「顧客理解」の側面で生成AIを用いた実践的な取り組みを行っているのが、株式会社ジャルカード(JALカード)だ。
同社ではDXの取り組みとして、デジタル技術を活用した新たなマーケティング手法を検討していた。そこで、「LITRON® Multi Agent Simulation」で提供しているAIエージェントに多種多様の会員ペルソナを設定し、エージェント同士が行う議論やその過程をヒントに会員向けマーケティング施策を実施。高級商材の販促にもかかわらず、購買率が大きく向上したという。
「体験/業務デザイン」では、 NTTデータのデザイナー集団「Tangity」が、生成AIを活用した業務デザインの支援を実施している。「サービスデザイン×生成AI×データ活用」をテーマに、マーケティング業務の刷新から顧客に向けた新たなサービスデザインの提供など、多様な支援を実施している。
3つ目の「着実な実行サポート」については、重要な顧客タッチポイントである広告を顧客一人ひとりに合わせて訴求すべく、訴求ポイントの検討やコンテンツ自体の変更を生成AIがサポートしている事例があるという。
上述の事例は総じてAIエージェントの取り組みといえるが、他にも特化エージェントの取り組みとして、熟練技術者が持つナレッジを生成AIに落とし込み、技術伝承に活用しているLIONの事例もある。
「生成AIの話をすると人間の仕事が奪われると思われがちですが、生成AIがいくら進化しても、ビジネスの中心は"人"です。人のために生成AIをどう使うか考えた際、SmartAgent™が提供する世界観は、さまざまな企業の課題解決に貢献できるでしょう」(奥田氏)
NTTデータの技術とノウハウを集合させたSmartAgent™で、ビジネスに革新が訪れる日はそう遠くないだろう。
[PR]提供:NTTデータ