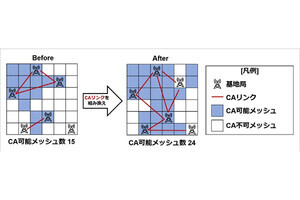ICTインフラトータルサービス企業のユニアデックスでは、これまで基幹システムのデータを主にExcelで集計していましたが、非効率、属人化、共有のしにくさといった課題を抱えていた上、意思決定においてもなかなかデータを活用できていませんでした。
そこで同社はデータに基づいた働き方への転換を目指し、データの民主化を推進したといいます。
その結果、例えば経理部門では受注モニタリング、経費の見える化、全社決算データや固定資産の見える化などを実現し、年間284時間もの業務時間の削減といった効果を得られました。
また、売上実績データの集計・レポート作成にかかる時間を10日から1日に削減したケースもあるとのことです。
このユニアデックスによる取り組みは、一体とのようにして進められたのでしょうか?
“働き方なんですよ。デジタルを活用した経営判断ができるだけではなく、社員の働き方そのものをデジタルに基づいた働き方にしようと考えました。そして社員全員がデータの民主化という形で、自分たちでデータを扱えるようにするという目標を立てました。”
高畑 浩史 | DXシステム本部 DXシステム改革推進部 部長
-

(組織名は2022年度当時のもの)
1. ビジネス背景:データの民主化のためのツールを検討
同社では2020年にDomoを導入し、一部の部署での利用を開始しました。当時、どのような理由で、導入を検討したのでしょうか。
「DX戦略推進のため、『デジタルワークスタイルの実現』と『情報とナレッジを活用した働き方』の2つのビジョンを掲げていました。特に2つ目を実現するにはデータが不可欠で、社員全員が自分でデータを扱えるようになる、データの民主化の必要がありました。」(高畑氏)
こう話すのは、同社のDX推進の責任者であるDXシステム本部 DXシステム改革推進部 部長の高畑浩史氏です。高畑氏は、老朽化した社内システムの刷新と、新しいテクノロジーの導入を担当しており、Domoの導入は後者の取り組みとなります。
「基幹システムを導入してから20年以上が経過していました。データ整備ができておらず、データの集計に時間がかかるので、データを見ながらビジネスの判断をすることはできませんでした。経営層も現場もデータで意思決定できるようになれば、効率化、迅速化につながるという期待がありました。」(高畑氏)
2. 導入前の課題:ファイル管理の限界と、予実管理の代替
Domoの導入前は、基幹システムのデータをExcelにエクスポートして、手作業で集計していたそうです。
「Excelのスキルに長けた社員が集計ファイルを作成していましたが、非常に手間と時間がかかっていました。その上、ファイルのマクロ設定などが属人化し、その社員が異動や退職をすると、管理ができないという課題がありました。」(高畑氏)
「またExcelの場合、共有がしにくいことも課題でした。ファイルサーバーで共有しても、場所がわからなければアクセスできませんし、ユーザーによってはアクセス権限が無くて見られないという問題もありました。」(高畑氏)
一部の部署で、データ分析のツールを試験的に導入したこともありましたが、全社展開となるようなツールはなかったそうです。
「Office 365についている無償版Power BIを全社員使えるのですが、限定的で個人ユースな製品なので、Domoみたいに作ったものを全社で共有して見ることはなく、課題感を感じていました。」
3.なぜDomo?:使いやすさを最重視して複数製品を比較検証
Domoを導入し、1年目はサービス企画部で試験的に利用しました。2年目からは全社展開を見据え、営業部も導入し利用者数が10倍になります。そこで全社展開に最適なものという観点で再度製品選定を行うことになり、高畑氏が中心になって複数製品を検証しました。
「データの民主化を目指すには、一部の社員に限らず全社員が手軽に操作を習得できることが必須要件でした。そのため、使いやすさを重視して比較検討しました。それに加えて、Domoはグラフなどビジュアル表現が充実しており、表現力が豊かな点を評価しました。あとはサポート体制が十分で安心感があり、コスト面も納得でした。1年目に導入したサービス企画部での評価や効果も、社内承認を得る上で重要な後押しとなりました。」(高畑氏)
「導入後、特にデータ加工関連機能の使いやすさに満足しています。利用を拡大する中で、私達がサポートをしなくても、現場の社員が自分たちでグラフを作成しています。」(高畑氏)
なお、エンジニア職ではなく、データベースの知識がないという営業企画本部 営業企画部 営業企画推進室 グループマネージャ 福田浩志氏は、DomoのETLツール(Magic ETL、データの取得・処理・変換を行う)の使いやすさを評価しています。
「最初にETLの講習を受けただけで、自分で使いこなせるようになりました。ビジネス部門のユーザーでも、自分でデータの取得、接続や統合を簡単に行えるのは、全社での利用を拡大するにあたって重要な要件です。」(福田氏)
<選定のポイント>
・使いやすさ
・表現力
・サポート
・価格
4.定着化:DX推進部主導から、各部門から代表者を募ったタスクフォースへ
1、2年目はDX推進部が推進役としてユーザー部門と要件を取りまとめ、ダッシュボードを作成していきました。
2年目に古くなった基幹システム(旧SFA)を株式会社セールスフォース・ジャパンのSales Cloudへ置き換えましたが、Sales Cloudでは基幹システムにあった管理会計(売上・粗利の予実管理)機能を実現できなかったため、これをDomoで実現しました。Domoへの置き換えは、高畑氏と共にDomo推進を行っている、エクセレントサービス開発本部 DXシステム改革推進部 改革プロジェクト企画推進室主任 中村圭佑氏がDomoのコンサルタントによる支援の元で行いました。
「元のシステムが古いので、誰も知らなかった機能が後からわかり、あれもできないか、これもできないかとギリギリになって相談がたくさん来てしまいました。しかしDomoに様々な表現方法が用意されていたので、期限までに対応することができました。」(中村氏)
さらに旧システムには過去案件の検索機能があり、こちらもDomoで実装することになりました。実装を担当した 営業企画本部 営業企画部 カスタマーサクセス推進室 濱口ありさ氏は次のように話します。
「契約番号、得意先、部門などから過去の案件を検索したり、フィルターをかけたりできる機能で、営業企画部内で要件整理から実装までを行いました。Domo上に擬似的な業務アプリを構築できました。」(濱口氏)
「Domoへの置き換えは成功し、営業は必ずDomoを見ています。Domoの浸透度が高まりました。」(高畑氏)
3年目はさらに全社へ展開するため、エンジニア企画推進本部、経理部、経営企画部など9部署から約30名のメンバーを募ってタスクフォースを立ち上げました。
「データの民主化を全社レベルに引き上げるために、1年間各部署の代表者に徹底的にDomoを使ってもらい、翌年からは各部署でのDomoの推進を担ってもらいます。自分たちの業務に直結するデータを使ってダッシュボードを構築し、業務改善に活かしてもらっています。」(高畑氏)
タスクフォースは、月に1回メンバーが集まって、各チームの進捗報告や部門横断の協力依頼を行いました。次のようなテーマでダッシュボードの構築を行いました。
<タスクフォースで作成したダッシュボード例>
5.導入後の効果:業務工数の最大90%削減効果
1年目のサービス企画部での導入では、売上実績のデータ集計、レポート作成にかかる期間が10日から1日になり、 90%の削減効果がありました。2年目の営業の予実管理では、営業部員がほぼ毎日確認して、進捗管理を行っています。
3年目のタスクフォースでは、それぞれの部門で成果があがっていますが、特に注目すべきは、最多の11名がタスクフォースに参加している経理部です。
「経理部では、受注モニタリング、経費見える化、全社決算データや固定資産の見える化など、一人1業務以上のDomo化ができました。結果、年間284時間の業務時間削減の効果がありました。」(高畑氏)
中村氏は次のように話します。
「活動に加わったメンバーは前向きにデータ活用に取り組んでくれました。メンバーがデータ活用ができるという自信を持てたことが大きな成果です。」(中村氏)
「営業部門の商品別売上の数字と、エンジニア部門のスキルデータをかけあわせて、どんなスキルが売上に貢献するのか分析する動きもあります。これまでは、データが各部門に分散しているため、その部門でしか利用できませんでしたが、Domoがあることで部門を越えたデータ活用が実現できそうです。相乗効果が出るのはもう少し先ですが、最初の一歩は踏み出せました。」(中村氏)
導入推進者、ユーザーとして感じたDomoの良いところはどこでしょうか。
「ノーコードでデータ加工が簡単にできることです。加えて、アクセス権設定などセキュリティ機能などを含め、Domoですべて完結するAll in Oneである点が便利です。」(高畑氏)
「SaaSなので、サーバ構築などのインフラ系の管理が不要な点です。DX推進チームのデータ利活用チームは5名で、他にも業務がある中で、基盤構築のリソースが不要なのは助かりました。」(中村氏)
「過去実績の検索機能を作ったとき、修正点があれば対応する方針で、簡単な要件定義で実装を始めました。走りながら完成させられたことがよかったです。」(福田氏)
※記載内容は2023年2月に行った取材内容に基づくものです。
[PR]提供:ドーモ