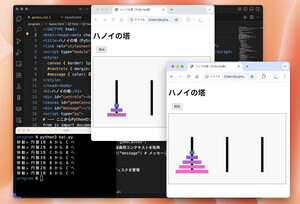国内外で価格・品質競争が激化するリテール業界。データドリブン経営により自社のコアコンピタンスを見出し差別化を図ることが、競争優位性を高めるための1つの糸口となりえる。そのためには、社内外に存在する多種多様かつ大量のデータから意思決定に活用できるデータを収集し整備する必要がある。
2月10日に開催されたリテールガイド×TECH+共催セミナー「リテールDXソリューションカンファレンス2022」で、Denodo Technologies 営業本部 営業部長 篠崎義治氏は、データドリブンな意思決定に役立つデータ仮想化ソリューションとリテール業界におけるビジネス変革事例について紹介した。
従来型データ統合プラットフォームの限界
昨今のITの進化により、リテール業界では、店舗や倉庫、ECサイトなどから発生する各種データを収集することが容易になってきている。リテールテックも普及するなか、多くのリテール企業は、既存サービスの改善や新規ビジネス・サービスへのデータ活用を進めるなど、データドリブン経営へシフトしつつある。
では、いかにして、多種多様かつ膨大なデータを有効活用し、スピーティーな意思決定につなげていけばよいだろうか。そこで必要性が高まっているのが、さまざまなロケーションで発生したデータを収集・蓄積し、加工・整理・統合するデータプラットフォームである。
篠崎氏は、「DXやデータ戦略を推進するにあたっては、消費者の生活様式の変化への対応、Time to Marketへのスピード感が求められる」と、データプラットフォームに求められる要件のハードルが高くなってきていることを説明する。しかしながら、従来の方法ではアーキテクチャ上、解決できない3つの課題があるという。
1つめは、リアルタイム性。製品サイクルの短縮化や顧客の多様化に対応するためには、迅速な意思決定が求められる。しかしながら、エンタープライズのデータ統合環境はこれまで、バッチ処理を中心に構築されてきたため、リアルタイムのデータを活用しづらいことが課題となっている。
2つめの課題は、コストである。さまざまなロケーションからデータが取得できるようになることで、データの多様性も増していく。しかしながら、各データは別々のシステムで管理されることによってサイロ化してしまう。結果として、データを活用できる状態に加工するためのコストが発生してしまう。システムの移行・改修を行う場合にもコストが掛かる。
そして、3つめの課題がガバナンスだ。データドリブンな意思決定の質を高めるためには、誰もが同じデータを元に判断できるSingle Source of Truthの状態を保持することが重要となる。また、統一された品質、セキュリティを担保し、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスを実現していく必要もある。しかしながら、データ自身がサイロ化されてしまっていると、データに一貫性を持たせることは困難である。
3つの課題を解決するデータ仮想化プラットフォーム
こうした3つの課題を解決するアーキテクチャとして、「論理データウェアハウス」が2017年にガートナーより提唱された。論理データウェアハウスとは、業務アプリケーションとデータソースとのあいだに位置するセマンティックレイヤであり、ここを通ることで業務アプリケーションは任意のデータソースを利用できるようになる。物理的なデータのコピーや再配置は必要とせず、直接データソースにつなぐことで、リアルタイムのデータにアクセスすることが可能となる。そして、この論理データウェアハウスを実現するソリューションが、データ仮想化プラットフォームである。
篠崎氏は、Denodoのデータ仮想化プラットフォームについて「データを抽象化し、物理的なデータをもとに加工・修正を行い、データ活用層からの要望に対してリアルタイムのデータを提供できるテクノロジー。データへのアクセスを中間層に一元化することで、ガバナンスやセキュリティを統一的に管理できる。データの民主化として注目されるデータカタログ、APIによるデータ配信の機能も有する」と説明する。
また、既存システムの改修はほぼ必要ないため、PoCから本番稼働まで、短期間で導入できることも特徴。PoCに1カ月、本番導入に3カ月、合計4カ月で導入を完了した事例もあるという。
データ仮想化のユースケース
ここからは、リテール業界におけるDenodoのデータ仮想化のユースケースを紹介したい。
世界最大の小売業者である米Walmartは、IT資産のコスト削減を目的に、自社システムに関してオンプレミスからクラウドネイティブへの移行を検討した。しかし、パブリッククラウドへの移行にあたっては、いくつかの課題があった。
ECで発注した商品を実店舗で受け取るというサービスにおいて、顧客が発注をしてから来店するまでのあいだにデータ更新が遅延することで、顧客が店舗にたどり着いた時点で商品の準備ができていない状況が発生していた。このため、商品キャンセルによる売上減やカスタマーエクスペリエンスの悪化がビジネス上の課題となっていた。また、技術的には、パブリッククラウドへの移行に時間的・金銭的コストが掛かることが大きな課題であった。
こうした課題をクリアするために、Walmartは、Denodoのデータ仮想化プラットフォームを導入。ECと実店舗との連携を改善し、カスタマーエクスペリエンスの向上を実現したほか、物理データマートから論理データマートに変換したことで、約4000万ドルのITコスト削減につなげたという。
グローバルで約5000の倉庫を展開する米Prologisは、グローバルでの協業やECの発展による物流量の増大への対応を検討。サプライチェーンやERPシステムの膨大なデータを活用することで、グローバルでの効率的な倉庫運用およびロジスティクスの実現を目指した。
データプラットフォームの構築は、3つのステップで進めていったという。まずは、Denodoを利用し、データ統合・可視化を実施。その過程で、クラウド上のデータストアを導入し、オンプレミス・クラウド含め論理的なデータウェアハウスを構築した。
続いて、データを抽象化し、ビルディングブロックとなるセマンティックレイヤを構成し、データをすぐに使える状態にすることに取り組んだ。これにより、データドリブンな意思決定のスピード向上を実現した。
3つめのステップでは、データサイエンティストがRやPythonなどを利用し将来的な需要予測などプロアクティブな分析を行える状態を構築した。
「Denodoのデータ仮想化プラットフォームは、リアルタイム性や対応力を求めるのに最適な基盤。下図のキーワードのなかに、何か1つでも引っかかるものがあれば、データ仮想化をご検討いただきたい」(篠崎氏)
[PR]提供:Denodo Technologies