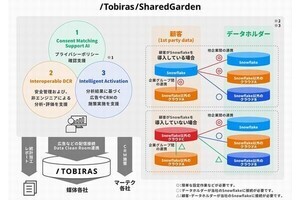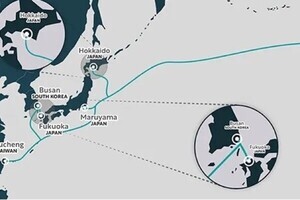安全運転をすれば、保険料がお得になる――今年3月にリリースされた運転特性連動型自動車保険「GOOD DRIVE」は、スマートフォンの専用アプリによって計測された運転特性データをAIが分析し、ドライバーの事故リスクを算出。事故リスクが低いドライバーに対して保険料の最大30%がキャッシュバックされるというサービスだ。
ソニー、ソニー損害保険(以下、ソニー損保)、およびソニーネットワークコミュニケーションズの3社が会社の枠を超えて共同で開発を進めた同サービスは、どのようにして生まれたのだろうか。ソニー R&Dセンター Tokyo Laboratory 07 古川亮介氏と、ソニー損保 マーケティング部門 ダイレクトマーケティング部 部長 石井英介氏に、GOOD DRIVEの詳細や開発秘話について聞いた。
根底にあるのは「事故を起こさないように」という思想
従来の自動車保険は、保険金の受け取りや各種ロードサービスなど、事故やトラブルの事後対応を中心に考えられていた。しかし、ドライバーにとっても保険会社にとっても、事故は起きないに越したことはない。GOOD DRIVEの根本には、事故が起きたときのサービスだけではなく、事故そのものを起こさないための仕組み作りが重要であるという思想がある。
GOOD DRIVEは、スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、保険加入者に配布される専用デバイスを車内のアクセサリーソケットに差し込むだけで利用できる。エンジンをオンにすると、ビーコンが作動し、アプリが自動で起動。アクセル、ブレーキ、ハンドル、走行中のスマートフォン操作の4点が運転特性データとして計測/評価される。例えば、急ブレーキ、急発進、急加速、急ハンドル、走行中のスマートフォン操作はマイナス評価となるといった具合だ。「普段通り運転すれば、意識せずとも勝手に運転特性データが計測されるよう工夫しています」と石井氏は自信を見せる。
事故リスクはS~Dランクの5段階で評価され、ランクに応じて保険料のキャッシュバック率が決まる。また、運転診断結果は降車後すぐにアプリに反映され、走行経路や運転時間、車の操作状況を振り返ることができることに加え、事故リスクを低減させるためのアドバイスが個々の運転特性に応じて提示されるなど、安全運転に向けてドライバーの行動変容につながる仕掛けが随所に組み込まれている。
「3つのアセット」を駆使した開発
競合の保険会社のサービスのなかにはドライブレコーダーを活用したものもあるが、運用やハードウェア自体にコストが掛かってしまう。安価でかつ高精度に運転データを記録できないかと考えたときに、古川氏が着目したのがスマートフォンの活用だった。
「専用デバイスにセンサーを搭載するほうが、開発は圧倒的に簡単です。しかし、保険サービスとして広く普及させるにはデバイスにコストを掛けられません。一方、スマートフォンには、加速度センサー、GPS、ジャイロセンサーが搭載されています。これらをうまく活用すれば運転記録を取ることができると考えました。
ただし、実用化するにあたって問題となるのは信号の精度やノイズです。GPSは都会ではビルの影響などを受けて精度が全く出ませんし、加速度センサーやジャイロセンサーは人が少し触るだけで反応してしまいます。このような問題を鑑みて、走行場所やスマホの置き場所などに依存することなく、車の挙動のみの信号をいかに抽出するかというところが技術的な挑戦でした」(古川氏)
また、車の挙動を把握できたとして、それが実際に事故のリスクにつながっているかどうかという判断も必要となる。そこで、ソニー損保とソニーがタッグを組んだ。ソニー損保が契約者8000人以上の1年間の運転挙動データと実際の事故データを取得し、そこにソニーのビッグデータ解析技術を用いることで、事故リスクの定量化を実現したのだ。
「日本でこうした保険サービスが普及していない理由は、開発の観点から考えると、3つのアセットが必要であることが挙げられます。1つは、自動車メーカーが持つセンサー技術や車両計測技術。2つ目は、保険会社が持っている事故実績の情報。そしてもう1つは、IT企業が強みを持つ、AIやクラウドを用いて多様なデータを処理して分析する技術です。しかし、一般的にこれらの3つのアセットを合わせようとすると、それぞれの社風が違いすぎるために協業がうまくいかないことがあります。
一方で、私たちソニーグループはこれら全てのアセットを保有していると言えます。チームメンバー同士で惜しみなく情報をやりとりすることで、スムーズな開発につながりました」(古川氏)