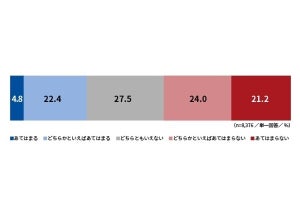セルフブランディングのすすめ
自分自身のブランド価値を高めることを「セルフブランディング」と呼びます。これは、皆さんの仕事においても価値があることですし、キャリア開発においても目標を定めやすくなります。筆者がこの連載をしていることについて、知人が「セルフブランディングしているね」と言ってくれることもあります。筆者の例に漏れず、少なくともセルフブランディングはやっておいてまったく損はないです。ただし、自分のブランドをどう作るかを意識し、普段からスキルアップすることも必要になります。
そもそも、ブランドとはどういう意味があるのでしょうか?ブランドの語源については諸説あるようですが、古代ケルト語の牛の焼き印である「brandor」からきていると言われています。これは、燃えるというBurnと同じ由来です。多くの牛の中から、特定の牛を識別するということです。つまり、違いを作るということです。
ビジネスの世界において、これは差別化と言われます。差別化とは、同じカテゴリーに分類される他のものと比較して、"大きな違い"を作り出すことです。ブランドはその差別化の下で、一貫したコミュニケーションをすることが大事です。ビジネスのブランドにおいては、社員からの発信、PR、マーケティングなどがコミュニケーションチャネルです。
このように複数のコミュニケーションチャネルが存在するので、一貫性が重要であり、メッセージやブランドイメージの統一を行います。そのメッセージのもとになるのが、差別化なのです。
差別化を生み出す「コア要素」と「拡張要素」
ビジネスにおいても個人においても、差別化は大変厄介な課題です。筆者は長年マーケティングを担当しており、営業などの社員から「もっと宣伝を増やしてブランド認知を上げてほしい」というリクエストを頻繁に受けます。
ここには、2つの問題があります。まず、そもそも差別化がないと宣伝しても仕方ないがないということ。そして、今時ブランドは宣伝では作れないということです。後者は後で詳しく説明します。ブランドに限らず、マーケティングプロモーションや営業活動において課題を詳細に分析すると、結局は事業戦略や製品戦略で差別化が作れていないというルートコーズ(根本原因)にたどり着く場合が本当に多いです。すべての起点が差別化と言っても過言ではありません。
個人においても同じで、上流である自分自身の差別化をどう作るかが、セルフブランディングの出発点となります。では、どのように差別化を作るのでしょうか?自然に出来上がるのでしょうか?
実は、差別化は計画的に作り上げる必要があります。さまざまな経験を通して、ある程度の差別化は形成できます。しかし、そもそも差別化は上述の「brandor」のように、他とは違う知識やスキルのセットを持つ必要があるということです。そのためには、計画が必要です。
ビジネスにおいての差別化は、コア要素と拡張要素の二つの要素があります。コア要素とは絶対的な強みの部分で、他の人が認知する差別化のポイントです。Apple製品のカッコいいデザインや革新性とか、トヨタ自動車の品質などです。拡張要素は、AmazonにおけるIT基盤や、Googleがやっている10%の時間をコア業務以外で使う取り組みなど、外からは見えづらい影の強みです。
個人の場合もコア要素と拡張要素で、どのように差別化を作り上げるかを考察します。コア要素は周りの誰もが「○○さんはこういうことが優れている」と言えるところです。拡張要素は、他人には見えない、外にはあまり見せない強みです。じわっと醸し出されていくような強みとでも言うべきでしょうか。
筆者の場合は、コア要素はITのマーケティングおよびオペレーションの経験やスキル・知識で、拡張要素はITエンジニアやギタリストとしての創造性だと思っています。自分の差別化を考えるために、下のような図を書いたことがあります。皆さんもぜひ図にしてみるといいですよ。
差別化は伝言ゲームで広がる
差別化は、今持っている強みに加えて、将来のキャリアを開発する上でどのように強みを作っていくかです。将来の強みにしたいことこそ、これから習得する知識やスキルの羅針盤になるのです。そうです、このように差別化は作り上げるものなのです。
差別化が構成できたら、それを文字で表現してみましょう。差別化はコミュニケーションされるのですが、人々の記憶には「あの人はこうだから」と言語化されて残ります。これは人から人へ伝播していきますので、ある意味、伝言ゲームです。だから、分かりやすい伝言を作り上げるのです。
そのためには、筆者は次の3つを作ると良いと思います。皆さんを売り込む1行で表現するヘッドライン、端的に表現する2行のリード文、そして、5行程度で表現するステートメントです。新聞の記事を思い出すと、これらで構成されていることが分かります。これは、書籍『朝日新聞記者がMITのMBAで仕上げた戦略的ビジネス文章術』(中央経済社 著者:野上英文)から学びました。
ヘッドラインはキャッチコピーであり、それを作るためにまずは多くの候補をリストアップしておきます。その中から、後で作るリード文とステートメントに最適なヘッドラインを選択します。そこには自分の差別化が発揮できる分野が入るようにしてください。また、印象に残るインパクトが必要です。他のメールではなく、そのヘッドラインが入ったメールを読みたくなるようイメージです。
リード文は2行で、「強みのAと強みのB」、または、「強みのAとその理由B(なぜならば)」のどちらかの型で表現します。そして、ブランドステートメントとして5行で表現します。なぜ5行かというと、上記の書籍を参考にしているのですが、5行の文章を口頭で読むと約30秒を要するからです。人の記憶はこれくらいが限度だそうです。いわゆるエレベータピッチというやつです。
最後に、ビジネスにおいて宣伝ではブランドが作れないことと、セルフブランディングへの関係を述べます。ビジネスのブランドの歴史をみると、最初は近所の評判から、そしてマスメディアでの宣伝、それからインターネットでの対話によってブランドが作られてきました。
現在は情報や商品が溢れる中、ソーシャルメディアなどで勝手にブランドが作られる時代になっています。また、宣伝の効果はもともと認知があればそれなりに得られますが、認知がない企業の宣伝は簡単に無視されます。読者の皆さんも興味がない宣伝は見ないですよね?社外でのポジティブな会話を誘発することが大事なのです。
同じようにセルフブランディングにおいても、個人のブランドは自分以外のところで勝手に作られてしまいます。他人同士の会話や噂話で作られるということです。その中で私たちができることは、社内外の影響力のある人との良い関係性を作りあげていくことではないでしょうか。内にこもっていては、個人のブランドは作れないのです。