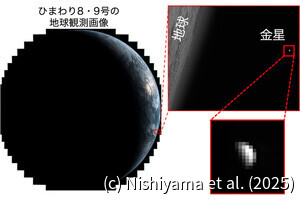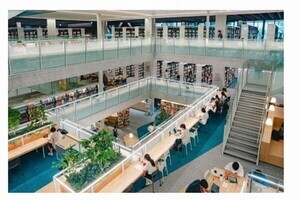前回までは、新しい開発の立ち上げに焦点を当ててお伝えしました。今回は異なる視点から、非開発部署メンバーの「ITへの情報感度強化」の重要性をお伝えしたいと思います。
なぜ、非開発部署メンバーにITへの情報感度が必要なのか?
「ITリテラシー」と言うと、情報基礎リテラシーやネットワークリテラシーなどの技術的なスキルや知識を思い浮かべる方も多いでしょう。確かに、それらは重要であり、関連する資格の取得支援を開発組織以外にも広げていくことには価値があります。しかし、今回取り上げたいのは非開発部署メンバーの「ITへの情報感度強化」です。これは、新しい技術トレンドやツールの出現、変化するユーザーニーズに迅速に対応するための感度を高めることを意味します。
ではなぜ、開発組織の立ち上げにおいて、非開発部署メンバーの情報感度を強化する必要があるのでしょうか。「立ち上げたばかりの開発組織が他部署からどう見えるのか」というところから考えてみましょう。
開発組織というのは、その性質上、他の部署から見るとミステリアスな存在となりがちです。私の所属していた組織でも、以下のようなイメージの変遷を経験しました。
この変遷は、他部署とのコミュニケーションや共同プロジェクトを通じて、徐々に理解と信頼が深まる過程を示したものでもあります。具体的には以下のような状態です。
初期段階
そもそも何をしていて、どういったことを依頼・相談ができるのか分からない状態のため、組織間コミュニケーションが一切生じません。解決方法としては、積極的に開発組織が働きかけ、プロダクト開発だけではなく、社内業務効率化につながるような提案活動を行っていくことが挙げられます。
中期段階
初期段階を上手く乗り切ると、他部署にとって、開発組織は「何でも解決してくれる魔法使い」のような存在になり、小さなことから大きなことまでさまざまな要望が開発組織へ来るようになります。これはある意味では初期段階を乗り切ったと言うことでもありますが、対応に忙殺されるといった弊害が生じる場合もあるため、この段階は最もいち早く抜けるべきだと考えています。
発展段階
基本的なITトラブルは各部署で解決でき、エンジニアは専門的な業務に専念できる状態です。この段階まで来れば、開発組織立ち上げとしてはうまくいったと評価して良いでしょう。同時に全社員の「ITへの情報感度」が高まっており、自己解決能力に長けた社員が自然と養成されていく組織へと変化していきます。
開発組織が企業の成長を支える存在に成長していくために
これらの段階を適切にステップアップさせていくには、エンジニア側の歩み寄りだけではなく、その他組織からの理解も非常に重要です。少し前までは、専門家であるエンジニアが歩み寄りを行うことで円滑なコミュニケーションをとることが可能でした。しかし最近は非開発部署が業務上、各種のSaaSソリューションを扱うことも増え、ITに対する相応の理解が必要とされています。そのため、エンジニア側の一方的な歩み寄りのみでは解決が難しいケースも多くなりました。今の情報社会においては、エンジニア以外の情報感度を強化することも開発組織を成功させるための必須要件であると言えます。
こうした変化の中で、企業全体の競争力を高めていくためには、エンジニアだけでなく、全ての部署がITの知識を持つことが鍵となります。基本的なITトラブルの解決をエンジニアに頼るのではなく、各部署がそれを自力で解決する力を持つことは、企業全体の効率を大きく向上させるのです。
具体的に当社で発生した課題をご紹介します。中期段階においては、以下のような質問まで開発組織に来るようになりました。
このような質問や依頼が開発組織に届くと言うことは、組織が変わりつつあるという意味では評価できます。しかしこの状態が長期に渡り続いてしまうと、エンジニアが本来行うべきサービス開発を阻害する要因になりかねません。だからこそ、全社レベルでの「ITへの情報感度強化」が非常に重要になるのです。
中期段階の課題を解決するために実践した施策
こうした問題を解決するためには、全社員のITリテラシーを向上させる取り組みが必要です。我々が実践したのは、全社員を対象にした「Google検索講座」と「ローコード・ノーコードツールの講座」の実施です。Google検索講座では、効率的な情報収集の方法や信頼性のある情報源の見分け方などを指導しました。ローコード・ノーコードツールの講座では、プログラミング知識がない人でも業務の自動化や効率化ができるツールの使い方を解説しました。
一連の取り組みの結果、基本的なIT関連の課題を自部署で解決できるようになり、エンジニアはより専門的な業務に専念できるようになりました。
このように、全社員を対象とした実践的なITリテラシーの向上も、エンジニア組織の立ち上げ期には効果的です。近年であれば、ChatGPTの活用方法といった内容も検討する余地があるかと思います。
組織の立ち上げ期にはつい、その組織だけに目が行きがちですが、その他の組織の状態も把握しながら、共に変化・成長させていくことが新組織組成の重要な立ち回りになるでしょう。