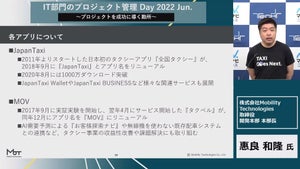タクシーアプリの「GO」と、クリエイターの創作プラットフォーム「note」。異なるジャンルのサービスではあるが実は共通している点がある。
GOはタクシー乗務員と乗客、noteはクリエイターとユーザー。どちらも“2者をつなぐサービス”なのだ。サービスを利用する目的や、背景にある課題などが異なるユーザーに対して同一のサービスを展開する場合、UX/UI設計は一筋縄ではいかない。一方を優先すると、もう一方に不利益が生じる可能性もあるからだ。両社はそうした課題をいかに解決し、サービスを提供しているのか。
今回はGO 執行役員 プロダクトマネジメント本部 本部長の黒澤隆由氏と、note 執行役員 CDO(チーフデザインオフィサー)の宇野雄氏による対談を実施。それぞれの視点から、UX/UIの重要性について語り合った。
「あのアプリ」が誕生したワケ
--まずは、それぞれのサービスについて紹介をお願いします。
黒澤さん(以下、敬称略):GOはスマートフォンのアプリからタクシーが呼べるサービスです。元々、「JapanTaxi」と「MOV」という別々のタクシーアプリとして提供されていたサービスを2020年9月に統合し、GOという名称に変更しました。
日本のタクシーの特徴としては、安心で安全性に優れていることが挙げられますが、当社のようなタクシーアプリが登場する以前のタクシーサービスは、お客さまにとってもタクシー乗務員にとっても非効率なものでした。お客さまがタクシーに乗りたいときは、電話で住所を説明して家まで来てもらうか、道で手を挙げたり乗り場に並んだりして空車のタクシーに乗るしかなかったし、タクシー乗務員はどこにお客さまがいるかわからず、勘と経験を頼りに働くしかありませんでした。
タクシーを必要とするお客さまがいるのに、まったく違う場所でお客さまを探してタクシーが走っている。そのような非効率な状況をDX(デジタルトランスフォーメーション)により効率化していきました。
GO
執行役員 プロダクトマネジメント本部 本部長黒澤隆由さん
2008年より楽天にてプロダクト開発に従事。2018年よりディー・エヌ・エーにてタクシーアプリのプロダクト責任者を務め、2020年4月にGOへプロダクトマネジメント本部 本部長として転籍。2021年10月に執行役員に就任。日本CPO協会理事。
宇野さん(以下、敬称略):私もGOを日頃から利用しています。リリースされたときはびっくりしました。まさにこんなサービスが欲しかったと思ったんです。今までタクシーに乗るときはオフィスのビルの車寄せに行くか、電話をするしかないものだと思っていましたから。GOが誕生したことで、自分が気づいていなかったペインが解消され、それまで当たり前だったことがもっと便利になる瞬間を体験できました。
黒澤:ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。noteさんはどのようなビジョンや、課題感から生まれたのですか?
宇野:当社の場合は題解決型というよりも、「世の中がこうなったらいいな」というミッション・ビジョンをもとに生まれたサービスです。
当社は「だれもが創作をはじめて、続けられる世界」を企業のミッションに掲げており、そんな世界を実現できるサービスづくりを目指しています。当社は元々、ピースオブケイクという社名で、「cakes」というコンテンツ配信サイトを運営していました。cakesもnote同様にコンテンツを発信できる場ではあったのですが、発信者は一部の選ばれた方に限定されており、誰もが発信できる場ではなかったのです。
そんなcakesに対して、より一般の方に門戸を開き、プロでなくても報酬を得られるクリエイターエコノミーの世界を達成するために生まれたのがnoteです。
note
執行役員 CDO(チーフデザインオフィサー)宇野雄さん
制作会社やソーシャルゲーム会社勤務の後、ヤフーへ入社。Yahoo!ニュースやYahoo!検索などのデザイン部長を歴任し、その後クックパッドでVP of Design/デザイン戦略本部長を務める。2022年2月よりnoteのCDOに就任。
noteが目指すのは「すべての人がクリエイターになる世界」
--UX/UIというキーワードが出たので、ここからはそれぞれのサービスがユーザーに提供しようとしている価値と、それをUX/UIでどう実現しているのかについてお聞きします。
宇野:noteは先ほど申し上げたように、「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」ことを目指しています。ただ、「続ける」と一口に言ってもさまざまな要素が求められます。その中でも、クリエイターが創作活動で一定の収益を得られるようにすることは特に重要と考えており、その点を意識したプラットフォーム設計を行っています。イメージとしてはnote全体が「街」であり、クリエイターが生み出すコンテンツは街にあるお店、そしてユーザーはお店で買い物をするお客さまと考えてください。
従来のブログはあくまでも一つひとつが独立した存在ですが、noteはクリエイターとユーザーが住む街であり経済圏なのです。だからこそ当社はnoteという街で皆さんが豊かに“生活”できるようにさまざまな施策を行います。例えば、クリエイターのnoteにユーザーが立ち寄りやすい導線設計だったり、クリエイターが報酬を得られやすくする仕組みだったりします。
noteが目指しているのは、「ユーザーもまたクリエイターになっていく世界」です。すべての人がクリエイターになってほしいし、それによって生き方が自由になると考えており、当社としてはそうしたクリエイターエコノミーを形成していきたいです。
黒澤:noteが登場したばかりの頃は、「ブログみたいなもの」と思っていました。でも、弊社でnoteを利用してオウンドメディアを開始してから、「ブログとは似て非なるもの」という印象を抱くようになりました。
宇野:そうですね、サービスとしてブログに近い部分もあると思います。ただ、ブログが情報を伝えるためのプラットフォームなのに対して、noteはクリエイターが集まって発信し続けるためのプラットフォームです。似ている部分はあっても、目的が明確に異なるのです。そこが機能面やUX/UIに表れているのだと思います。
当社では、法人もまたクリエイターであると考えているんです。「法人格」と言うように、企業も一種の人格を持っており、自治体や学校などさまざまな組織がクリエイターとして創作物を生み出しうる存在なのではないかと思っています。
黒澤:弊社のオウンドメディアの主役は弊社の社員で、一人ひとりの顔が見えるコンテンツを発信しています。そういう意味では、弊社ならではの個性が出ている創作物と言えますね。
--noteは「クリエイター」だけでなく、創作物を読んだり、視聴したりする「ユーザー」にも体験を提供されていますが、どのような考え方で運営されているのでしょうか。
宇野:noteでは圧倒的にクリエイターの応援に力を入れています。なぜなら、クリエイターが集まるところにユーザーが集まり、ユーザーが次のクリエイターになるからです。クリエイターがいないとコンテンツが生まれませんから、ユーザーは集まりません。クリエイターがコンテンツを生み出しやすいUX/UIを作ることが何よりも重要なのです。これを社内では「グロースモデル」と呼んでいます。
ただ、一方をえこひいきしているわけではありません。私たちはクリエイターの味方になることで、ユーザーの皆さんにも「ぜひ作る側に回ってみませんか」と呼びかけているのです。そのためのUX/UI設計としては、例えば、必ずクリエイターの名前を記事のトップに表示しています。そうすることで、創作物や情報だけでなく、クリエイター自身に目を向けてもらいやすくなると考えます。
また、記事にはハートマークの「スキ」ボタンを用意しています。これは単に記事をブックマークする目的ではなく、記事を読んだユーザーがクリエイターにポジティブな感情を伝えるための仕掛けです。ボタンを押したユーザーの名前とユーザーからのメッセージはクリエイター側に通知されます。
どんな人が、どんな感想を持ってくれたかが伝わるサービス設計にすることで、クリエイターの創作意欲を刺激し、ユーザーには創作することに興味を持ってもらえるのではないかと考えています。
GOが大事にするタクシー乗務員と乗客の「人肌感」
--noteがクリエイターとユーザーにサービスを提供しているのと同様、GOも「タクシー乗務員」と「乗客」の両方にサービスを提供しています。それぞれにどのような体験を提供しているのでしょうか。
黒澤:大前提として、GOは単にタクシーを呼ぶためのアプリではなく、「タクシー乗務員とタクシーに乗りたいお客さまのマッチングサービス」だと考えています。両者はGOを通してマッチングした後、数分後には実際に顔を合わせて、タクシーという空間内で一定の時間を一緒に過ごすわけです。そうであるならば、その時間はお互い快適に過ごしたいですよね。そのために、例えば、GOにはタクシーを待っている間もアプリを通して簡単なコミュニケーションがとれる機能などがあります。
なぜ、このような機能を提供しているかというと、お互いの状況を簡潔に連絡し合えることで、現地で「ストレスなく」「スムーズに」出会えることをサポートできると考えるからです。また、事前に少しでもコミュニケーションをすることで、「迎えにきてくれているタクシー乗務員さん」と「待ってくれているお客さま」といったように、人が介在していることを自然と意識できるので、思いやりを持った行動に繋がり、トラブルも起きにくくなると考えています。
一般的には、タクシーを呼んだ直後に「流しのタクシー」が通りかかると、お客さまはそちらに乗ってしまいます。反対に、タクシー乗務員の都合で配車をキャンセルしてしまうこともあります。配車やキャンセルに人を介していないので、「キャンセルしたら迷惑かな?」と思う間もなく、悪気なくキャンセルをしてしまいがちです。
でも、GOの場合、こうしたキャンセルは極めて少ないです。ユーザーインタビューなどを行うと、「GOでタクシー乗務員さんが向かってくれているからもう少し待とう」と流しのタクシーに乗らないでいてくれるお客さまや、「お待ちいただいているお客さまにご迷惑をおかけするから」とキャンセルを控えてくれるタクシー乗務員の声を多く目にします。 ほかにも、到着時間にはお客さまが約束の場所に出てきてくれていたり、タクシー乗務員も少しでも早く到着できるように努力したりと、両者が相互に気づかう場面がGOには非常に多いです。これはプロダクト設計において、機能性からUIデザインの細部まで、「人と人との関わり」や「人肌感」を意識した体験設計をしているからこそだと考えています。
「マッチング」と「創作のサポート」にAIを活用
宇野:性質の異なるステークホルダーに対して機能を提供していると、どちらの体験を優先すべきか迷うことはありませんか?
黒澤:ありますね。ただ、それでも私たちはタクシー乗務員とお客さまの両方を大事にしたいと考えています。何か課題が発生したとき、タクシー乗務員とお客さまのどちらか一方に「負の体験」を押し付けてしまえば簡単に解決できることが多いのですが、両者をトレードオフの関係にすることなく解決できる方法が無いか知恵を絞ることで、本当に良いプロダクトが生まれるのだと考えています。
例えば、タクシー事業者が電話で受けている従来の「タクシーの予約」がそうです。お客さまにとってタクシーを事前に予約できることはとても便利ですが、タクシー乗務員は予約を受けてしまうと、予約時間の前後に仕事を入れにくいので、売上効率が下がってしまいます。このケースでは、あえてタクシー乗務員に「負の体験」を寄せて、お客さまにとっての利便性を守っています。
そこで、GOでは「AI予約」という機能を提供しています。同機能ではAIによる高度な需給シミュレーションを行い、指定された日時と場所に配車できるだけの予約枠をお客さまに開放し、乗務員には無駄な待ち時間が発生することなく、最適なタイミングでお迎えにあがれるように配車を行っています。
宇野:良いプロダクトと機能実装って、正解がない問いですよね。noteでは誰もが創作を始めやすいように、エディター(編集機能)などをできるだけシンプルにしているのですが、機能の追加にあたっては、何度も議論をして慎重に検討を重ねています。
例えば、複雑な数式を表記しやすくするフォーマットや、縦書きレイアウトなどの機能を追加すれば、サービスとして確実に便利になると思います。でも、そうやって機能を増やして「高度なプロダクト」に成長するとUX/UIが複雑化して、これから創作を始める方にとってハードルが高くなってしまいます。
黒澤:そうだったのですね。最近、追加した機能は何かありますか?
宇野:最近では「AIアシスタント(β)」という機能を追加しました。これはAIを活用して創作活動をサポートする機能です。一方で、「AIがコンテンツを作ってしまうなら、もうクリエイターはいらないんじゃないか?」と思われてしまう可能性もあります。
私たちがやりたいのは、あくまでもAIでクリエイターの創作活動をサポートすることであって、創作活動自体を奪うことではありません。そこを正しく伝えるために何度も議論し、新機能の名称もAIクリエイターではなく「AIアシスタント」にしました。
--タクシー乗務員と乗客、クリエイターとユーザー、性質の異なる2者を繋ぐサービスであるという点は共通していても、実現したいことは違うものですね。GOとnote、それぞれのサービスを今後どのように成長させていきたいですか?
黒澤:みなさんが「どこかへ行きたい」と思ったときに、真っ先に想起していただける移動ポータルとして、それぞれの状況やニーズに応じて最適な移動手段をお届けできるオンデマンド移動プラットフォームでありたいと考えています。それは今後、ほかのお客さまとの相乗りの車両であったり、自動運転車両であったり、さまざまな可能性が考えられます。
GOは現在、44の都道府県でご利用いただけますが、今後は地方の過疎地なども含めて、いわゆる「交通空白地帯」と呼ばれるようなエリアにも、さまざまなビジネスアイディアとプロダクト開発力を駆使して広く展開して、多くの人々の生活の足として無くてはならない交通インフラになっていきたいですね。GOのある街がどんどん増えて、みんなが移動の不安なく暮らせる社会を実現していきたいです。
宇野:noteの基本スタンスは変わらないと思います。より多くのクリエイターを生み出し、創作活動をサポートしていきます。一方で、伝えたい人にしっかりと作品を届けられているかというと、まだ不足している部分もあると考えています。そこは技術を用いて、リコメンド機能などで対応していきたいですね。
黒澤さんが先ほど「人肌感」とおっしゃいましたが、私はnoteというサービスにも人格があると思っています。過去に当社では、サービスにおける「noteらしさ」を定義するため、「noteさん」という人格を考えるワークショップを実施しました。具体的には、服装はシンプルで、でも少し遊び心の入ったファッションで、言葉遣いは硬くなり過ぎず、でも丁寧で人に寄り添ってくれるような人格です。そうした空気感を持ち、クリエイターを応援できるサービスであり続けたいですね。