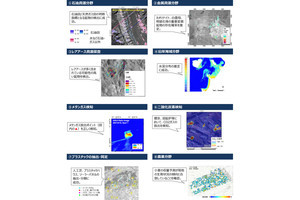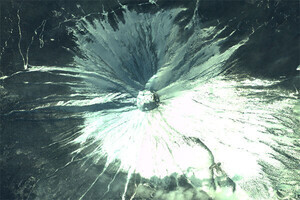Tellusは11月13日、衛星データ活用のための法人向けクラウド型ワークスペース「Tellus Pro」を提供開始。データの取得・処理・共有をクラウド基盤でシームレスに実現し、複数衛星の軌道を一括検索したり、新規撮像を依頼したりといったこともできるという。
衛星データ業務をひとつのクラウド基盤に集約し、企業内での効率的なデータ活用を可能にするもので、同社では国内初のサービスと謳っている。
利用できる衛星は、2025年11月時点では「GRUS」(900km2)と「ASNARO-1」(1シーン)の2種類で、2026年度以降は「Synspective」と「QPS研究所」の観測衛星を順次追加予定。アカウント数や利用できるストレージ容量、機能の異なる2プラン「スタンダード」「プレミアム」を用意しており、最低利用期間は3カ月。基本的には同一法人での利用を想定しているが、複数社での共同利用も相談可能としている。
Tellus Proの中核を構成するのが、ストレージサービス「Drive」、衛星データ販売サービス「SatHub」、データ処理・分析をクラウド上で行えるコンテナ基盤「Pipelines」の3サービス。日本国内で完結するクラウド基盤を用いており、衛星データの処理・解析・保管を国内環境で安心して利用できるという。
各サービスの概要は以下の通り。なお、DriveやSatHubなど一部機能のみの利用も可能で、個別に相談を受け付ける。
Drive(ドライブ)
大規模な衛星データをはじめ、前処理・解析済みデータ、新規撮像(タスキング)データを安全に格納・管理・共有できるストレージサービス。多様なデータを一元的に集約し、衛星データ活用の基盤として機能する。
SatHub(サットハブ)
複数衛星の新規撮像(タスキング)を照会・注文し、Tellus Pro上で直接購入できる衛星データ販売サービス。各衛星の軌道を一括で見られるシステムで、新規撮影依頼を事業者ごとに個別対応することなく取得できるとしている。
Pipelines(パイプライン)
衛星データの前処理や分析をクラウド上で実行できるコンテナ基盤。Tellus Proで購入したデータに加え、保有する外部データも取り込み、高性能GPU環境で柔軟な処理フローを構築・実行できる。GPU不要の場合に、CPUで代替するプランも用意する。
近年、衛星打ち上げ数の増加に伴い、政府機関・研究機関・民間企業などが保有する衛星データが急速に拡大している。しかし、十分に活用されずに保管されるデータも増え、提供事業者の運用・管理コストを圧迫する要因になっている。
一方、衛星データの活用事業者にとっては、衛星データの新規撮影依頼を事業者ごとに個別対応する必要があることや、データ共有の難しさ、データ取得と処理プロセスの分断などの課題があるとされる。
Tellus Proはこうした課題に対し、データの提供事業者と活用事業者の双方が抱える管理・運用負荷や活用上の課題を、ひとつのクラウド基盤で解決することを目的として開発。今後は、Tellusやサードパーティが開発したAIツールやアルゴリズムを実行できる機能や、大規模ストレージに蓄積されたバルクデータセットへアクセスできる機能、各衛星のアーカイブデータとの接続の追加など、順次拡充予定とのこと。
サービス詳細
スタンダード
- アカウント数:最大30ユーザー
- Drive:500GiB
- バケット数:1
- SatHubタスキング:1シーン/月
- Pipelines H100:30時間/月
- セキュリティ設定:2要素認証のみ
- アカウント管理:ID・パス認証のみ
プレミアム
- アカウント数:最大10,000ユーザー
- Drive:5TiB
- バケット数:10
- SatHubタスキング:3シーン/月
- Pipelines H100:100時間/月
- セキュリティ設定:ログ参照
- アカウント管理:SSO認証(Okta連携)