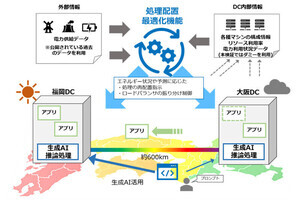NTTとNTT東日本は7月11日、野生鳥獣監視などカメラ映像を画像認識する遠隔監視ユースケースにおいて、IOWN APN(All-Photonics Network)と低負荷データ収集通信制御技術により、通信性能を確保したまま多数の高解像度カメラ映像データを低負荷に収集できることを実証したと発表した。
実証の背景
近年は担い手不足や高齢化の対策として、ネットワーク経由でカメラ画像をサーバへ送信し、AIで画像認識を行う遠隔監視の導入が進んでいる。例として、熊や猪などの動物を検知する野生鳥獣監視、交通量の測定や駐車場の出入りを管理する車両監視、不審者の検知や進入禁止区域への立ち入りを監視する侵入検知などがある。
しかし、ネットワークやサーバ負荷の制約によりデータ収集に利用するカメラの台数を増やしたり解像度を上げたりできないため、局所的な監視に限定される課題がある。野生鳥獣監視では罠の状況確認のような点での監視にとどまっており、動物の種類や数を継続的に把握する面的な監視は難しい。
山林への定期的な見回り調査のような負担の大きな現場作業を削減するために、多数の高解像度カメラを配備し画像を分析する、人手を介さない広域な監視の実現が求められている。
カメラを配備する際の制約のうち、ネットワークの観点についてはIOWN APNや6Gといった次世代通信技術の発展によって解決の見込みがある。一方、サーバ負荷の観点については大容量データの受信処理に要する負荷への対策方法が確立されておらず、多数の大容量データを低負荷に収集する技術が求められている。
実証実験の概要
実証実験では、NTT中央研修センタ(東京都 調布市)とeXeField Akiba(東京都 千代田区)をIOWN APNで接続し、NTT中央研修センタに設置した複数の4Kカメラで撮影した画像をeXeField Akibaに設置したサーバに送信して、AIによる画像認識を行う実験システムを構築した。
なお、画像認識のユースケースとして、野生鳥獣監視、車両監視、侵入検知の3つを再現した。今回構築したシステムでは、一つのビルやエリアに多数設置したカメラが回線を共用し、遠隔地のサーバへ画像データを送信する構成を採用している。
多数のカメラが設置された環境を模擬するため、実際のカメラを接続した実端末に加え、仮想的にカメラを構成する仮想端末も併用。実験では、画像データを収集した際のサーバ負荷、スループット、および画像認識の精度を測定した。
技術のポイント
多数の大容量データ受信時に処理負荷が増大する要因は、OS(Operating System)からアプリケーションへのメモリコピー処理にある。この課題を解決する方法として、あるサーバのメモリから別のサーバのメモリに直接データを書き込む技術であるRDMA(Remote Direct Memory Access)の適用が考えられる。
RDMAは高速かつ低負荷という特徴を持つが、通信路のロスレス性を前提に動作するため、ネットワーク内部でパケットロスを抑止する仕組みを構築する必要がある。従来RDMAが利用されてきたデータセンタネットワークでは、近傍に設置されたすべての通信機器でフロー制御機能を連携動作させることによりパケットロスを抑止してきた。
しかし、今回のデータ収集が対象とする広域ネットワークは、さまざまな通信機器が広範囲に多数配備されていることから同様の機能が困難であり、パケットロスの抑止が行えずRDMAをそのまま利用すると通信性能が低下する。
そこで、多数の端末から発生するRDMA通信の開始と終了のタイミングをコントローラで制御することで、パケットロスを抑止して通信性能を確保する低負荷データ収集通信制御技術を確立した。
この通信制御技術では、収集すべきデータの発生を契機として端末が通信の開始をコントローラに要求し、コントローラが各端末の要求に基づきRDMA通信が衝突しないよう通信の開始・終了タイミングを制御しパケットロスを抑止する。
また、RDMAの高速性と収集データごとに異なる遅延要件の多様性といった特徴をふまえ、速やかな分析が必要なデータの場合のみ通信開始・終了を即時行い、分析に時間をかけてもよいデータの場合はシステムのスループットを高められるよう一定量データを集約して通信開始・終了を行う。タイミング制御のオーバーヘッドを極力抑えて通信性能をより高められるという。
高速かつ低負荷である一方で通信路のロスレス性が求められるRDMAに対して、データ収集に適した通信制御を行うことにより、通信性能を確保しながら多数の大容量データを低負荷に収集できる。
実証の成果
従来、RDMAでデータを収集する場合は、サーバ負荷の低減が可能であるものの、多数の端末で回線を共用することによるパケットロスが発生し通信性能が低下する課題があった。一方、今回の通信制御技術でデータを収集する場合は、RDMA利用時のパケットロスを抑止できるためスループットを約5倍向上できることが確認されたという。
また、TCP(Transmission Control Protocol)でデータを収集する場合と比べて同程度の通信性能を確保しながら、受信処理に要するサーバ負荷を最大1000分の1まで低減できることが確認された。
今回の通信制御技術の適用による効果として、カメラの収容台数の増加や高解像度化が期待できる。TCPの場合はサーバ負荷の制約などにより収容台数が制限されるが、この技術を用いる場合のサーバ負荷は無視できるほど小さく、利用可能なネットワーク容量の上限まで収容台数を増やせる。カメラ収容台数を約10倍まで拡張できると見込めるという。
また、多数のカメラでの収容台数増加による広範囲の監視実現に加えて、4Kのような高解像度カメラ画像を使った画像認識によって、動物が小さい場合やカメラからの距離が遠く被写体が小さく映る場合でも高い精度で検出可能となる。
今回の実験システムでは、小さく映る被写体の検出において、フルHDで撮影した場合の検出率が約60%であるのに対し4Kで撮影した場合は約80%であり、20%程度の精度向上が確認された。