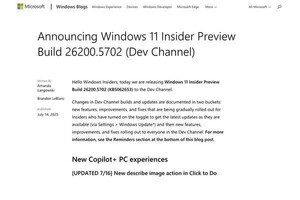今、世界のAI(人工知能)を巡る動きを見た時に「エヌビディア1強」の状況がどうなるかは引き続き焦点です。グーグルやマイクロソフトに加え、アマゾンも自前の半導体開発を進めていますが、それはエヌビディアからの供給を前提としたAIの発展に限界が見えてきているからです。
ただ、エヌビディアもパートナーと連携したクラウドサービスを提供し、さらに自前のクラウドサービスの計画を発表しました。クラウドベンダーも自前の半導体を開発していますが、生成AIでの活用はまだ限定的です。これが双方とも逆転すると市場が広がりますが、道半ばです。
また、生成AIの性能向上も間近に迫っています。AI開発を手掛けるオープンAIによる「チャットGPT」は次のバージョンで、それ以前の100倍の性能を持つようになると言われています。
この100倍の性能には、推論精度の向上や効率性の改善など様々な解釈がありますが、端的に言えば収益性が大幅に改善する可能性を意味します。
これまでは投資フェーズで、未来を見せることが大事だということで、オープンAI自身も相当な投資を続けてきましたが、今は回収に向けて着実に手を打ち始めています。
今後、利用者である我々の側は2分されると見ています。生成AIを使わないワーカーは、今日で言えばパソコンを使わないワーカーと同義と言えるほど急速に普及していくでしょう。
そして、従来の100倍の性能を持った生成AIは、おそらく日本円で1人当たり数万円で提供される見通しです。では、自分で数万円払って高度な仕事をしたいというホワイトカラーは、日本にどれだけいるでしょうか。
しかし、月20ドルでできる範囲のことをやろうという仕事をしていると、知的集約労働の中で役割を果たせなくなるかもしれません。
例えば当社で言えば、社員には生産性高く仕事をして欲しいので、全社員に数万円で生成AIを利用してもらおうと考えています。
その意味で道具を供給する経営側が決断できるかどうか。そして月20ドル程度でどれだけ生産性を上げられるか、月数万円の道具で月10万円の付加価値を上げられるかという形で社員側の意識も変わらざるを得ないでしょう。
経営、社員ともに進化が問われている局面で、この1、2年でキャッチアップできた会社は、その先も活躍できるでしょうが、月数万円、あるいは月20ドルも社員に支払えない会社は衰退せざるを得ません。ここで今後10年の勝敗が決まる夜明け前、分水嶺と言うことができます。
当社は独自の生成AI(人工知能)プラットフォ―ムサービス『GaiXer』(ガイザー)を提供していますが、我々の社内で生成AIを徹底的に使い、先導できる立場でありたいと思っています。
当社自身、AIを使ってユーザーに代わってタスクを自律的に実行するソフトウェアプログラム「AIエージェント」に取り組んでいます。
今後はAIエージェントが別のAIエージェントを動かして、人間が望む仕事を行う「自律型エージェント」が実装されていきます。
ただ、人間の顧客はあくまでも人間です。顧客に対して価値を生むために、AIにどんな指示をするかが人間に問われる役割になります。