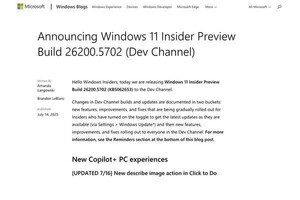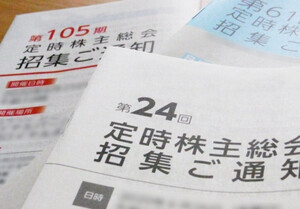内は深く、外は広い
『内は深く、外は広い』─。禅文化を国の内外で広めた鈴木大拙(1870―1966)の言葉とされる。
明治の日本の興隆期に青春時代を送り、大正、そして昭和の激動期を生き抜いた仏教学者であり、啓蒙思想家であった鈴木大拙。その鈴木大拙のこの言葉の持つ意味は大きく、腹の底に響いてくる。
自分自身の心の内を探っていくと深化していくし、外の世界を観ると、果てしもなく広がりがあるということ。
いわば、内省・謙虚さと開拓魂を併せ持つ言葉と言ってもいい。『少年よ、大志を抱け』(Boys , be ambitious!)の言葉で知られるクラーク博士。そのクラーク博士の言葉に触発された人物は多い。明治期の啓蒙家、内村鑑三、新渡戸稲造もそうだ。
内村、新渡戸は共にクリスチャンであり、札幌農学校(現北海道大学)の卒業生であり、ウィリアム・S・クラーク博士(1826―1886)の薫陶を受けた人物。
志と使命感がいかに若者の心を奮い立たせ、世の中(社会)に貢献する生き方を実践させていくか。
人を育てることの意味
内村は、『代表的日本人』を著し、日蓮上人、二宮尊徳、中江藤樹、上杉鷹山、西郷隆盛らの名を挙げた。新渡戸稲造は、『武士道』を著し、本人は国際連盟の事務次長を務めたりして、国際紛争の問題解決に奔走。また東京女子大学や拓殖大学で学長を務め、教育・人材育成にも打ち込んだ。
鈴木大拙や内村鑑三、新渡戸稲造らに共通するのは『知性主義』であろう。明治維新(1868)から157年、先の大戦終了(1945)から80年が経つ今、世界中で〝反知性主義〟の嵐が吹き荒れる。
国の針路はもとより、企業経営のあり方、そして個人の生き方・働き方はどうあるべきか。今、わたしたちは分岐点に立たされているのだと思う。しかも、現実の世界は荒れぎみで、混迷を深めている。
混迷下での新しい国づくり
世界がブロック経済化する懸念がある中で、日本の『国のカタチ』をどう創りあげていくか─。
米トランプ政権の高関税政策や移民締め出し案などの諸政策が世界中を混乱に陥れている。
先の大戦終了から80年、今、世界中が混沌とした状況の中で、各国とも何とか生き抜こうと、もがき苦しんでいる。
米国が自国第一主義(米国ファースト)を振りかざして、なりふり構わなくなっているのも、自分たちに余裕が無くなったからだ。
移民取り締まりで、ロサンゼルスで暴動が発生。トランプ政権はカリフォルニア州兵を大統領権限で出動させ、デモ鎮圧に当たる挙に出た。海兵隊の出動も含めて、デモ鎮圧に軍隊が出動するというのは、やはり異常な事態である。
戦後80年、民主主義国の元祖として、自由貿易、法の支配をスローガンに新世界秩序づくりを進めてきた米国の国力低下が世界の混乱を招く一大要因になっている。
このような状況下で、日本は新しい『国のカタチ』をどう創っていくかという命題である。
世界が荒れる中で……
ロシアによるウクライナ侵攻はまだ続く。イスラエルはイスラム過激派・ハマスとの闘いでガザ地区への攻撃を続行中。子どもを含む民間人死傷者は増えるばかりだ。
中東がまたキナ臭くなっている。イランの核開発をめぐり、米国との協議も難航。イランとイスラエルとの対立が再燃し、イスラエルがイランの核開発施設を攻撃すれば、イランはイスラエルの主要都市・テルアビブを攻撃。両国の応酬は続く。
西太平洋や台湾近海においても中国の空母や艦載機が活動を活発化させ、日本の自衛隊の哨戒機に〝異常接近〟して威圧行動を取るなど、緊張感も高まる。
世界の随処で一触即発のリスクが高まる。安全保障が経済と密接に絡む時代だと痛切に感じる。
そういう中、日本を強い国にするにはどういう視点や問題意識が必要かということで、本号は三菱総合研究所理事長の小宮山宏さん(1944年=昭和19年生まれ、第28代東京大学総長)に登場していただき、〝混迷期の中での新しい国のカタチ〟づくりを語ってもらった。
御手洗冨士夫さんの提言
日本の立ち位置をどう取っていくか─。
「アメリカは世界に影響を持つ国。影響を持っていることは確かなんですね。大輸入国であるし、大輸出国でもある。資源もいっぱいあるし、人口も大きいしね。わたしが居た頃のアメリカは世界のリーダーであるという意識があったわけです。いろいろな国の面倒を見たり、世界を治めるという意識があった」と語るのはキヤノン会長兼社長・御手洗冨士夫さん(1935年=昭和10年9生まれ)。
御手洗さんはキヤノンを日本を代表する企業に育てあげ、グローバル企業に持ってきた経営者。30歳の時、米国勤務を命じられ、米国キヤノン社長を務めて帰国(1989)するまで23年間米国で働いてきた。
その御手洗さんも、トランプ政権下の米国について、「今はアメリカだけを良くすればいいと。それが自分の責任だという風に変わってきた」という現状認識を示しながら、日本の使命と役割について、次のように語る。
「日本の立ち位置はですね、マクロ的に言うと、やはり日米間の関係をよくしていくと。日米両国は同盟国ですから、この関係をガッチリ固めて、日米間の政治経済関係を固めた上で、中国と仲良くする。ここがポイントです」
日本はつなぎ役を
御手洗さんが続ける。
「別の言い方をすると、やはり日本は日本として、国の力を強化しておいて、軍事力も含めて経済力も含めて強化しておいて、アメリカと中国の間を取り持つという仲介役ですね。この二大大国の調整をしていくのが日本の役割だと。この2つの国(米国と中国)が戦争を始めたら、世界はもうたまったものじゃないですからね」
米国と中国の対立は当分続く。そういう状況下、「アメリカと中国の大きな2つの国をつなぎ、アジアにおいて平和を保つために、この2つの国の間に立って、平和を保つ役割を担うのが日本の使命だと思います」。
御手洗さんは経団連(日本経済団体連合会)の会長を2006年から2010年までの4年間務めた。当時は日本政治の混迷期で、経団連会長時に首相は自由民主党の小泉純一郎氏、安倍晋三氏、福田康夫氏、麻生太郎氏、そして鳩山由紀夫氏(当時民主党)と5人も変わった。
政治の混迷は経済の停滞をも引き起こす。日本が〝世界のつなぎ役〟としての使命を担うためにも、『新しい国のカタチ』を構築し、国力を高めていかないといけない。
日本の志と使命感が問われている。