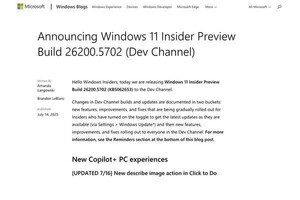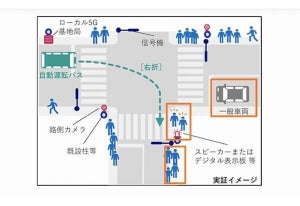NECは6月10日、同社の経営の方向性を発信することを目的に、グループインタビューを田町本社で実施した。インタビューでは、取締役 代表執行役社長 兼 CEOの森田隆之氏が説明を行った。
立ち上げから1年、「BluStellar」の現在地
--BluStellarは立ち上げから1年が経ちました。トランスフォーメーションを進めるためには、人材教育が大事ということでコンサル人材含め育成する中で、競合他社のDXブランドと比べた強みは何でしょうか
森田氏:マインドセットの変革だと思っています。
日本はBtoBマーケティングが育たないと言われており、過去(新野社長の時代)、次々とマーケティングがスタートしていくのを横で見ていましたが、しっくりきていませんでした。なぜなら、当時のNECのマーケティングはBtoCのマーケティングに近かったため、ブランドを知り、そこに対して好意を持ってもらうといったものが多かったからです。
NECは10年以上前に、通信事業者にソフトウェアを提供しているNetcrackerを買収しており、毎年Netcracker2.0、3.0、4.0という形で新しいITシステムをCIOをはじめとする経営幹部に提案していました。
それを見ているうちに、BtoBのマーケティングとは、お客さまの業務の流れを理解して、その中でどのような価値を出していくかということに対して新たな切り口で提案し、それによってどういう価値が生まれるかを訴求していくしていくことなのだと分かりました。
これを構成しているテクノロジーは二の次であり、むしろお客さま(企業や政府など)がそれによってどういう価値が実現できるかが一番の訴求ポイントなのです。その訴求ポイントを実現するために必要なのが技術と機能であるという気付きがありました。
これがBtoBのマーケティング、プロダクトマーケティングという言葉を使うと誤解する人がいるかもしれませんが、それがBluStellarの根底に流れています。
あくまでモノを売るのではなく、お客さまの売上の増加、コストダウン、利益の上昇につながる、そういうところに対するロジックを積み重ねてソリューションや商材を売っていく、ということです。
BtoBにおけるマーケティングはそうあるべきであり、これをどこまで徹底できるかが勝負だと思っています。
--その中で他社と比較した際の「Blustellar」の強みは何でしょうか
森田氏:NECは、エンジニアリングだけではなく、サイエンスを持っています。例えば、顔認証技術やAIをスクラッチから作る技術、広帯域の光通信伝送の技術など、科学技術の領域で独自技術を持っています。
また、社会インフラ領域の防衛・宇宙について、極めてミッションクリティカル性の高い、ある意味で失敗が許されない領域でのシステム構築や運用に携わっています。
これをBlustellarに織り込んでいければ、圧倒的な差別化ができると考えています。
グループを整理し人心を一つに
--森田社長は以前、現行中計の達成よりも次期中計を定めていく年にすると話しました。それを踏まえて今年度は何をするのか、また、やり遂げなければならないことを教えてください
森田氏:2025中期経営計画において計数目標の一部を2024年度に達成できた。2021年度当初はこんな目標本当にできるのかとも言われましたが、今後、大きなサプライズがなければ、現在は中計達成が射程圏内に入ってきています。
そうした時に、次期中計を何年間にするかは決まっていないが、(仮に5年間とすると)その中で自分たちがどこに向かっていくのかについて、組織、特に経営チームの中で方向性についての共通認識を持つことの重要性が大きいと思います。
もう1つは、NECグループの力を集めていく準備を進めることです。組織を整理し、人心を一つにしていくことが重要と考えています。
例えば、NECネッツエスアイのTOBを行い、100%子会社化しましたが、さらにNECネクサソリューションズ、そしてNECの消防防災事業、中堅・中小企業向け事業の部門を統合して中間持株会社を7月1日に発足し、一定の期間を通じて最適化して仕掛けを作ります。
この青写真について、現在のNECネッツエスアイの牛島会長兼CEOなどのチームが中心になってもらいながら作っていくことになりますが、少なくとも今年度中にはこれでいけそうだという状態にもっていかなければならないと考えています。
他にも、アビームコンサルティングとの連携もこの数年急ピッチで進めてきましたが、これをさらに拡大するためにはどういうことをやっていくか。さらには、この夏に買収したヨーロッパ3社の本社機能を日本からヨーロッパに移します。
これらを通じてグループガバナンスの新しい形をグローバルレベルで実証していくことが求められており、このような次の成長を作るための土台の検証をこの1年でやっていきたいと思います。
数字については、どうしたら営業利益率で15%が次の中計でしっかり足付けられるようになるのかをこの1年で考えていきます。
市場の成長以上に伸びていかなければなりませんが、多くのことを同時に考えるのは難しいでしょう。売上はM&Aを行えばすぐに上がるが、これを目標に置くのは適切ではないと考えています。
売上先行だと先行投資型になり、リスク許容型になりますが、これはNECが昔間違った道でもあるので、利益の額や規模をどれだけ拡大させるかを中心に考えていきたいと思います。
キャリア採用に対しても平等に門戸を開く
--人材採用について。中途採用を強化していると思うが、なぜ力を入れているのか。また、どのような変化があったか、新しい人が入ってきたことで見えてきた課題はあるか?
森田氏:新卒採用は日本特有の採用形態だと思います。これはこれで良いところはあるが、中心とするのは正しくないと思っています。
キャリア採用の人に対しても平等に門戸を開き、また、一旦NECを離れた人に対しても採用をオープンにしていく。こうしたことは人材難の時代にあっては、非常に重要だと考えています。受容性が高い組織であると、広く認識されることはとても大事だと思います。
2つ目に、キャリア採用に加えて、女性を中心としたダイバーシティ推進、海外の買収会社の経営幹部を含めた組織の活性化の効果はすごく大きいと思います。新たな気づきや新たな学びもありました。
これをどれだけ取り入れられる組織かどうかで、NECの強さが決まってくると思います。その意味では非常にいい試金石になっています。一方で、中途採用の人は時間軸が新卒採用の人と違う点もあり、組織の期待値や自分のキャリアに対する考え方も人によって大きく変わることもあります。
キャリア採用初期の方たちが入社して5~6年経った中で、継続的に優秀なタレントの人に意義を感じています。入社してからさらに新たなキャリアを開いてもらうことができるかが非常に大きなチャレンジだと思っています。
中途採用の人もそうですし、NECにしてもそうです。例えば良い例が、DGDFのBU長をやっている久保は、もともとM&Aの部門のヘッドとして入りましたが、2年ほど前から事業部門の部門長に就き、今度はヨーロッパで部門を率いる。このようなキャリアを開けることになると、すごく良い形になっていると思います。