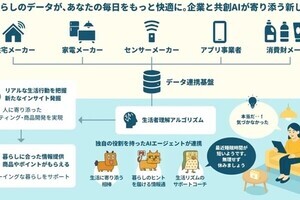トランプ関税を見直すための日米交渉が4月から2回実施されている。4月9日に発動された相互関税24%は、暫定的に7月9日まで10%に引き下げられている。自動車、鉄鋼・アルミ以外の対米輸出品目にかかった追加関税の10%をなるべく0%まで引き下げるための交渉を、赤澤亮正経済担当大臣とベッセント財務長官の間で進めている。このベッセント氏は、トランプ政権の中では穏健派である。これまで強硬策が見直されるときには政権内で存在感を示してきた。だから、交渉相手としては与しやすいと思われる人物だ。トランプ大統領自身を納得させるのは難しくても、ベッセント氏ならばハードルは低いと思わせる。これが対米交渉の戦術だとしても、そう悪くはない。
では、日米交渉をどう進めていけばよいのか。1つ言えるのは、カードを安易に切らないことだ。2月7日に石破首相は米国で初めてトランプ大統領に会った。自動車の対米進出、LNG輸入などの「お土産」を持って行ったが、相互関税24%をかけようとする態度はそのお土産を無視するかの対応である。日本側が用意したカードは、相手が確実に譲歩しない限り切るべきではない。約束の履行を確認して、こちらの履行を進めるくらいの用意周到さがあった方がよい。トランプ大統領はまるでブラックホールのように米国側の利益を飲み込んでいく。いくらでも利益を誘導しようというのがトランプ流のディールの正体だ。
トランプ大統領の脅しも話半分に聞いた方がよい。相手を過剰反応させて、より多くの譲歩を導こうとするからだ。円安誘導の批判は、いくら「日本側の理解を求める」とつぶやいても伝わりにくい。日本が狙われないためには、交渉してもなかなか恩恵を引き出せない国だと感じさせる方が都合がよい。
また、トランプ大統領の弱点を見透かすと、それは「時間」ではないかと思える。すでに大統領は高齢だ。任期は2029年1月まで。米国の関心は、2028年夏頃には次の大統領に移っているだろうから、求心力を保てるのはその位までだろう。トランプ大統領の年齢は2028年夏には81歳になっている。丁度、昨年11月の大統領選挙を戦ったバイデン前大統領と同じ年齢だ。トランプ大統領の体力、求心力は任期後半に落ちるとみられる。2026年11月には中間選挙があって、そこで勝てなければ、議会を法案が通らなくなる。
時間が勝負だとすると、長い交渉をやりたくないというのがトランプ大統領の本音だろう。日本の非関税障壁を個々に議論すると、必ず長期戦になる。なぜ、非関税障壁を持ち出すかと言えば、それは日本から短期的な利益を引き出したいからだろう。そうした思惑をあらかじめ見透かして交渉をしないと、また次の言いがかりをつけるに違いない。そこは、日本は強かに長期戦を戦う覚悟が必要である。