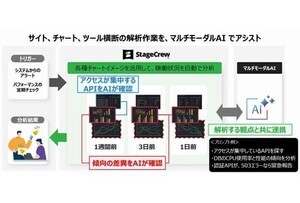オブザーバビリティ製品を提供するDynatraceは5月21日、都内で事業戦略発表会を開催した。発表会では米国本社からCEOのリック・マコーネル氏が来日し、説明を行った。
統合的なオブザーバビリティを提供するDynatrace
同社は2005年にAPM(アプリケーションパフォーマンス管理)製品を提供するベンダーとして設立し、2019年ニューヨーク証券取引市場に上場、2021年に日本市場での活動を本格化。現在の本社は米国ボストン、グローバルに62拠点を展開し、社員数は4700人を抱え、顧客数は欧米の大企業を中心に4000社以上に達する。
同社製品は「OneAgent」と呼ぶ単一のエージェントでインフラ、アプリケーションに関連する情報を収集し、ノースキーマかつノーインデックスのデータレイクハウス「Grail」で収集したデータを格納して高速で分析を行う。また「PurePath」は、ブラウザからコードからデータベースまでアプリケーションの全階層のコードを変更することなく自動的に処理の流れを捕捉する。
全階層にわたるすべてのアプリケーションコンポーネント間の依存関係を理解し、インタラクティブマップによる可視化やAI分析を行う際は「Smartscape」を利用。さらに、AIによる分析結果などをトリガーとして人手を介さない自動化処理をワークフローで実行することが可能な「AutomationEngine」を備える。
冒頭、マコーネル氏は「オブザーバビリティ、アプリケーションセキュリティ市場は650億ドルの規模がある。昨今、ITの複雑化は従来以上に進んでおり、クラウドへの移行に伴いデータも増加していることから、管理していくことが難しい状況になっている。データやソフトウェアが複雑に絡み合う状況においては、自動の管理プロセスに取り組む必要がある」と指摘。
そのうえで同氏は「当社はAIの主導の製品を提供しており、企業のデータを分析して、どのように企業の活動に結びつけるかというプロセスを自動で行うことが可能だ。たとえば、インシデントを検知して削減したり、MTTR(Mean Time To Repair)を短縮したりといった目的で導入されている。しかし、技術的な分析や解決に使うだけでなく、ビジネスの文脈でも活用されている。単なるソフトウェアの管理のみならず、ビジネス全体の最適化という観点で利用が広がっている状況」と胸を張る。
3つのAIを活用し、プラットフォームに搭載
マコーネル氏によると、Dynatraceで実現できることとして、あらゆるトランザクションの分析、AIによる自動化、迅速なイノベーションの3つを挙げている。そして、同社製品の肝と言えるのが独自のAI「Davis」を搭載したプラットフォームで4つのレベルにおいて、統合的なオブザーバビリティを提供している点にあるという。
具体的にはAPMやインフラ、アプリケーションセキュリティ、RUM(リアルユーザー監視)などの「モジュールレベル」、ログ、トレース、メトリクスの「データレベル」、経営層、IT運用者、プラットフォームエンジニアいといった「ペルソナレベル」、経営層レベルのビジネス分析を行う「技術・ビジネスレベル」となる。
Davisについてマコーネル氏は「10年以上提供しており、因果AIと予測AI、生成AIの3種類のAIを活用している。これにより、根本原因分析やインシデントの予測、自然言語によるユーザーサポートを可能にしている。当社は統合データ、AI駆動型インサイト、自動レスポンスを強みとしている」と説明した。
一方、日本市場に関して同氏は「経済規模を考えると非常に大きな市場機会が存在している。また、大企業になればなるほどシステムが非常にユニークであり、当社はそうした企業に対してサービスを提供することに慣れている。さらに、昨今では日本国内においてオブザーバビリティが経営アジェンダ化していることから訴求していく」と述べていた。
日本市場における戦略と展望
続いて、日本法人のDynatrace 代表執行役社長の徳永信二氏が日本市場の戦略について、説明を行った。まず、徳永氏は「日本市場でのチャンスは大きい。ポテンシャルを感じており、期待感は非常に強く、国内の主要パートナーも着々と増えつつある」と力を込めた。
ただ、同氏は同時に日本市場の問題点も挙げている。それは、アプリケーションやインフラの監視が従来の手法にとどまっていることから、ビジネス分析やRUMなどを一元的に運用管理できるオブザーバビリティが必要だという。
また、ITシステムのレガシー化や大規模・複雑化に対応するため、AIによるリアルタイムな把握と、根本原因分析が可能な自動化された運用プラットフォームが望ましいとのこと。さらに、サイロ化された組織とツール群がDX(デジタルトランスフォーメーション)の障壁になっていることを鑑みて、組織を横断的に統合しつつ乱立したツールも統合してビジネスの意思決定を支えるBizDevSecOpsのプラットフォームが不可欠との認識だ。
徳永氏は、こうした日本における状況をふまえ、同社の強みとしてエンドツーエンドオブザーバビリティプラットフォームの提供、AIOpsの実現、Davisによる高度な分析機能の提供している点を挙げた。
注力分野は、ITエグゼクティブ層に向けた運用の高度化やビジネスオブザーバビリティの提案、開発チームが利用するクラウドネイティブ技術やAI実行環境に対するオブザーバビリティの提供、IT運用チームに向けた障害対応の迅速化・効率化の支援となる。
このような戦略に伴う組織体制とパートナーシップは、各業界の大手企業に対するハイタッチ営業の実施、国内SIerなどとのパートナーエコシステムの構築、ローカライゼーションといった国内顧客のサポート体制の強化を図る。
ターゲットに置く業界は製造業、金融業、デジタルエンターテイメントの経営層やIT部門開発部門などにおけるオブザーバビリティ活用を重点的に支援し、インフラ、アプリの監視にとどまらず、エンドツーエンドのオブザーバビリティを導入の目的とした案件の大型化をもくろんでいる。
最後に、徳永氏は「一連の施策に取り組むことでFY25(2024年4月~2025年3月)と比較して、FY26(2025年4月~2026年3月)は3倍以上のビジネス成長を目指す。数年のスパンで見れば、それ以上の成長が期待できると考えている」と意気込みを語っていた。