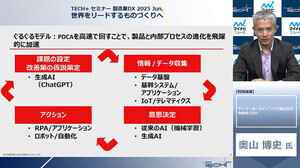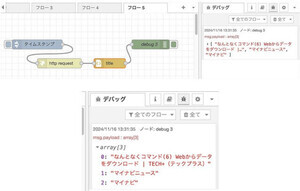公共事業の受注が9割以上
─ 3月に新社長へ就任されたばかりの中西さんですが、まずは就任の抱負を聞かせてもらえますか。
中西 当社は1959年の創業以来、高度な技術力で水インフラの持続に貢献することを経営理念としてきました。
この理念の下、多くの先輩方や社員が会社を築いてきたわけで、これからも人が資本であり、人材が生命線ということに変わりはありません。そうした伝統を持続させるためにも、技術開発とプロフェッショナルな人材を育成し、社会問題の解決に寄与することで会社を成長させたいと考えています。
─ まずは人が大事だと。
中西 はい。わたしは人が一番大事だと思っていまして、皆さんがやり甲斐を感じるような会社にしていきたいというのが第一の抱負です。あとは大きな成長というのは難しいかもしれませんが、安定成長と言いますか、確実に成長していく会社にしていきたいと思っています。
─ 上下水道の技術コンサルティングということですが、会社の成長性についてはどう考えていますか。
中西 国や地方自治体等、公共事業分野の受注が9割以上を占めていますので、安定して成長できると考えています。
特に近年は、記憶に新しい埼玉県八潮市での道路陥没事故や和歌山市での水管橋崩落事故等、施設の老朽化に伴う事故や地震、豪雨災害が頻発し、しかも激甚化しています。その意味で、国も上下水道インフラの強靭化への関心がかなり高まってきていますから、国がこれから国土強靭化へ予算をしっかりと付けていくということで、確実に受注や売上を伸ばしていきたいということですね。
─ 戦後80年が経ち、八潮の事故のように、日本全国いたるところでインフラが老朽化していると思うんですよね。その辺の現状はどうなっているのですか。
中西 八潮の事故は当初直径10メートル、深さ5メートルの穴が空いたわけで、あれほど大きな陥没事故は稀ですが、小さい陥没事故は結構あるんですね。
年間何千件と起こっていますから、事故自体は珍しいものではありません。下水道管に劣化による穴が空いたことが直接の原因ですが、その劣化の要因については、今後調査が進められることになります。よく言われているのは、水道管は水圧が掛かっている満管状態なので、水道管に穴が空いたら水が噴き出すので、目に見えてわかるんですよね。水道管は割と浅いところにありますから、地震で接続部分が外れたり、破損したりすることも結構あります。
ところが、下水道管は深いところにありますし、満管ではなく水路のように流れているので、管の中に空間があるんですね。だから、穴が空いたら上部の土砂が中に入ってしまう。それで段々と空洞ができて、道路が陥没してしまうのです。
─ 水道管と下水道管でそういう構造の違いがあるわけですね。
中西 ですから、こういう箇所は普段見えていないだけで全国に結構あると思います。
─ そうすると、どのように対応していくべきですか。