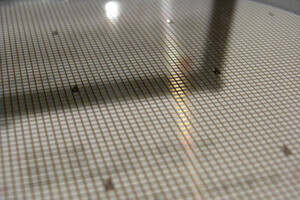移動手段から移動する舞台へ
2023年9月。プロレス興行団体の社長でもある高木三四郎選手と、高木選手の長年のライバル、鈴木みのる選手が対戦。エルボーやチョップが繰り出され、最後には鈴木選手による「ゴッチ式パイルドライバー」が決まって鈴木選手が勝利した。
実はこのプロレスの試合が開催された会場は体育館やイベントホールではない。JR東海が運行する東海道新幹線の車内だ。最高時速285キロの車内で繰り広げられた熱戦に参加した75人のファンは大いに盛り上がった。「さすがにプロレスをやりたいと言われたときは『できないだろ』と思ったのが当時の正直な感想だった」と同社営業本部法人営業グループの担当者は振り返る。
いま東海道新幹線は1車両の貸切りが可能になっている。修学旅行や社員旅行で車両を貸し切るという意味ではない。貸切りした1車両に加えてモニターや音響設備なども貸し出し、利用客がオリジナルの車内装飾や車内放送ができるようするもので、同社がJTBと始めた「貸切車両パッケージ」だ。
冒頭の「新幹線プロレス」以外にも昨年3月には「おいしい新幹線」を運行。食の雑誌とのコラボレーションとして開催され、貸切り車両に東京・四谷の寿司店「後楽寿司 やす秀」の板前が同乗し、車内に運び込んだネタを使って車内で寿司を握り、コース仕立てで提供した。
他にも日本酒「ワンカップ」で知られる大関。ワンカップが発売から60周年を迎えたことを機にファン感謝祭として「ワンカップ号」を走らせた。車内の座席にある背もたれカバーにはワンカップのロゴが入り、床には青いカーペットが敷かれた。
鉄道会社にとって安全・安心が1丁目1番地に位置付けられる中で、JR東海が大きく舵を切ったことには訳がある。コロナ禍だ。昨年60周年を迎えた東海道新幹線は1987年の同社発足時は東京―大阪間が約4時間だった所要時間を約2時間30分に短縮させ、1日平均231本だった運行本数も平均373本に増やした。1時間当たり最大12本という「のぞみ12本ダイヤ」によってビジネスマンの出張需要や観光客の移動需要を獲得。コロナ禍前の20年3月期の同社の営業利益率はJRの中でも断トツの35.6%だった。
しかし、コロナ禍で景色は一変する。コロナ禍が直撃した20年4月、東海道新幹線の利用客数は前年同月の9割減という前代未聞の状況に陥り、業績も21年3月期通期の連結最終損益が1920億円の赤字と、民営化後初の赤字を記録した。
主力のビジネス客が蒸発したことで新たな需要獲得が至上命題となったのだ。23年4月に社長に就任した丹羽俊介氏は新しい発想による収益の拡大に取り組んだ。その際に強調したのは「自由に考え、大いに議論し、粘り強くやり抜く」ということ。
前出の担当者も「新幹線の貸切りを実現させるためには、駅や車両、駅員など多方面にわたる社内の調整が必要だった。しかし、ノーは言わないと決めていた」と語る。そこで先の新幹線プロレスでは「車両の設備を破壊しない」「車内を汗で濡らしてはいけない」などのルールがある中で「5分に1回の汗拭きタイムを設けてクリアした」。また、おいしい新幹線では保健所との連携強化を図って実現させた。
これらの貸切車両パッケージは収益向上に大きく貢献するわけではない。足元ではビジネス客も戻り、インバウンドで乗車率は高止まりしている。それでも新幹線を単なる移動手段ではなく、イベントや発表会などの〝移動する舞台〟として活用することによって、新たな法人客の獲得に結び付ける考えだ。
改造した専用車両を投入へ
「新幹線のスピードを価値に変えていく」─。JR東日本社長の喜㔟陽一氏は語る。コロナ禍で新幹線が苦境に陥ったのは同社も同じ。そこで東北や北陸といった農・水産物の生産地を管轄内に抱える同社は地方創生にもつながる取り組みとして新幹線の客室などを活用して荷物を運ぶサービス「はこビュン」の拡大に力を入れる。
これまでスポット契約でのサービスだったが、4月18日から大口の定期輸送サービスと車両貸しサービスを開始。東京―新青森間で客室を使用した車両貸し輸送を始める。また、山形新幹線の「つばさ」などに使われているE3系1編成の全号車を荷物輸送の車両に改造。全号車の座席を取り外して床面をフラット化し、25年秋にも盛岡―東京間で輸送を始める。年間100億円規模の売り上げを目指す。
地方創生にもつながるJR東日本の「はこビュン」
新幹線での輸送であれば速達性と定時性の面でトラック輸送よりもメリットがあり、生鮮品や精密機器、医療用品などの輸送と親和性が高い。また、物流業界の人手不足の解決策の一助にもなり得る。「行く行くは飛行機と結び付けて海外にまで広げていきたい」と同氏は語る。
1987年に国鉄が分割・民営化され、35年余が経った。その間、人口減少が続き、リモートワークも普及するなど、新幹線を巡る環境は大きく変化している。将来「空飛ぶクルマ」が普及すれば更に競争は激しくなる。その中で日本の大動脈としての新幹線が持つ潜在力をどう掘り起こしていくか。新しい発想が求められてくる。