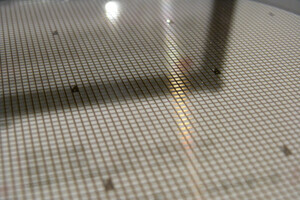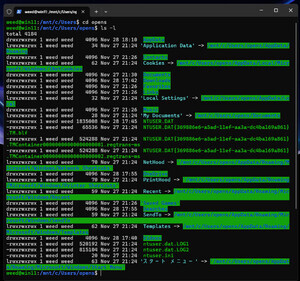DEIとは、「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」の頭文字を取った略称。これは、個々の違いやニーズに応じて、公平な機会と待遇を提供することを目指す組織的なフレームワークとなっている。
企業経営において「社員それぞれが持つ多様な個性が最大限に生きることがより高い価値の創出につながる」ということを背景に、DEIを意識する企業が増えている。
電通では、「管理職の多様性」も追及するため、「ミライGM(MGM)」の取り組みをスタートさせた。
本稿では、第5CRプランニング局(以下、「5CRP」)CMプランナー/クリエイティブ・ディレクターの岡野草平氏に、「ミライGM(MGM)」の取り組みについて聞いた。
後半では、MGMとしての業務にあたる大来優氏と沼澤祐治氏に活動内容や取り組みに対する想いを聞いた。
「ミライGM(MGM)」の活動内容
「ミライGM(MGM)」とは、電通の第5CRP内で導入されている制度で、現GM(ゼネラルマネージャー)とは異なる性別/年代の社員が副GMとして、GMと2人で部員の育成、組織運営を行う「ペアGM制度」のこと。この取り組みにおける副GMを「ミライGM(MGM)」と名付けられている。
ペアGM制度の目的について岡野氏は、「局にとって」「MGM本人にとって」「GMにとって」という3つの軸で説明した。
「まず局にとっては、5CRP内に管理職の多様性を生み出すことで、人財育成、組織運営においての視点を増やすという目的があります。そして、MGM本人にとっては、GMの主たるミッションである『部員の育成』や『組織運営』を早期に体験することができ、局にとっても、MGM本人の成長支援を促し、キャリア設計への気づきを獲得してもらうことができるという利点があります。また、この制度により、GMが抱える業務の負担軽減につながります」(岡野氏)
MGMの主なタスクは「1on1ミーティング」と「MGM会議」の2つ。
1on1ミーティングは、原則月1回行われるもので、GMとは違う目線で部員のキャリア相談に乗ることを目的としている。年齢の近いMGMだからこそ打ち明けられる悩みなどを吸い上げることもでき、MGMたちは管理職という立場で人財育成を経験することができる。
そしてもう1つのタスクである「MGM会議」は、MGMのみで局運営について議論する場。組織のマネージメントの経験を目的としている。
実際に筆者もMGM会議に同席させていただいたが、活発な意見交換が行われており、なかなか普段は経験することのない組織の業務について議論している様子が印象的だった。
月1回程度行われるMGM会議のトピックは、MGM自身から問題提起され、「若手の育成」「出社率」「局内コミュニケーションの活性化」「仕事のアサイン」「多様な働き方のサポート」など多岐にわたっている。
上記2つのタスク以外にも、「MGM主催の部会」「CD(クリエイティブ・ディレクター)会への代理出席」などについて、各GMとMGMが相談の上、決定・実行しているという。
MGMとして活躍する2人にインタビュー
MGM導入の成果について、岡野氏は「MGMが管理職の主たる業務を経験したことで、本人の管理職業務への理解向上と就任意向が向上した」と説明した。
さらに組織にとっては、管理職になることへの懸念の払しょくや管理職候補者プールを可視化できたことが大きな成果だという。MGMを打診したことで隠れ管理職意向者が顕在化したことに加え、MGMに対する部員からの高い評価も相まって、組織や本人さえ気づいていなかった新しい管理職の適正を発見することができたというメリットがあったという。
今回、話を聞いた大来優氏と沼澤祐治氏もMGMに選出されたことでリーダーシップの素養を発見できたメンバーだ。特に沼澤氏は「自分の業務も抱えている中で、それとは別に1on1を毎月行うことに不安があった」と、当初はMGMへの取り組みに後ろ向きだったという。
しかし、1on1の取り組みを通じて沼澤氏本人も部員の近況を知ることができ、楽しめるようになったと話す。部員からも「一見、寡黙で自分から話すタイプではないように見えるが、包容力や傾聴力が高く、部員がすごく話しやすい。GMに向いているということが、みんなに伝わる機会になった」という声が上がっており、本人・部員ともに同氏の適正に気付くことになったそうだ。
一方の大来氏は「会社に所属している以上、組織と自分は切り離せない。以前から、リーダーとしての役割や組織運営への興味はあったものの、自分から言い出すきっかけを作ることができなかった」という。
しかし今回のMGMの取り組みによって、大来氏のような隠れた管理職意向者のやりがいの発見にもつなげることもできた。
実際にMGMに選出された後も「良い取り組みだと思う。部内で話して、他者の悩みを聞いて、組織の中で貢献できていると感じるきっかけになった。また、コミュニケーションを取ること自体が楽しい」と、大来氏は語ってくれた。
最後に今後の目標について、沼澤氏に聞いた。
「GMには権限があるからどうしても距離感ができてしまいます。MGMは目線が近いからこそやれることがある。どうすれば組織がもっと良くなるかを考え、これからも上手く進めていきたいと考えています」(沼澤氏)