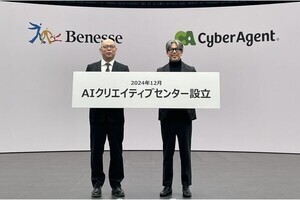ベネッセコーポレーションは3月25日、「従業員の学びと組織の成果」に関する記者説明会を開催した。説明会では、ベネッセと村田製作所が共同で行った「学びの費用対効果(ROI)」に関する調査の内容をまとめた「従業員の学びと組織の成果」の発表が行われた。
説明会には、ベネッセコーポレーション Udemy事業本部 ラーニングデザイン部 部長の内木場絵里、マーケティング統括部 データ戦略推進責任者の大塚卓氏、ラーニングデザイン部 研究責任者/ベネッセ教育総合研究所 研究員の佐藤徳紀氏が登壇。業種別の「組織における従業員の学習意識調査」、村田製作所との共同調査の結果の2点を発表した。
労働人口が減少に向け求められる戦略「全員戦力化」
人手不足が叫ばれる中、日本企業では従業員一人ひとりの生産性を高めることが重要課題になっている。加えて、生成AIの進化を筆頭に労働環境も激しく変化しており、従業員個人にとっても、従来のスキルだけでは活躍を続けることが難しい状況が訪れつつある。
そのため、企業・従業員の双方にとって学び(リスキリング)による新たなスキル獲得が急務となっており、それと同時に個人の学びや成長を組織の成果や発展に結びつける仕組みづくりが必要とされているという。
「労働人口が減少しているという環境の変化によって『全員戦力化』という戦略が求められています。その中で、組織力開発を進めることで、人材としての総合的な力を向上させることができ、企業価値の向上につながると考えられます」(大塚氏)
同社では「企業が目指す状態」について、「学習環境が整う」「学習する人が増加する」「業務につながる学びができる」「知識を仕事で活用する人が増加する」「組織全体の成果(売上増や新規ビジネス)を得られる」という5ステップを挙げている。そのための支援として、「学びの活用による組織変化(組織学習)」と「個人(社員)の学習による知識獲得」の2点を掲げている。
「個人学習」における学習成果に関わる構成要素としては、自立学習に取り組んだ「学習目的」、新しいスキルを学ぶ「きっかけ」、学習機会が増加する「学習習慣」の3点が重要になってくるという。
反対に「組織の取り組み」における学習成果に関わる構成要素としては、職場内でスキル獲得の「期待」、自立学習において職場の「サポート」、学んだことを職場で「活用する機会」の3点が挙げられている。
最初に発表された業種別の「組織における従業員の学習意識調査」は、個人・組織における学習成果に関わる構成要素として挙げられた「学習目的」「期待」「きっかけ」「サポート」「学習習慣」「活用機会」の6点について、IT/情報・通信業/銀行・証券業/コンサル/製造業/保険業という6業種で調査を行ったもの。
なお、調査の結果は以下のようになっている。
ベネッセ×村田製作所による共同調査の結果
村田製作所は、2021年に策定した「長期構想Vision2030」と「中期方針2024」に基づき、成長戦略の一環としてDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を掲げ、「個人を変える」「組織を変える」を軸として、DX人材育成を進めている。
同社は、DX人材育成の質をさらに高め、個人の学びと組織学習推進がどのような成果につながるかを明らかにするため、ベネッセと共同調査を実施した。
今回の調査の結果、「組織学習」は「組織成果」を促進する可能性があることが分かったという。
特に「組織学習」の中でも、獲得した知識を組織に共有する「情報分配」、知識を実際に使ってみる「情報解釈」、知識を将来の使用のために蓄積していく「情報記憶」との関連が確認され、それらを促進することで「組織成果」の向上につながる可能性が明らかになった。
さらに「組織学習」に関連を与える要素を分析するため、関わりがあると予想される「学習推進(スキル獲得についての個人の意識や組織の取り組み)」「業務成果(学習結果を個人の業務や改善に生かせたか)」「心理的安全性」との関係を調べた結果、職場において、「失敗しても問題ない」といった心理的安全性が確保されている場合、「組織学習」が促進される可能性が高いことが判明した。
また、個人が学びを継続し、その学びを組織の成果に結びつけるためには、「学習期待:職場や上司から新たなスキル獲得への期待があること」「学習サポート:会社や職場が学びをサポートする環境を提供していること」「学習継続意向:個人がスキル獲得のための学びを継続する意思を持っていること」という3つの要素が重要であることも分かったという。
最後に、内木場氏は「2つの調査を通して、組織の学びを進めている人材と実際に学びに取り組む従業員の間にギャップがあるのではないかと感じた。これからも調査などを続けることで、より学び続けられる環境を作っていきたい」と今後の展望を述べていた。