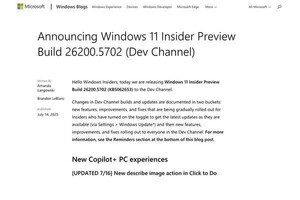人の採用をどう進めていくか─。人手不足が深刻な経営課題となっている。物流業界では「2024年問題」がクローズアップされたが、根本的な解決には至っていない。その中で「仲間づくり」を標榜して成長を図っているのが小売業に特化した3PL(物流一括請負)大手のAZ-COM丸和ホールディングス。社長の和佐見勝氏は「人の採用と荷主への料金改定交渉は経営トップの仕事」と語り、顧客との交渉に臨んでいる。およそ2700社の中小運送事業者等を束ねたネットワークを生かしながら次なる成長に舵を切っている。
5年間で5000人採用へ
─ 物流業界をはじめ、産業界全般で人手不足が大きな経営課題になっています。「物流の2024年問題」が叫ばれ続けていますが、物流業界の現状認識から聞かせてください。
和佐見 今も深刻な人手不足は間違いなく続いています。物流の2024年問題はドライバーの年間の時間外労働時間の上限を960時間に制限するものですが、これによって今までのような働き方ができなくなり、労働時間も短くなります。物流業界にとっては、輸送能力の低下が懸念されていたわけです。
それを何とかクリアするためにも、当社も人の採用に力を入れているところです。ただ、これがなかなか難しい。当社は2022年からの5年間で5000人の社員を採用する計画を掲げていました。その内訳は新卒採用が3000人で、中途採用が2000人です。
2年ほどが経過しましたが、フタを開けてみると、厳しいというのが正直なところです。当社の25年度の新卒採用は320~330人の見込みです。計画に掲げる3000人を実現するためには毎年600人必要なのですが、半分強に過ぎないというのが現状です。
新卒採用の目標達成が難しいため、中途採用も含めて年間を通して採用活動を行っています。物流業界に限らず、どの業界でも人を集めることは大変だと思います。
─ 5年間で5000人ですから、全体で年間1000人の採用を継続しなくてはならない。
和佐見 ええ。様々な経営者に話を聞いてみても、どこも人が採れないという悩みを持っています。特に新卒を採用できるようにしたいとなれば、初任給を上げなくては興味を持ってもらえません。
そういう意味では、「人手不足の解決=コストがかかる」という経営になってきたと言えますね。
少し前までの物流業界の大卒初任給は平均約22万円ほどでしたが、足元では政府からの賃上げの要請も相まって大手企業などでは25万円前後にまで高まっています。
そうすると、新卒だけの初任給を上げても入社2年目以降の社員の給料も上げなければバランスが悪くなってしまいます。ですから、全体のコストも上がってきます。
それでも年明けにはカジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングさんが新卒の初任給を30万円から33万円に引き上げると発表されましたが、これには驚きました。他にもマンション建設の長谷工コーポレーションさんが総合職の大卒初任給を30万円にしています。
我々と同じように建設業界も人手不足で苦しんでいますが、そういった業界の企業も初任給でかなりの金額を出すようにしているわけです。ですから、経営者としては、人を集めるための賃上げの原資をどう確保するかが一番の課題です。
料金改定にどう臨むか?
─ 賃上げの原資には料金改定が必要になります。そこはどう臨んでいきますか。
和佐見 おっしゃる通りです。人を集めるためにはコストがかかり、その原資を得られるかどうかは荷主への料金改定を図れるかどうかにかかっています。これがまた簡単にはいきません。当社の料金改定の浸透度もかなり厳しい。
─ 和佐見さん自身も料金改定の交渉の現場に赴く?
和佐見 はい。私も含めて役員・幹部社員が手分けしてお客様に直接お会いしてご説明するようにしています。
中には「少し待ってください。上げないとは言いませんが、もう少しだけ待ってください」とおっしゃるので、こちらも「いや、待てないんです。コストの負担が大きいのです」と事情を説明して何とかご理解いただくようなケースもあります。これからの時代は安売りできませんからね。
企業経営は「売上最大・経費最小」が肝要です。
─ シビアな環境がしばらく続きそうですね。AZ-COM丸和グループは小売業に特化した3PL(物流一括請負)を得意としていますね。各業界の顧客の反応は違いますか。
和佐見 濃淡がありますね。当社は主に3つの事業を核に展開しています。「EC(電子商取引)物流」「低温食品物流」「医薬・医療物流」になります。近年ではそれに加えて「BCP(事業継続計画)物流」事業を展開しています。
その中で低温食品物流のお客様は主に食品スーパーさんになりますが、対応はまちまちですね。ご理解いただいている顧客がある一方で難しい顧客もあります。
─ 料金改定の浸透度はどのくらいなのですか。
和佐見 目標の達成にはまだまだです。厳しい状況に変わりありません。今期中に目標を達成できるようにしなければならないと考えています。これはやはり社長・役員・幹部社員の仕事です。
中には今まで当社がご奉仕した荷主さんもあって、10%近く上げてもらわないと厳しいというケースもありますからね。
─ EC事業者の対応はどのように分析しますか。
和佐見 どうやって料金改訂を理解していただくか。我々の力量が問われるところだと思います。特にラストワンマイルの宅配は荷物の量が非常に多い。
ですから、当社のような物流会社にとっては、荷物をいかに効率的に取り扱うかということと同時に、高品質を維持し、他の協力会社さんとも強固な物流ネットワークを構築していかなければなりません。
EC事業者によっては、品質よりも価格を重視して、より安い運賃で運んでくれる運送会社さんに切り替えるところも出てくるでしょう。これはどこのEC事業者も試行錯誤しています。
─ 揺れ動く環境の中で和佐見さんはどういった経営信条で臨んでいきますか。
和佐見 こういうときこそ、ブレを起こすような経営はできないと思います。また、そういった経営を行ってはいけないとも思っています。社内外共に経費削減策を採らないといけません。
賃金だけでなく、車両や燃料なども値上がりしていますので、料金改定をしなければ、生き抜いていくことはできません。
中小運送事業者のネットワーク
─ 先ほど他の運送事業者との協力と言っていましたが、そういったネットワークを構築している強みがあると。
和佐見 そうです。15年に丸和運輸機関が中心となって創立した運送事業者のネットワーク「AZ-COM丸和・支援ネットワーク(AZ-COMネット)」がそれです。AZ-COMネットに加入しているのは主に中小運送事業者です。
ただ、中小運送事業者だと、今のように燃料費や車両購入費が高騰している環境下では、どうしても1社ごとの負担が大きくなります。
─ 運送事業者は全国にどのくらいあるのですか。
和佐見 約6万3000社のトラック運送事業者があります。それらの多くは若いドライバーの不足に直面していたり、トラックや燃料などのコスト負担による財務の逼迫にもさらされています。
他にも荷主からの不利な取引条件を強いられたり、さらには後継者問題といった山積する様々な課題を抱えています。
しかし、こういった中小運送事業者を束ねれば価格交渉力が出てきます。ネットワークを組むことで規模が大きくなり、バイイング・パワー(購買力)が強化されるわけです。規模を生かして車両や燃料の購入コストを抑えることができます。
─ 具体的には?
和佐見 AZ-COMネットに加入している会員企業には当社の仕事を年単位の長期契約で請け負ってもらっています。また、トラックなどの車両の購入でも丸和運輸機関で購入する車両と他の会員企業の購入する車両を束ねることで、それらを合計した台数で取引し、価格に対する交渉力を高めています。
これは車両だけではありません。燃料をはじめ、事務用品やOA機器・その他経営資源なども含まれます。これらは個社で買うと量が少なくなるため、価格交渉力が弱くなります。
しかし、当社と会員企業を合わせれば交渉力が強まる規模になります。会員企業は本年1月末時点で2712社ですから、メリットが高まります。他にも高路料金の大口割引といったメニューもあります。
─ 車両を割安で購入できるのは大きなメリットですね。
和佐見 ええ。そもそも運送会社にとってトラック車両の有無は商売の決め手になりますからね。荷物を運ぶ車両がないと言ったら、そこで終わってしまう。ですから今は車両を出しながら辛抱強く料金改定の交渉を続けているような状況です。
AZ-COMネットでBCP物流に参画している会員企業が保有する車両台数は約8000台になります。目標は3万台です。というのも、先ほど申し上げた当社の事業の柱の1つであるBCP物流を全国で展開するには、それくらいの台数が必要になるからです。
AZ-COMネットの会員企業で連携してBCP物流を広げていき、各社の強みにしていきたいと。
─ 工夫次第で厳しい環境でも乗り越える道筋が描けますね。実際、荷主企業の間でも物流に対する工夫が出てきました。
和佐見 その通りです。AZ-COMネットなど運送会社のネットワークを活用するケースもありますが、それだけでは不十分です。やはり荷主企業の方々にも意識を変えていただかなくては難しい。その意味では異業種が連携して荷物の混載をするケースが出てきています。
お客様がそういった努力をされているわけです。それなのに我々が何もしないということではいけません。そうしないと、お客様からのご評価もいただけない時代になっています。
TOB不成立の教訓
─ 自らも努力をしていくということですね。さて、昨年は同業のC&Fロジホールディングス(HD)に対してTOBを行いましたが、不成立に終わりました。教訓を聞かせてください。
和佐見 もともとC&FロジHDの経営陣の皆様とは経営統合に向けて協議を行っていましたが、社長交代で同社の経営方針が変わってしまいました。そして、佐川急便を擁するSGHDさんも名乗りを上げ、TOB価格が吊り上がりました。
当社の買付け価格は三方良しを意識した1株3000円でしたが、SGHDさんは5740円。辞退することを余儀なくされました。
ただ、C&FロジHDさんのビジネスはもっと大きくなっていいと思います。
冷蔵・冷凍食品を運ぶための冷蔵・冷凍施設などを保有していますし、冷蔵・冷凍に関する専門の技術機能も持っていますからね。アレンジメントできる人材も豊富です。しかし、当社は正直すぎましたね。
─ 今回のTOBは不成立でしたが、仲間づくりが今後のポイントになりそうですね。
和佐見 私はそう思っています。それは物流業界だけに限りません。ですから、大学とも様々な連携をしています。例えば、東京大学とは同大学スポーツ先端科学連携研究機構とタッグを組んでスポーツ科学の共同研究を行っています。
当社はもともとスポーツ活動に力を入れており、21年に、東京大学柏地区キャンパスに私が最先端のラグビー場の整備を寄付した縁もあります。また、京都大学にもラグビー場を寄付しました。
両大学の学生が当社を就職先として意識していただければ嬉しいですが、何よりもスポーツを通じて誠実なプレー、熱き情熱、チームの結束、礼儀正しい規律、そしてプレーさせていただくことへの感謝を得られます。
それは当社が関東・関西で2つのラグビーチームを運営しているので、よく分かります。
ありがたいことに東大からは22年に「東京大学稷門賞」を受賞させていただきました。これを励みに、大学のみならず、業界の垣根を超えた当社グループの理念を理解する同志づくりを進めていきたいと思っています。