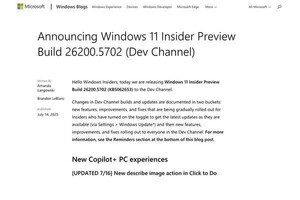自国第一主義台頭の中 経営のカジ取りは?
現在の世界の動きを見ると、米国をはじめ、自国第一主義が勢力を持ち始め、分断・対立の様相が深まる。
「ええ、自国第一主義になってしまったので、やたらあちこちに壁ができているわけですね。今までグローバリゼーションの推進で、世界は一つという感覚でやって来たのに、こうなると対応が全然違ってきます」
キヤノン会長兼社長CEO(最高経営責任者)の御手洗冨士夫氏(1935年生まれ)は世界の現状についての認識をこう示し、「経済人のわれわれにとって一番困るのは、先が見えないということ。非常に対応の難しい世の中になりました」と語る。
みずほ証券チーフマーケットエコノミスト・上野泰也が予測「2025年の景気」
キヤノンは1937年(昭和12年)に精機光学工業として創業。戦後、カメラや事務機器で成長し、最近は半導体露光装置や次世代製造装置、メディカル(医療機器)分野への投資などで事業構造改革を進めてきた。
2024年12月期決算では、売上高4兆5400億円(前年同期比9%増)、営業利益は4555億円(同21%増)になる見通し。通期の為替レートを円高方向に見て、1ドル=149円62銭、1ユーロ=163円19銭に設定しての見通しである。
今年1月20日、米大統領に就任し、2期目の政権を発足させるD・トランプ氏の関税や移民政策に関する発言一つで、為替も激しく揺れ動く状況。先行き不透明な中で、経営のカジ取りをどう進めていくかという命題。緊張感は世界全体に広がる。
キヤノンの場合、全売上高の78%は米国や欧州、中国を含むアジアなど、海外での販売である。当然、グローバル情勢がどう推移していくかに関心を払わざるを得ない。 冷戦崩壊後の グローバリゼーション下で 2025年は先の大戦から80年という節目の年。戦後しばらくは、資本主義対社会主義の東西冷戦という構図の対立が続いた。それが終焉を迎えたのは1989年(ベルリンの壁崩壊)。
この時からグローバリゼーションが一気に加速し、ヒト、モノ、カネといった経営資源が自由に世界を動き回るようになった。
「世界中で価値の交換が自由に行われるようになり、世界中が豊かになった」と御手洗氏。
中でも、著しい成長を遂げたのは中国。1978年、当時の最高指導者・鄧小平氏が改革開放路線を掲げて、外資や海外の先端技術を呼び込み、2010年に中国はGDP(国内総生産)で日本を抜いて、米国に次ぐ世界2位の経済大国となった。
日本は2024年、GDPでドイツにも抜かれ、現在は世界4位というポジション。
この間、世界的金融危機となったリーマン・ショックが起き、世界中が景気低迷に入る。英国がEU(欧州連合)から離脱するなど、自国第一主義の芽が吹き始め、グローバリゼーションに黄信号が灯り始めた。
現下の混沌状況に、グローバル企業として、どう対応していくかという命題である。
「わたしが社長になった時、日本国内中心の企業活動では、会社は大きくならないと。やはり、世界に市場を求めないといけないということで、経営体制を変革してきました」
御手洗氏が社長に就任したのは1995年(平成7年)のこと。それまでは海外にあるキヤノンの販売会社は、言ってみれば支店のような存在であったが、氏はそれらを、その国に籍を置く会社という位置づけに変えていった。
「ええ、海外の販売会社を全て現地法人化し、一定の独立性を持たせたわけです。わたしの23年間の米国駐在のうち、最後の10年間はキヤノンUSAの社長でしたが、会社を成長させるためには、独立した販売会社として、各々の地域に根差した経営をしなければならないことを痛感していました」
決算は連結するが、本社(東京)のためというより、「その国や地域で一流の会社になると。そういうふうに持っていったわけです」と御手洗氏は語る。
現地に根付くグローバル化を進めてきた理由
「海外で仕事をする場合は、現地の社員たちの信頼を獲得しなければいけない。それから取引先の信頼獲得。信頼を獲得しなければ、きちんとした経営はできない。そういった信頼を獲得するには、最低10年かかる。これは、わたしの経験です。それに基づいて、そういう布陣にしているわけです」
御手洗氏は1966年(昭和41年)から23年間、米国で市場の開拓に努めた。
キッコーマン・茂木友三郎 取締役名誉会長が考える「日本経済再生の道筋」
1966年は、日本は高度成長の真っ只中。その2年前には第1回東京五輪が開催(1964年)されたが、翌1965年(昭和40年)には、"40年不況"と呼ばれる証券不況が起こり、山陽特殊製鋼が当時最悪の負債総額で倒産するといった場面もあった。
1989年(平成元年)は、"昭和"から"平成"へ時代が移り変わる時で、世界に目を向ければ、『ベルリンの壁』が崩壊し、東西対立の冷戦構造が崩れた。資本主義(西側陣営)が社会主義(東側陣営)に打ち勝ったとされた年。
世界は目まぐるしく変化。旧ソ連邦を構成していたウクライナは2022年2月、ロシアの侵攻を受け、戦争は今も続く。
中東では、イスラエルとイスラム軍事組織との戦闘である。
東アジアに目を転ずれば、台湾問題に世界の関心が集まる。中国が台湾にどう対処してくるかで、東アジア情勢も大きく変わる。グローバリゼーションを撹乱する要因が増え、自国第一主義に走る国が増加しているのが現状だ。
また、御手洗氏が社長に就任した1995年は、インターネット元年とされる年。BtoB(企業対企業)、BtoC(企業対消費者)、CtoC(消費者同士)と、企業も個人も活動の領域が格段に広がった。
この30年間で、グローバル世界の環境は激変。それに対応するために、御手洗氏は米国、欧州、アジアの3拠点に、それぞれの国や地域に精通した人物をトップに置き、現地の変化に即座に対応できる布陣を取ってきた。
「米国会社のトップの在任年数は19年、欧州のトップは39年、中国のトップは20年です」と御手洗氏は語り、「これも世界の地域の変化を外で吸収できるようにするための措置。とても日本から命令して操作できる時代ではないですからね」と強調。
先端技術の開発で 市場を変革し続けてこそ
1月下旬、米国はトランプ大統領の2期目がスタート。対中国政策は、安全保障の観点から基本的に厳しい政策を取り、貿易では関税を10%から20%高くし、自国内産業を"保護"する方向にカジを切るものと見られる。隣国のメキシコやカナダなども影響を受けそうだ。
トランプ氏がどのような手を打ってくるか、世界中が固唾を飲んでいるが、一方で、トランプ氏が「市場の動向には関心を向けている」という見方もある。
「トランプ大統領の政策の変更はともかく、米国の市場はそう簡単には変わらないと思います」と御手洗氏は語る。
スガシタパートナーズ社長・菅下清廣が予測「トランプ再登場後の株式市場」
基本的に米国市場の、品質のいいモノ、付加価値の高いモノやサービスは受け入れる─―という本質は変わらないという氏の認識。
「米国はこれまでも、先端技術で世界の潮流をつくってきていますよ。GAFAMでITブームを起こして、米国の産業は変わったじゃないですか。昨今のエヌビディアとか、最先端技術によって、産業が進化し続けるという流れは変わらない」
GAFAM。グーグル、アップル、フェイスブック(現メタ)、アマゾン、マイクロソフトなどのビッグ・テックと呼ばれる巨大IT産業が登場し、世界の景気を牽引してきた。インターネット社会の今日において、米国内外で存在感を放ち続ける。そこに、エヌビディアという新興半導体メーカーが登場。同社の強みは、AI(人工知能)時代に求められるGPU(画像処理装置)である。
時価総額で見ても、トップのアップルの3兆7853億ドル強に次いで、エヌビディアは3兆2887億ドルと2番手に付けている(ちなみに3位はマイクロソフト、4位はアマゾン・ドット・コム、5位テスラの順)。
日本円換算では、アップル566兆円、エヌビディア485兆円強という水準(1ドル=150円で計算)。
日本の時価総額ランキングでは、トヨタ自動車がトップで約47兆円強(1月9日現在)。アップル、エヌビディア共に、トヨタの10倍以上の時価総額となっている(ちなみにキヤノンの時価総額は6兆7000億円強)。
こうした現状で、日本再生・地方創生を図っていかなくてはならないということ。
「これから世界に追いつくのは本当に大変ですよ。日本はもっと先端技術開発に投資をするべきですし、国が主導して先端技術を育てる体制を構築すべきです。大学と産業界の結びつきも必要ですし、官民一体となって先端技術開発を進め、新しい産業を生み出していくべきです」。
産業と大学の連携、つまり産学連携をさらに深め、産業界も先端技術への投資に注力し、大学改革も同時に進める。そして、政府(国)も一体となって、先端技術開拓に臨むことが大事だということだ。
「世界秩序の構築をもう一回やり直さなければ。経済のグローバリゼーションをつくることが世界の平和と結び付くわけですからね」と語る御手洗氏。そのためにも、イノベーションが重要で、「日本(企業)も新しい価値を生んで、新しい産業をつくり、世界との価値交換を行いながら、社会も成長させていく必要があります」と言う。
政治(家)には、国の大本を決める責任があり、経済人や経済リーダーは、技術革新で世界の国々や人と人をつなぐ役割と使命を負うという御手洗氏の考えだ。