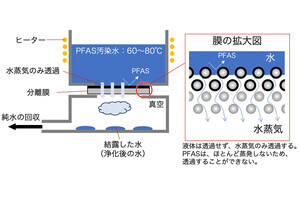日立ハイテクと東京科学大学は、水道水汚染が問題視され、健康上のリスクにつながることも懸念されるPFAS(有機フッ素化合物)の検出に関する共同研究を開始したと1月28日に発表。両者の技術とサービスを組み合わせ、PFAS検出の効率化をめざす。
今回の研究では、PFASの簡便かつ迅速な検出を実現する手法を検討。具体的には、東京科学大学がもつ、「ペプチド」(アミノ酸とアミノ酸が結合して、2個以上つながった構造の化合物)をセンサーとして利用する手法を用い合成高分子の検出・識別技術をベースに、日立ハイテクが提供する独自のデータベースを用いた化合物探索支援サービス「ケミカルズ・インフォマティクス」(Chemicals Informatics:CI)を組み合わせ、PFAS検出に有用なペプチドの効率的な探索・生成の実現をめざすとのこと。
PFASは耐熱・耐水・耐油などの特徴があり、生活用品・工業用品など多くの製品で幅広く使われているが、分解されにくい特性をもつため、廃棄物として処理後も海水や土壌に堆積する。昨今では、水道水に含まれるPFASが原因と想定される健康被害の報告を受け、各国で規制に向けた動きが進んでおり、日本国内でも2026年に自治体や水道事業者による定期的な水質検査の実施が法律で義務付けられるなど、対策強化に関する方針が固まっている。
現状のPFAS検出方法は複雑かつ時間を要するものであり、液体クロマトグラフ質量分析装置を用いた目的成分の溶媒抽出・濃縮作業には専門知識が必要とされるほか、1回の分析工程で前処理と測定に数時間と長い時間を要することも課題となっている。
今後PFAS検出頻度の増加が見込まれるなか、PFAS検出業務の効率化が求められることから、日立ハイテクと東京科学大学が連携。低濃度のPFASと相互作用するペプチドの効率的な探索を実現し、PFASの簡便・迅速な検出に関する検証を進める。また、PFASと相互作用するペプチドのPFAS除去への活用についても検証する予定とのこと。