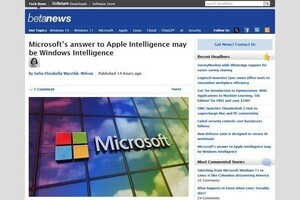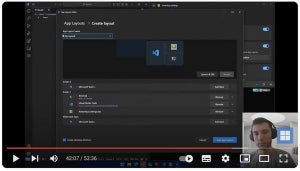BetaNewsはこのほど、「DeepMind dominates European AI research: What does this mean for researchers?」において、ヨーロッパのAI研究でGoogle DeepMindが支配的な影響力を持っていることが明らかになったと伝えた。
BetaNewsのレポートによれば、ヨーロッパのAI関連の研究で、DeepMindの研究がその引用のほぼ半分を占めたという。これは多くのAI研究が何らかの形でDeepMindの影響を受けていることを示しており、確かにその影響力は支配的というレベルに達しているかもしれない。
「引用バイアス」が問題に
Google DeepMindはイギリスに本拠地を置くAlphabetの子会社であり、AI関連の研究と開発において世界を牽引している。もともとは2010年に独立系企業として設立されたが、2014年にGoogleに買収されてその傘下に入った。代表的な成果物としては、世界で初めて人間の囲碁棋士に勝ったコンピュータ囲碁プログラムの「AlphaGo」や、タンパク質の構造予測を実行するAIプログラムの「AlphaFold」などがある。
DeepMindの功績はAhphaGoやAlphaFoldなどの名前を聞くだけでも十分に察することができるが、AI関連の引用数の調査によって、その影響力の大きさがあらためて明らかになったとBetaNewsは指摘している。AI分野における2020年から2024年のヨーロッパ大陸の引用数は33,450件で、そのうち半数近くに上る15,213件がDeepMindのものだったとのこと。その数は、他の7つの主要競合会社の引用数を合わせた数を上回っているという。
このような引用数の偏りの何が問題なのだろうか。BetaNewsは、こういった一極集中は、研究資金の配分や協力の機会に影響を及ぼし、イノベーションの可能性を制限する懸念があると指摘する。 引用数が高いことで、後に続く研究からさらに多く引用されるという「引用バイアス」が生じ、その反動で小規模な研究機関による優れた研究が過小評価される可能性があるというわけだ。
このような引用バイアスの問題を解消するためには、単なる引用数だけでなく、研究の実際の影響を広範囲に評価する新たな手法が必要とされる。
引用の大部分は西ヨーロッパの一部地域に集中
AI研究における引用数の調査では、ヨーロッパにおける別の問題も浮き彫りにしたという。それは、AI研究の引用の大部分が西ヨーロッパの一部の地域に集中しており、対照的に東ヨーロッパについてはほとんど記録されていないことが明らかになったのだ。
このような状況は、ヨーロッパ全体のAI研究の多様性と進展を妨げる可能性がある。BetaNewsのレポートでは、研究者や政策立案者は、より公平で包括的な研究環境を促進するための対策を検討する必要があると警鐘を鳴らしている。