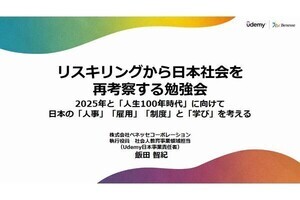HubSpot Japanは12月12日、日本のマーケティング組織で働くビジネスパーソンを対象に実施した「日本のマーケティングに関する意識・実態調査」の結果を発表した。
それに先立ち、12月11日に事前ブリーフィングが開催され、HubSpot Japan マーケティングチーム シニアマネージャーの土井早春氏が「日本のマーケティングに関する意識・実態調査」の調査概要を説明した。
「日本のマーケティングに関する意識・実態調査」の調査概要
コロナ禍による変化の波が落ち着いた2023年から2024年にかけて生成AIの爆発的な普及が起こり、Google検索をはじめとするマーケティング活動の主要領域に大きな変動が見られるようになった。
こうした状況の下、HubSpotが日々の商談やカスタマーサポートにおいて接する日本のマーケティング担当者から、「企業が従来のマーケティングプロセスを維持管理するだけではこれまでと同水準の結果を出すのが難しくなっている」という声が聞かれるようになったことを背景に、今回の調査は実施された。
同調査の対象者は、フルタイムで企業のマーケティング業務に従事するビジネスパーソン 計729名(BtoBマーケター423人、BtoCマーケター306人)で、11月14日〜19日の期間にオンライン上のアンケート調査で実施された。
今回の調査の目的としては「マーケティング担当者(マーケター)の意識や実態を可視化すること」「先行きが見えづらい事業環境の中でどのように新しいテクノロジーやツールと向き合っていくべきか考察すること」の2点が挙げられている。
86.3%が「マーケティングのやり方を変えていかなければならない」
マーケターに「企業が従来のマーケティングのやり方を続けているだけでは成果が出づらくなっている」という主張に対する自身の考えを聞いたところ、「そう思う」および「どちらかといえばそう思う」と答えた人の合計が82.6%と、肯定派が多数となった。同様に「企業は従来のマーケティングのやり方を変えていかなければならない」という主張を肯定した人は86.3%となった。
また各種マーケティング領域において「1年前と比較して成果が出やすくなったか、出づらくなったか」を聞いたところ、「成果が出づらくなった」「どちらかといえば成果が出づらくなった」と答えた人の合計値は多い順に「DM(メールではなく、物理存在する葉書や手紙)」が74.7%、「街頭広告(タクシー広告や電車車両内広告含む)」が72.2%、「テレビCM」が70.1%となった。
一方で、YouTubeなどの動画専門プラットフォームを活用したマーケティングやSNS運用(広告以外)については、「成果が出やすくなった」または「どちらかというと成果が出やすくなった」と考える人が多数派となる結果となっている。
生成AIの評価はこの1年で高まっている
業務支援ツールとしての生成AIの評価を調査した設問では、「1年前(2023年11月)と比較したとき、生成AIはマーケティング業務の役に立つようになってきた」(「そう思う」および「どちらかといえばそう思う」の合計)と答えた人の合計は全体の72.3%となり、業務支援ツールとしての生成AIの評価はこの1年で高まっていることが分かった。
生成AIを少なくとも週1回以上業務において利用していると答えた人は全体の32.7%となった一方で、業務において生成AIをまったく利用していないと答えた人は全体の28.9%と約3割にとどまる結果となった。週1回以上利用している人およびまったく利用していない人のいずれも、BtoB企業のマーケターとBtoC企業のマーケターの傾向に大きな差は見られなかったという。
さらに、業務において生成AIを利用していると答えた518人に具体的に使用しているツールを複数回答で聞いた質問では、1番多かったのが「ChatGPT」で全体の73.9%、2番目が「Copilot」(28.4%)、3番目が「Gemini」(15.4%)となった。最も回答が多かったChatGPTについては、利用者の34.4%が有料版を使っていると答えている。
また「マーケティング業務の中でストレスを感じていること」を複数回答の選択式で聞いたところ、1位が「情報収集の時間が足りないこと」(28.5%)、2位が「単純作業に時間が取られること」(27.7%)、3位が「欲しいレポートをすぐ作成できないこと(数字に加工が必要など)」(25.1%)という結果となった。
同時にこれらの3領域について「生成AIを使えば解決できるかもしれない」と答えた人はそれぞれ66.8%、71.3%、67.8%となり、生成AIへの期待が高いこともわかった。
83.4%が「業務の役に立つなら慣れないツールにも挑戦してみようと思う」
「勤め先で行っている業務の中で効率化したいものがあるか」を複数回答の選択式で尋ねると、1位「データ分析」(44.4%)、2位「プレゼンテーション資料作成」(36.8%)、3位「レポート作成」(36.4%)が上がった。
さらに選択肢それぞれに対して「効率化できる生成AIツールがあり、会社としても利用を禁止されていないとしたら積極的に利用したいかどうか」を聞くと、積極的に利用してみたいと答えた人は多い順に「データ分析(53.5%)」「レポート作成(52.3%)」「プレゼンテーション資料作成(51.2%)」がトップ3となり、効率化のニーズとほぼ対応する形に。
「業務の役に立つと分かっていれば、慣れないツールの使用にもチャレンジしてみようと思うか」という質問に対しては、全体の83.4%が「そう思う」および「どちらかといえばそう思う」と回答した。
また「日本は先進的なテクノロジー導入の波に遅れがちだと思う」と考えている人が全体の79%となった一方で、「生成AIについては、今から国と企業が努力を続ければうまく活用して成果を出していけると思う」と考えている人が全体の79.5%となり、生成AIの業務への活用に肯定的な傾向が見られた。
一方で、業務効率化できる生成AIのツールがあり会社からも利用を禁止されていないとしても「興味はあるが、難しそう」または「利用したいとは思わない」と答えた人に、その理由を複数回答で尋ねたところ、1位は「具体的な事例や実績を見ないと効果を信じられないから」(24.5%)、2位は「生成AIに対する知識がないから」(23.8%)、3位は「新しいツールを使いこなせる自信がないから」(22.1%)という理由が挙げられた。
生成AIの活用で成果が出ることを期待する人が多い一方で、実際に自分自身が使うとなった際には「新しいものに対する懸念」や「自信のなさ」がハードルになっていると考えられる結果となっている。