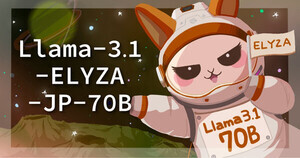LLM(Large Language Models:大規模言語モデル)の開発と社会実装を進めるELYZAは12月3日、コンタクトセンター支援事業に参入することを発表し、記者向けの説明会を開いた。コンタクトセンターのオペレーターの業務効率化に寄与するLLMプロダクトを2025年内をめどに展開するという。
コンタクトセンター向けプロダクトの概要
ユーザーとの対話記録やメールなどが蓄積されるコンタクトセンターは、LLMの活用が期待される事業領域。しかしその一方で、多くの導入事例はチャット形式のUI(User Interface)にとどまり、業務の中にLLMを組み込んで運用する例は多くないという。
ELYZAは2020年ごろからコンタクトセンターにおけるLLM活用を検討しており、複数社と連携してきたとのことだ。今回発表したプロダクトには、同社がコンタクトセンター領域で蓄積した知見や技術を搭載。オペレーターの業務高度化を支援することで、その結果としてCX(Customer experience:顧客体験)の向上に寄与する。
なお、新プロダクトは現在開発中であり、具体的な提供開始時期や価格は未定だ。直販モデルの他、KDDIグループのアルティウスリンクなどBPOパートナーを経由した間接販売などで展開する。
JR西日本コンタクトセンターで分析パッケージを利用開始
説明会には、JR西日本で「お客様センター」を運営するJR西日本カスタマーリレーションズの社長である堤恵理子氏も登壇した。両社は生成AIを活用したVoC(Voice Of Customer:顧客の声)分析パッケージの実運用を開始している。
JR西日本お客様センターは尼崎と広島にそれぞれコンタクトセンターを持ち、1日当たり約2200件の電話と、約290件のメールに対応しているそうだ。このうち「ご意見・ご要望」は3%程度の約75件。
JR西日本カスタマーリレーションズは2022年から、顧客対応業務の品質向上とオペレーターの業務負荷軽減を目的に、生成AIを起点とした業務フローの見直しプロジェクトを開始した。アフターコール業務において要約AIを導入したところ、通話後のレポーティングなど要約作業時間を1件当たり65秒削減できたという。「ご意見・ご要望」のみに限れば、1件当たり230秒の削減に成功している。
しかし、人的リソースの制限などが要因となり、蓄積した対応履歴を用いたVoC分析には至っていなかった。以前は「ご意見・ご要望」のデータのみVoC分析を行っていたという。
こうした状況の中で、ELYZAが開発したコンタクトセンター向けパッケージを試験的に導入。全量の対応履歴を用いたVoC分析が可能になったとのことだ。また、従来は約2時間かかっていた週報の作成は、パッケージ導入により30分まで短縮できた。
堤氏は「オペレーターの作業効率化はもちろんのことだが、対応内容の要約を人に頼らずにAIで行ったことで、客観性を持ち後から深堀りできる内容を蓄積できるようになった」と導入効果を振り返った。
輸送障害の発生時などにも効果が見られたという。障害発生時にはコンタクトセンターでも混乱が発生し業務がひっ迫するが、VoC分析パッケージの導入により対応履歴を自動で集計し可視化する仕組みを構築したことで、対応業務に集中できたとのことだ。また、後からトピックごとの深堀りも可能となったことで、コールリーズン(電話をかけてきた理由)の分析にもつながった。
ELYZAの代表取締役である曽根岡侑也氏は「この両社の取り組み、生成AI時代のコンタクトセンターを象徴する一事例を作れたことに価値がある。単にAIを開発しただけではなく、現場の担当者の声を聞きながら業務にフィットさせられたことが、検証を前に進められた要因となった。将来的にはコンタクトセンターにおける問い合わせの真因特定や改善施策の仮設検討にも使えるようなAIも見据えている」と展望を示した。
ダッシュボード機能のデモを公開
説明会の中で、JR西日本カスタマーリレーションズが導入したVoC分析パッケージのデモが公開された。このシステムは、要約AIによって生成したデータに対しタグやカテゴリを付与し、ダッシュボード上で分析できるようにする機能を備える。
「概況」では、直近2週間など、特定期間の対応内容を一覧で把握できる。それぞれの対応にはタグが付けられているため、コールリーズンに応じた推移が確認可能。日付や業務分類、トピック、エリア、フリーワードなどによる絞り込みにも対応する。
「エリア分析」ではエリアごとの問い合わせ内容を一覧で提供する。JR西日本カスタマーリレーションズでは、支社ごとや路線・線区ごとの問い合わせ確認に利用しているという。
「キーワード分析」はあらかじめ設定したキーワードにひも付く分析が可能。ただし、鉄道業界では「新幹線」「みどりの窓口」「定期券」など、問い合わせ件数の多いキーワードがある程度固定されてしまうため、前週と比較して増加したワードだけを抽出して分析する機能なども備えるとのことだ。
「類似検索」では特定の問い合わせに対し、関連する問い合わせがどれだけ寄せられているかを抽出する。AIが類似する内容の問い合わせを検索し、その内容を提示する。