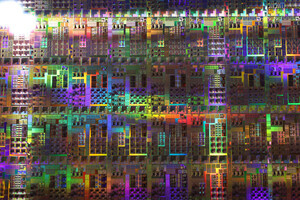自治体にもDXの波が広がっている。神奈川県藤沢市では「デジタル市役所」構想を掲げ、市を挙げて、DXに取り組んでいる。DXを推進する上で欠かすことができないのが、ノーコード/ローコード開発だと話すのは、藤沢市 企画政策部 デジタル推進室 専任主任の宇田川晟氏だ。
9月13日に開催された「TECH+セミナー ローコード/ノーコード開発 2024 Sep 自組織に適した開発基盤の実装」に同氏が登壇。同市が目指す「デジタル市役所」構想と取り組み事例について説明した。
「デジタル市役所」構想とは
藤沢市では、2021年4月にデジタル推進室を設立し、DXを進めてきた。2022年4月には、藤沢市DX推進計画や藤沢市スマートシティ基本方針を策定。2023年10月に、DXの第1弾として、コンタクトセンターを始動させた。
藤沢市が目指すのは、デジタル市役所の構築だ。
「藤沢市DX推進計画の中にはいくつか取り組み項目がありますが、一丁目一番地となっているのがデジタルプラットフォーム、デジタル市役所の構築プロジェクト事業です」(宇田川氏)
藤沢市が思い描くデジタルプラットフォームのポイントは、住民と行政のタッチポイントだという。住民はこれまで市役所に来庁して、手続きごとに各窓口を訪れていた。今後は、来庁を不要にし、1つの統一されたデジタル窓口から手続きすれば、その情報が関係部署に連携される仕組みを目指している。
「接続点をオンライン空間上で1つにして、内部の業務システムと連携しながら、職員は組織横断的に仕事をしていくというコンセプトです」(宇田川氏)
DX第1弾はコンタクトセンタープラットフォームの構築
同市がデジタルプラットフォームを構築するにあたり、まず着目したのは問い合わせ業務だ。問い合わせ業務は全庁共通の業務であり、市役所と住民がコンタクトを取りたいと思った際に、最初の入口となるため、ここから着手することにしたという。
また、問い合わせ業務には、チャネルが複数あり、それぞれの業務の流れがバラバラになっていることや、問い合わせに対するナレッジで共通のものがなく、職員の経験値・勘に依存していることといった課題もあった。
実際、職員にアンケートを取ったところ、半数以上の職員が問い合わせ業務に負担を感じていると回答したといい、この業務を変革することが大きな省力化につながると考えたと宇田川氏は説明する。
そこで、問い合わせ対応に関する一連の業務を全て「ふじさわ疑問解決プラットフォーム」で完結させる仕組みづくりを行った。これは、電話、Webフォーム、チャットなどあらゆるチャネルからの問い合わせを、コンタクトセンターのオペレーターが一次対応する仕組みだ。
オペレーターが一次対応するにあたっては、共通のナレッジベースが必要になるため、プラットフォーム上で職員が自らナレッジベースをつくれるようにした。さらに、問い合わせの対応業務とナレッジベースの作成管理を1つのプラットフォームで行う設計にしたという。これはナレッジベースを参照して対応することで、ナレッジベースを作成するメリットを感じ、作成を促進させる仕掛けだと同氏は明かした。
公共施設の予約の仕組みをリニューアル
問い合わせの業務に続いて、同市がDXに取り組んだのは、公共施設の予約受付業務だ。従来、各施設がそれぞれ、さまざまなかたちで予約を受け付けていたが、これを一元管理できるシステムにする計画である。
システム化するにあたっては、施設ごとに運用ルールがバラバラである上に、運用ルールが条例規則で決まっているため、全ての要望に沿うかたちを採ると、フルカスタマイズでしか対応できないという課題に直面した。
そこで藤沢市ではまず、ワーキンググループを立ち上げ、関係部署を集めてDXの考え方とは何か、サービスデザインとは何かを時間をかけて浸透させ、ユーザーエクスペリエンス基軸で、運用ルールをできるだけ統一していく合意形成を図ったそうだ。グループでの話し合いの結果、予約に関する大枠は統一し、細かい部分は各施設独自の運用を一部残すかたちを選択することが決まった。
従来、施設予約を希望する市民は施設ごとに来庁して予約に必要なID登録をしていたが、システム化することで、予約者のアカウントを一本化し、1つのアカウントであらゆる施設の予約がオンラインでできる仕組みとなった。また使用料の支払いについても、オンライン決済システムと連携し、キャッシュレスに対応。施設の鍵受け渡しも、スマートロックシステムと連携したそうだ。このシステムは、来年正式にリリースされる予定である。
ローコード/ノーコードツール導入のメリット
公共施設の予約システムの構築には、ローコード/ノーコードツールが利用された。宇田川氏はDXにおいてローコード/ノーコードを活用するメリットについて次のように語った。
「不確実性により、変動が大きい今の時代においては、新たな価値をどんどん生み出して、業務を抜本的に変えていかないといけません。自治体にこれまで提供されていたパッケージは、縦割りプラットフォームを前提として設計され、変化に対応しきれない、組織横断的に連携していくという考え方に即応しきれないといった課題がありました。これに対して、ローコード/ノーコードの開発は、理想と考えるDXのワークフローを短期間で実現でき、かつ、何か変化があった際も、アジリティ高く対応ができるといったメリットがあります」(宇田川氏)
加えて同氏は、システムとシステムを繋ぐことが容易にできる点やメジャーなSaaSソリューションとのAPI連携が容易である点も強みだと語った。また、職員がある程度のスキルを積めば、簡易なアプリ開発や運用・保守ができるようになり、自走できる点もメリットとして挙げた。
デジタル市役所実現は、小さな積み重ねから
最後に宇田川氏は、デジタル市役所を実現していくにあたっては組織自体が変化していくことが必要だと語った。
「組織自体も変わっていかないといけません。市役所の組織構造や人事制度に切り込んで、横の繋がりもこれまで以上に連携していく必要があるのです」(宇田川氏)
その上で重要な観点として、CoE(Center of Excellence)を確立し、ガバナンスを効かせること、職員による内製開発・運用保守が可能な体制にシフトしていくための人材育成があるという。また、各部門のニーズに応えるため、ツールの特性を鑑みた展開をすることや、プラットフォームエコシステムを創出していくことも重要だと述べた。
「DXは小さな積み重ねが重要です。小さな改善でもコツコツと積み重ねていくと、ある日気が付いたらDXと呼べる状態になっている。それが理想だと思います。変えていくのが難しい組織であっても、DXができないと諦めるのではなく、まずできることからコツコツと改善を進めていくことが非常に重要です」(宇田川氏)