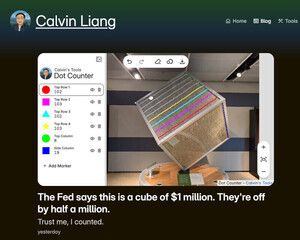Snowflakeは9月12日、年次カンファレンス「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2024」を開催した。同カンファレンスは6月に米国で開催されたカンファレンス「Snowflake Summit 2024」を起点としており、世界各地で開催されている。
Snowflake 社長執行役員 東條英俊氏は、「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2024の登録人数は5000名に達している。目玉は顧客の事例紹介で、24社が説明を行う」と語った。
エンタープライズAIを実現する「AIデータクラウド」を提供
続いて、今年2月に米SnowflakeのCEOに就任したスリダール・ラマスワミ氏が登場し、エンタープライズAI戦略について説明した。「Snowflake Summit 2024」で発表された同戦略は、AIベースのチャットボットを簡単に構築することで企業が自社のデータを活用することなどにフォーカスしている。エンタープライズAIを実現するソリューションが「AIデータクラウド」となる。
ラマスワミ氏は、「AIデータクラウド」はAI駆動のデータプラットフォームとデータ駆動のAIプラットフォームで実現すると述べた。同氏は、AIとデータプラットフォームの関係について、「AIもデータプラットフォームに変革をもたらしている。AIはガバナンスを変え、最適化を推進し、効率性を高める」と語った。
また、ラマスワミ氏は「AIは新しいビジネスモデルを生み出す可能性がある。これを実現するには、企業のデータを活用できるプラットフォームが必要。加えて、このプラットフォームでは、非構造化データ、構造化データがエンド・ツー・エンドまで使えることが求められる」と述べた。
ただし、データを活用するうえで「複雑性」「コストの制御」「セキュリティとプライバシー」という3つの課題があるため、同社はこれらの解決を支援するという。
「当社は立ち上げ時から複雑性に取り組んでいる。データを自由に移動できないと、狙った成果を出せない。われわれはデータ戦略を効率よく展開できることを最重視している。また、オーバーヘッドやよく不可能なAIコストなど、データ活用のためのインフラ管理にはコストがかかる。そこで、われわれはマネージドインフラ、シングルプラットフォームを提供する。データやAIを活用する上で、プライバシーの規制やコンプライアンスの遵守が求められる。そのためのソリューションとしてHorizonを提供している」(ラマスワミ氏)
Snowflakeだからできたスピーディーなデータ基盤構築
同社の顧客としては、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC) 執行役員 CIO、CCCMKホールディングス 取締役 撫養宏紀氏と三井住友カード 執行役員マーケティング本部 副本部長 兼 データ戦略ユニット長 白石寛樹氏が登壇した。
両社といえば、今年4月にカルチュア・コンビニエンス・クラブの「Tポイント」と、三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)の「Vポイント」が統合され、国内最大級のポイントプログラムが生まれたことが記憶に新しい。その裏では、システムやデータの統合など、さまざまな苦労があったであろう。
クロスクラウド環境におけるデータ活用
デジタルデータを取得できるポイントグラムを運営する企業は、日々データをどう活用するかに注力しているはずだ。撫養氏は、「当初からデータの力に注目しており、Tポイント開始から取り組んできた。顧客価値を向上することをテーマとしており、Tカードをモバイルにシフトして価値を提供していく」と、同社のデータ活用について説明した。
一方、白石氏は「当社はデータ活用として、データとAIを使いこなすこと、データビジネスの2つに取り組んでいる」と述べた。
Snowflake導入がもたらしたメリット
CCCはMicrosoft Azure、三井住友カードはAmazon Web Services(AWS)と両社は異なるクラウドサービスを利用していたが、Snowflakeを導入したことで、クロスクラウドによるデータ基盤を早期に実現できたという。
撫養氏はSnowflakeがもたらしたメリットとして、スピード、セキュリティ、コストを挙げた。統合プロジェクトは1年半かけて進められたが、データ連携はプロジェクトの最後までなかなか決まらなかった。しかし、Snowflakeを利用したことで、「スピード感をもってできた。その速さは画期的だった」と同氏は語った。
データ連携に必要な開発と運用のコストを減らせたことから、コストは10分の1まで削減できたという。
対する三井住友カードはもともとSnowflakeの導入を検討していたが、白石氏によると、金融にとってクラウドはハードルが高く、話が進まなかったという。しかし、「CCCがSnowflakeを使っていたことが後押しとなり、トントン拍子でデータを共有するイメージが進んだ」と、同氏は述べた。
ユーザーに支持されるサービスの提供を
データ基盤が整った今、次に取り組むべきは、両社のデータをいかに掛け合わせるかということだろう。なお、両者は個人を特定できるデータの共有は行っていないそうだ。
撫養氏は、今後の課題が「シングルIDにどんなデータをひもづけるか」だと語った。「ユーザーに支持されるサービスがあって、データが提供されるという流れを作りたい。そのために、今まではなかったサービスを作っていきたい」と語った。
白石氏は、「エンドユーザーが知らない間にデータが結び付いていることがないように、細心の注意を払っている。今後、デジタル体験を提供できる力をもっとつけて、AIドリブンなビジネスを進めて行きたい」と、今後の抱負について述べた。