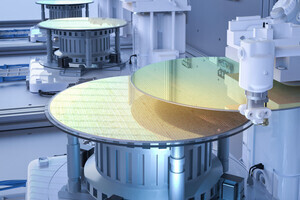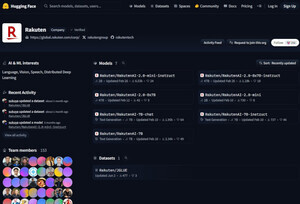ガートナージャパンは8月27日~28日、年次カンファレンス「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」を開催した。「生成AI時代の新たなコミュニケーションにチャレンジする」と題したセッションでは、ガートナー バイス プレジデント アナリスト 池田武史氏が登壇。生成AIの登場により、コミュニケーションがどう変わるのか、企業として新しいテクノロジーにどう向き合っていくべきかを解説した。
生成AIはコミュニケーションの在り方をどう変えるのか
生成AIは、人とコンピュータの関わり方を大きく変えつつある。詳細な調査や内容の要約など人手がかかっていた仕事は、生成AIを活用することで大幅に効率化している。コンピュータに指示を与えるだけでなく、コンピュータから適した指示を受けることもできようになった。
また、生成AIの影響により、これまで当たり前に行われてきた人と人とのコミュニケーションも徐々に変わり始めている。池田氏はこう講演を切り出した。
「生成AIにはまだまだのところもありますが、近い将来に実現することを想定した準備も必要です。生成AIのコミュニケーションにはさまざまなトピックがありますが、ここで考えたいのはAIと話すことをどこまで受け入れられるか、つまり、話の相手は本物の人間ではないとダメなのかというテーマです。直感的にはコンピュータと話すことに違和感があると思います。しかし、身近なところでは、コマンドやアラートを言葉で伝えることはよくありますし、防災無線などもそうです。今後、こうしたコミュニケーションはどう変わるのでしょうか」(池田氏)
その上で同氏は、人とコンピュータのコミュニケーションについて、3つの論点として「デジタルがリアルを拡張するコミュニケーションの新世界とは何か」「企業や組織におけるコミュニケーションの現状はどうなっているか」「新たなコミュニケーションへのチャレンジをどう進めるとよいか」を取り上げ、今後を展望した。
コミュニケーションが拡張された世界では、教師や医師がAIに
1つ目の論点「デジタルがリアルを拡張するコミュニケーションの新世界とは何か」では、コミュニケーションの未来像、そこでの期待と懸念を整理した。池田氏はまず、これまでの歴史を振り返った。
「人類のコミュニケーションは対面からはじまり、150年前に電話が発明されて目の前にいない人と話をすることを体験しました。私は生まれていませんが、おそらく当時は大きな衝撃だったと思います。今ではWeb会議などのユニファイドコミュニケーション(Unified Communications、UC)が普及し、映像、音声、チャットを使ったコミュニケーションに進んでいます。ただ、それもこの10年ほどの出来事にすぎません」(池田氏)
生成AIのインパクトは、音声や映像、テキストをつくり出すところにある。今後は、生成AIが、自然なテキストを生成するだけでなく、本物の人間のような姿で流暢に話をしていくことになる。ガートナーが発表しているデジタル・ワークプレース・イノベーションのハイプサイクルを見ると、生成AIのほかにも、コミュニケーションを根本から変えるさまざまなテクノロジーがあるという。
「コミュニケーションが拡張され、AIが人を助けてくれるようになります。このようにAIがアバターやリアルを拡張する一方で、AIやアバターが人間の代わりに対応するシーンも増えていくでしょう。電話を受けたら相手がAIかもしれないし、学校の先生や病院の医師がAIになるかもしれません。AI同士が対話することもありますし、マシンカスタマーと言われるように、お客さまがAIになるかもしれせん」(池田氏)
そんななか、期待されるのは「より気の利いた表現や映像の提供」「自分より知っていることが多い」「自分の能力を超えた表現ができる」などだ。一方、懸念としては「他人と似たような表現が横行する」「嘘っぽくなる、そもそも嘘をつく」「自分の感覚を勝手に解釈される」などがある。
全従業員共通のコミュニケーション手段はスマホとUC、その環境整備が必要
2つ目の論点「企業や組織におけるコミュニケーションの現状はどうなっているか」では、企業や組織が置かれている現状を整理した。
「企業や組織での中心的なコミュニケーションツールは、デバイスとしてはスマートフォン、アプリケーションとしてはUCです。スマートフォンはAndroidとiPhoneを使っています。UCツールについてはガートナーが従業員500人以上の国内企業400社を対象に行った調査では、Microsoft TeamsとZoomが多くを占めていました。使い方としては、社内外で共通のツールとして利用しているケースが最も多く、そのほかに、社外専用、ゲスト専用といった使い方もありました。複数のツールを使う理由としては、セキュリティ管理上分けたい、顧客やパートナーごとにふさわしいツールを使いたいというものでした」(池田氏)
UCツールの利用実態については、ガートナーによる別の調査もある。それによると、多くの企業が幅広く従業員に使ってもらうための環境を整備しているが、対面とのギャップに悩んでいることも分かったという。
「『全ての従業員が会議に参加できるようにライセンスを整えている』という回答が最も多かった反面、『大事な会議は対面でやるのが最もよい』という回答も多くありました。リアル会議で盛り上がって、リモートからの参加者とのコミュニケーションが希薄になるという課題も多い状況でした。逆に、『会議に向けて全社的な施策や目標がある』『満足度について定期的に調査を行っている』という回答は少なく、会議の質向上に取り組む企業が少ないことが懸念されます」(池田氏)
その上で池田氏は、企業が採るべき基本方針として「全従業員共通のコミュニケーション手段はスマホとUCであり、必要な際は、いつでもどこでも互いに連絡を取れるようにしておくことが重要」だとした。
「全ての従業員にスマートフォンを配布することが難しい企業も多いかもしれませんが、その場合は、個人所有のスマートフォンなどを利用することも検討しましょう。用途に応じてそれに特化した環境を提供していくことも必要です」(池田氏)
テクノロジーの特徴を理解し、ビジネスシーンにふさわしい選択をすることが重要
3つ目の論点「新たなコミュニケーションへのチャレンジをどう進めるとよいか」は、企業の具体的な施策となる。池田氏は、さまざまな目的にあわせて適切なツールを選定することが重要だとし、こう述べた。
「社内の情報共有や打ち合わせ、トレーニング、セミナー、共同作業などは、Web会議ソリューションなどのUCがおおむね妥当です。また、社外での会議や打ち合わせなど機密性の高い話をするときや、経営陣からの通達などに関しては、UCでもできますが、セキュリティやパフォーマンスを考慮して、他のツールをうまく使い分けすることがよいでしょう。人事面談やフィールドサポート、営業のサポート、顧客サポートなどは、CRMやSFAなどの専用ツールを使うことを推奨しています」(池田氏)
ツールを選定する際には、コミュニケーションを分類しておくことも役立つと同氏は言う。例えば、目的ベースで分類すると「提案や相談」「指示や助言」「議論や交渉」「交流や親睦」などのコミュニケーションがある。「提案や相談」は、営業や販売店などに新しいサービスや商品の紹介を行うものなどで、提案内容や要求、状況が明確な場合は、AIなどの活用シーンも広がりやすい。
「ある程度、マニュアル化されたコミュニケーションは、AIなどのテクノロジーで強化しやすく、また自動化できる可能性があります。コミュニケーションの目的はさまざまですから、AIで支援できるビジネスの場面を徹底的に調べることが求められます。もちろん、AIが直接人を相手にすることで嫌悪感が生まれるシーンも多いと思います。一部のメンバーのコンセンサスだけで安易に拡大させないよう、慎重な評価や検証が必要です」(池田氏)
最後に池田氏は次のように述べ、セッションを締めくくった。
「テクノロジーを効果的に利用するためには、その特徴を理解し、ビジネスシーンにふさわしい選択をすることが求められます。人と人とのコミュニケーションをテクノロジーでどう豊かにするのかは、まさにこれからのチャレンジです。皆さまがテクノロジーのリーダーとしてご活躍することを期待しています」(池田氏)