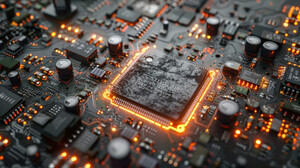世界がまさに混沌とする中をどう生き抜くか─。海外の売上比率が全体の50%強に達し、総合酒類・飲料大手として日々、内外の消費者に接するアサヒグループホールディングス。同社会長・小路明善氏は、「高付加価値循環型の経済構造」をキーワードに、「高い付加価値を持った商品やサービス・技術を追求していく」と語る。同社の今期(2024年12月期)の業績見通しは、連結純利益で1930億円、前期比17.6%増で、売上高も前期比6.5%増の2兆9500億円を見込む。今、日本は”失われた30年”から、新しい経済・産業構造への転換を図る時。国、企業、そして個人も新しい生き方を求められる時代。「企業は、高付加価値経営であげた収益を賃金引上げや、人材育成、商品開発投資に向けていく。政治はそうした経済活動を後押しするためにも、新しい社会像・国家ビジョンを示すことが必要だと思います」と小路氏は語る。世界が混沌とし、株価・為替も激しく揺れ動く中、経営のカジ取りをどう進めていくか─。
インバウンド増と裏腹に日本の課題も明白に…
東京・隅田川の吾妻橋畔に本社を構えるアサヒグループホールディングス。江戸文化や情緒を残す浅草・蔵前エリアにあり、浅草寺や東京スカイツリーなどの観光名所を訪ねるインバウンド(訪日観光客)も多い。
世界の都市にも、テムズ川(ロンドン)、セーヌ川(パリ)と有名な河川があるが、隅田川は下町情緒のある風景が人気。屋形船に乗って天ぷらを味わう外国人客もいて、吾妻橋界隈は多くの人で賑わう。
「インバウンドのお客様にも、すき焼きや天ぷらは大人気のようですし、最近はおすしも人気急上昇中だと聞いています」とアサヒグループホールディングス会長・小路明善氏は語る。
コロナ禍では、インバウンドもパッタリ途絶えていたが、昨年5月、新型コロナ感染症が〝第5類〟に移行して以来、その数は急増している。
今年は約3500万人にのぼると見られるインバウンドの経済効果は、GDP(国内総生産)レベルで20数兆円に達するという見方もある。
酷暑の続く今夏だが、街中を旅行バッグを手にして行き交うインバウンドの姿を見ると、経済面では明るい気分にさせられる。
一方で、内外の環境の変化は激しく、緊張感のある局面も出現。7月末の日本銀行の政策金利引き上げをきっかけに、為替は円高に振れ、株価も乱高下。
8月5日には、日経平均株価が4451円安で取引を終了し、過去最大の下落幅を更新したが、翌日は前日比3217円の上昇。結局、週末の8月9日には、政策金利引き上げ前の平均株価3万5000円台を取り戻しているものの、実に荒っぽい動きだ。
為替も株価も新たな調整局面に入ったということだが、近年は金融、財政両緩和で経済拡大を図ってきたということで、「一種のバブル調整期に入った」という見方は強い。
前世紀後半からだけでも、ブラックマンデー(1987年)、アジア通貨危機(1997年)、バブル経済崩壊(1990年初め)、ITバブル崩壊(2000年)、リーマンショック(2008年)とわたしたちはいくつものバブルを経験し、そしてその崩壊に苦しんできた。
円高に向かうとされる為替の調整、そして株価の調整であるが、米国の景気後退の懸念、米中対立、米国大統領選挙、ウクライナ戦争、イスラエルとイランの対立激化と先行き不透明感が強まる。
ひと頃、先吹き不透明な時代を示す『VUCA』という言葉が使われていたが、今はまさに、V(Volatility、変動)、U(Uncertainty、不安定)、C(Complexity、複雑性)、A(Ambiguity、曖昧さ)が絡み合い、世界中が混沌として、複雑な様相を呈している。
そうした中を、国はもちろん、企業も個人も、どう生き抜いていくかという命題である。
特に、日本は前世紀末からの〝失われた30年〟からの再生をどう図るかという課題を抱える。
GDP(国内総生産)でいえば、2023年に日本はドイツに抜かれ、世界3位から4位となった。
2024年の1人当たりGDPでいえば、日本は3万3138ドルで、前年の34位から38位に下落。1位のルクセンブルク(13万1384ドル)、2位のアイルランド(10万6059ドル)や3位のスイス(10万5669ドル)と比べ、なぜこうも差があるのか。
アジア勢と比べても、世界14位の台湾(7万6858ドル)、同15位の香港(7万5128ドル)、同30位の韓国(5万9330ドル)と大きな差を付けられている。為替が円高に向かえば、この格差も多少は縮まってくるであろうが、基本的には、国力低下が続く現状をどう克服していくかという課題である。
国力の基礎づくりを担うのは、その国の経済活動を支える企業であり経済人。
国際競争の中を生き抜き、従業員への賃上げや株主への配当、さらには地域自治体や国への納税の原資を生み出すのは企業活動。では、この先行き不透明な時代にあって、企業はどう動こうとしているのか─。
高付加価値型の経済構造への転換を
人口減、少子化・高齢化で内需がしぼみ、企業は成長を求め、海外市場の開拓に注力してきた。
アサヒグループホールディングスでいえば、欧州や豪州市場、さらには、近年はASEAN(東南アジア諸国連合)市場の開拓を進めてきており、約2兆8000億円に及ぶ全売上の50%強を海外市場で賄うようになった。
〝ヒト、モノ、カネ〟の経営資源の配分をグローバルな視点で見なければならないポジションになった今、小路氏はこれまでの円安をどう受け止めていたのか。
「もう当たり前のことなんですけど、お金は金利の高い所と経済成長の高い所に流れていくという大原則に従っているだけだと思うんですね」
つい最近まで、米国の政策金利が5.5%であるのに対して、日本は0.1%と金利差は大きかった。日本はデフレ経済から脱却するために、超金融緩和措置を取り、〝マイナス金利〟を実行。そのマイナス金利をようやく解除したのが今年3月。
「日本はゼロ金利が解除されて、本当にコンマ幾つの金利だと。GDPの成長も米国は2.5%位なのに対し、日本の実質成長率は0.5%位ですよね。そうしたら当然のことながら、お金はドルに流れていく」
お金は金利が高く、経済成長率の高い所に流れていく経済原則に則って、近年はドル高・円安が続いていたということ。そのトレンドが今、変わろうとしている。
日本では、多くの経済人が〝失われた30年〟、つまり30年続いたデフレからの脱却を目指して動いてきた。大事なのは、脱デフレを果たした後の日本の経済構造をどのような姿にするのかということである。
そこで、小路氏は、「高付加価値型の経済構造への転換」が必要との認識を示す。
先行き不透明感が高まり、企業を取り巻く環境がどう変わろうとも、その中を生き抜くレジリエンス(耐性)を高めるためにも、高付加価値型の企業経営を追求するということでもある。
『経営は人なり』の原点に立ち返って
小路氏は1951年(昭和26年)11月生まれ。1975年(昭和50年)アサヒビール(現アサヒグループホールディングス)に入社。80年前後、同社の業績は低迷。小路氏は1980年に労働組合専従となり、書記長なども務めた。労働組合時代には、人員削減などの悲哀を味わう経験をし、「2度とああしたことは体験したくない」という思いが強い。
87年に同社は画期的な新商品『スーパードライ』を世に送り出し、業績を好転させ、ビール業界で首位の座をつかんだ。
その後、小路氏は人事戦略担当、執行役員、取締役などを経て、2016年アサヒグループホールディングス社長に就任。最高経営責任者(CEO)になり、2021年会長に就任という足取り。
この間、同社はニッカウヰスキーやカルピスなどを合併し、総合飲料化を進め、海外企業のM&A(合併・買収)を実行し、グローバル化を推し進めた。
「買収先から学ぶことも多い」(小路氏)という対話路線で、同社を、日本を代表する酒類・飲料会社に育て上げた。
現在、小路氏は経団連(日本経済団体連合会)の副会長を務め、『教育・大学改革推進委員会』では、橋本雅博氏(住友生命会長)と共に共同委員長を務める。また、『労働法規委員会』では冨田哲郎氏(JR東日本前会長・現相談役)、芳井敬一氏(大和ハウス工業社長)と共同代表を務め、新しい生き方・働き方を探っている。
経営は人なり─。「人の成長が企業の成長になり、企業の成長が国の成長となる」というのが小路氏の持論。
国力の基礎づくりを担うのは民間経済。その民間経済を担うのは『人』であるということ。
小路氏が『人』をキーワードに思考し、議論を進めるのも、会社で人事・経営戦略畑を経験し、経団連などで、『教育・大学改革』、『労働法規』委員長を務めて、人づくりや生き方・働き方はどうあるべきかを思索してきた氏のキャリアとも関係があってのことだと思う。
では具体的に、日本の国力をどう掘り起こしていくか─。
『量』を追う経済から『価値と質』の経済へ
「端的に言えば、高付加価値型の経済構造、これをつくっていかなければいけないと思うんですね。高い付加価値を持った商品やサービスだとか、さまざまな技術を市場に投入していくことが大事だと」
高い技術に裏打ちされた商品やサービスを市場に投入し、それにふさわしい価格を付けていくことは日本産業界の重要課題の一つ。
現実には、価格競争から抜け出せない企業もあり、〝値付け〟は相当に難しい問題。そうした現状を踏まえて、小路氏が語る。
「高い技術によって、それにふさわしい価格を付けて、収益を上げる。その収益で賃金を引き上げ、人への投資とか商品開発への投資を進めていく。それからM&Aを含めた成長投資だとか、そういった所に資金を振り向けて、さらに高付加価値商品や事業を生み出していくと。これが高付加価値循環型経済ということです」
これまで、日本はGDP(国内総生産)のボリューム(量)を追うという〝規模の経済〟でやってきた。
それを、「価値と質の経済に転換して、高付加価値型経済構造というものをつくることが、脱デフレの第一歩になる」と小路氏がさらに続ける。
「もっと言えば、付加価値の高いものには、それなりの値段が付きます。ディマンドプル(需要創造)型のインフレ経済構造であり、付加価値への需要を増やし、その需要によってインフレを起こし、収益を取るということなんですね。このディマンドプル型の経済構造に転換して、これが継続していけば、デフレからの脱却ができると」
コストカット型から需要創造型の経営へ
〝失われた30年〟は需要創造型経済ではなく、コストカット型の経済であり、何とか利益を絞り出すものの、賃金はずっと横バイが続いた。従って、GDPの6割を占める個人消費も低迷し続け、企業は企業でさらなるコストカットに努め、低価格競争で生き延びようとしてきた。
今は時代の転換期。国富を創造する経済人の役割は重い。
「大事なことは、政府も経済界もデフレの後、どういう経済構造を日本でつくるんだと。これをやはり国民に示さなければいけない。そうすると国民も付加価値が高い経済構造とは何かを考え、理解を深めていくと思います。これは企業、自営業、フリーランスを含めてそうですし、農家もそうです。高いお米を作って消費者に提供する。それが自分たちの生活改善につながり、ご自身への還元につながってくると。こういうふうに国民は理解するんですね」
新しいステージの経済構造を構築していく上で、適正価格をどう実現していくかも課題。
「はい、値上げがあった後はどうなっていくんだと。その循環を見せないといけないんだと思うんですね。それが政府も言うように、人への投資につながる。分配と成長の循環論だけでは駄目なんです。要は、どういう成長をするのかということ。それは高付加価値循環型の成長でないと駄目だと。安いものでボリュームを追って成長していくのか。そうしたら、またデフレに戻ってしまいます。そういう事をきっちり示していかないといけないということが一つ言えると思うんですね」
今はまさに新しい経済構造をつくる転換点。こうした転換期には、改革・変革への反動が起きる。また、昨今の異常気象・自然災害の多発も加わって、未経験の出来事も起こり得る。
そうしたショックが起こる中での課題解決策である。
日本の企業数は約360万社。うち99%強は中小企業が占める。日本の全雇用の7割を中小企業が引き受けており、中小企業の生産性向上がなければ、日本全体の活性化は実現しない。
「中小企業もやはり、人材と、人材が生み出す技術が成長に不可欠。デジタル化、AI(人工知能)の活用も含めて、オンリーワンの技術をどうつくっていくかが大事。このオンリーワン技術というのは、企業規模の大小とは関係ないです。中小企業も光る技術を持っていれば、強さを発揮できます」と小路氏。
自助・共助・公助で
国力アップには、生き方・働き方改革が密接に関係してくる。
人口減、少子化・高齢化という流れの中で、『70歳定年』を導入する企業も登場してきた。また、70歳を過ぎて心身共に健常な民間人が、例えば、『中高一貫校』の校長に就任するというケースも見られる。
「生涯学習、生涯の学びというのを日本文化の一つにするというのが非常に重要なこと。生きるモチベーションにつながっていきますからね」
日本には古来、『自助・共助・公助』という生き方がある。
「ええ、日本は海外みたいに一定年齢に達したら、リタイアして、後はもう自分の生活を謳歌するだけというのとは違いますからね。その自助・共助・公助の精神というのは社会の隅々にあるんですね。だから歳を取っても、共助の精神でどこかの塾から教えてくれと言われたら、みんな喜んで行くんですよ」
小路氏がさらに続ける。
「うちの社員に聞いても、技術畑の出身者が小学校から頼まれて、喜んで出向いていますね。(グループ会社の)カルピスも出前授業をやっていますしね。やはり子どもたちもキャリア教育と言って、校舎の中だけで学ぶのではなくて、社会に触れさせることが大事だと思いますね」
イノベーションと人づくりの関係
「これは、ドイツ語学者の橋本文夫さんが話されたことで、何年か前にその話の内容に触れて感動させられたことがあります。教育というのは、小さな完成された器の人間をつくることではなく、大きな器の未完成の人間をつくることであると。小学校教育からマナーを学ばせることはもちろんいいんですけど、やはりあれをやっては駄目、これをやっては駄目だと。それから1+1は2だよという答えを常に教えて、そういう計算式だとか、決まりきった答えを導き出すという教えの教育なんです」
こぢんまりとした頭のいい子ができる教育─。その結果、小学・中学教育を終えた15歳の日本の子どもたちの数学、国語、化学に関するリテラシーは世界トップクラスだといわれるが、小利口な小さな器の人間になる教育になっていやしないかという小路氏の危惧である。
ドイツ語学者で教育論を論じていた橋本文夫氏(1909―1983、旧東京帝国大学文学部卒、中央大学名誉教授)の考え方に共鳴したと小路氏は語る。
「その大きな器の人間がたくさん競い合って、そこからイノベーション(革新)が生まれる多様性のある社会、同質の社会より多様性のある社会ができていくと思うんですね」
企業人の不断のイノベーションが経済を変動させ、発展させていくというヨーゼフ・A・シュンペーター(1883―1950、経済学者)の創造的破壊論を引き合いに、「大きな器の人間が議論し、ぶつかり合って、意見を出し合って、あるものを創り出していく。そういう日本社会になったら、日本の器も大きくなると思います」と小路氏は語る。
未来は待つものでなくわれわれがつくるもの
今、将来への懸念、先行きが読めないという不安が国民、特に若い世代の間で強い。
「ええ、自分たちの子ども、10代、20代の若い世代が日本の将来はどうなっていくのか全く分からないと。日本の将来に対する不安が高まっていますね」
こうした将来不安が高まる一つの理由として、小路氏は、「日本の将来をどうしていくかという国家ビジョンを示せない政治への不満と不信、期待のなさが国民の間にありますね」と語る。
では、どうすべきか?
「やはり国家ビジョンというものを今、示していかないといけない」と小路氏は語り、「本来、政治は国の行く末を決める前輪で、経済が後輪である」という認識を示す。
前輪と後輪の両輪がうまく回転していかないと、日本再生はもちろんのこと、混沌たる国際状況の中で、日本の基本軸、立ち位置も定まらないことになる。
「日本の行く末を、日本をどういう国にしていくのか。日本社会はどういう社会を目指していくのか。それから人々の生活・生き方はどうなるのか」という小路氏の問題意識である。
人口減、少子化・高齢化の流れの中で、生産年齢人口(15歳から64歳まで)は、2040年には今年(2024年)と比べ約1160万人減少し、全人口の55.1%にまで下落する見通し。
産業界での労働力不足は深刻で、中でも高齢化が進むことで医療・福祉の分野での人手不足はさらに深刻だ。2040年時点で、医療福祉分野で就業が必要とされる人数は約1070万人(総就業者数の約20%)。これに対して、確保できる見込数は約974万人で、今から約100万人の人手不足が懸念されている。
「2040年に向かって、そういう静かなる危機が押し寄せてきていると。ただ、わたしはどちらかというと、危機意識を持つことより、そういう問題を踏まえつつ、未来は待つものではなくて、未来はわれわれがつくるものだと。そういう気持ちで日本の未来をつくっていかなければいけないと思っています」
未来は待つものではなく、われわれがつくるもの─。政治(前輪)と経済(後輪)それぞれの使命と役割を果たす時である。