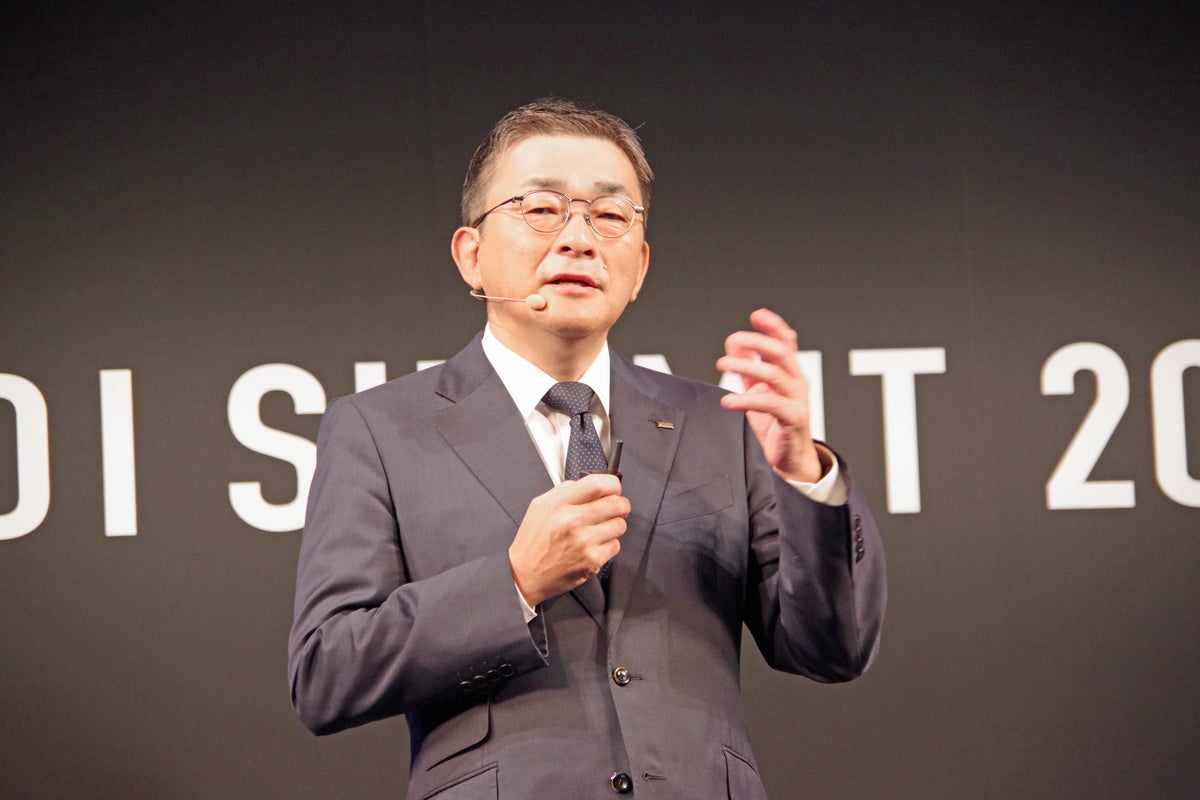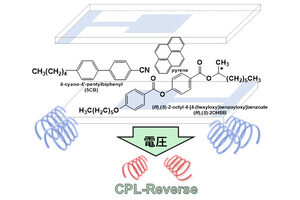KDDIは9月3日・4日、最新のテクノロジーや共創事例を紹介するイベント「KDDI SUMMIT 2024」を虎ノ門ヒルズ 森タワー(東京都 港区)およびオンライン配信のハイブリッド形式で開催した。オープニングセッションで、KDDI 代表取締役社長 CEOの髙橋誠氏とOpenAI Japan 代表執行役員社長に就任した長崎忠雄氏が「OpenAIが日本法人を立ち上げた経緯」や「コンビニと通信業界の共通点」などに関する話題を繰り広げた。以下、対談の内容を紹介する。
日本のAI活用の可能性
髙橋氏:長崎さんといえばAWS(Amazon Web Services)代表のイメージが強いです。あれほど大きく成長した会社から、現在はOpenAIに移られましたが、どのような心境でしたか。
長崎氏:私がAWS(前身のアマゾンデータサービスジャパン)に入った2011年には、クラウドという言葉も世の中にはありませんでした。入社から今年3月に退任するまでに私がやったことは、ITの民主化です。今でこそクラウドは当たり前に使われていますが、出始めた当初は革新的だと感じました。クラウドにより、誰もがITを使いこなすことが可能になり、あらゆるイノベーションにつながると思いました。
現在のAIもこれと似たような感覚があります。AIの民主化や、AIを正しく使って正しい成果を出す、ということのお手伝いをしたいというのが、OpenAIに移った大きなきっかけです。
髙橋氏:以前、大きな企業や金融業界などでは「クラウドは危ないぞ」という風潮がありました。
長崎氏:当時のアマゾンはネット上の本屋さんとして有名だったので、そもそもクラウドが何かといった話を毎日のように説明していました。そうした活動の中で、クラウドはソフトウェアの市場を大きく広げたことを実感しました。ソフトウェア開発の裾野が広がったことで、イノベーティブなスタートアップがたくさん出てきました。
AIは、このソフトウェアの裾野をさらに拡大するはずです。まだ見ぬスタートアップがこれから生まれるでしょう。AIがこれまでと決定的に違うのは、サービスというもののあり方を変える可能性があるということです。
私たちが日々生活する中でさまざまなサービスを受けますが、そのサービスをがらっと大きく変えてしまうと思います。AIが社会に与えるインパクトやスケールに私も何か貢献したいと思ったのが、2つ目のきっかけです。
髙橋氏:AWSの初期はスタートアップ支援のイベントを頻繁に開催していましたね。ほぼ無料のような料金体系で提供しており、多くのスタートアップがAWSを利用しました。そのような環境を作り上げたのが素晴らしかったです。目下、AIも同様の環境を作って付加価値を乗せられるプレイヤーを増やすことが大事ですね。
長崎氏:OpenAIの話になりますが、生成AIは新しい旗艦モデルを発表するたびにコストが大幅に下がっています。しかし、パフォーマンスは数倍向上しています。つまり、お客様は常に最新のモデルを使わなければ損なんです。
髙橋氏:どんどん活用して、いかに新しいサービスを残すかの方が大事かもしれませんね。
長崎氏:AIはまだまだ始まったばかりで、私はDay0(デイゼロ)だと思っています。インターネットが生まれたのは1960年代だったと思いますが、商用化されたのはそれから60年ほど後です。PCも開発されてから一般の人が使えるようになるまで50年ほどかかっています。ChatGPTはこれが数年で実現しています。このスピード感はわれわれが今まで経験したことがないものです。
髙橋氏:OpenAIには、20年前にGoogleやFacebookを見たときのようなわくわく感があります。これからがすごく楽しみです。その中で、なぜOpenAIは最初の海外拠点として日本を選んだのでしょうか。
長崎氏:多くのお客様から同じ質問をされます。皆様にはもっと自信を持ってほしいのですが、日本は世界4位の経済大国ですし、Fortune500というくくりでは第3位です。イノベーションや新しい技術に対して貪欲でもあります。そういう意味でも、AIに対するマーケットと可能性が日本にはあります。
さらに、日本は少子高齢化や地方衰退など、世界がこれから解決すべき課題にまっさきに向かっていきます。ソーシャルインパクトの観点から、日本とAIは相性が良いです。サム・アルトマンが世界を回って各国首脳らと対談する中でも、日本が抱える社会課題に対しAIが貢献できると考えたようです。
髙橋氏:私が投資家の方などと話をすると、「ESG経営が大事」「サステナビリティ経営が大事」などと言われます。これと、スタートアップが「AIを使ってミッションドリブンでソーシャルインパクトの大きなことをやろうよ」を掲げるのは同義だと感じます。
長崎氏:OpenAIに入って4カ月くらい経ちましたが、この会社のインパクトの大きさを実感しています。レベニューや数字よりも、AIを活用して正しく社会にインパクトを与えていることが、ミッションドリブンに通じています。チームの一体感や情熱が成長ドライバーになっていることを感じますね。大きなチャンスだと思います。
長崎氏が予測する今後のAIトレンド
髙橋氏:話は変わりますが、OpenAIはなんとなくベールに包まれている感じがします。Microsoftに話を通さないとOpenAIにたどり着けないイメージがあります。このあたりはいかがでしょうか。
長崎氏:ベールに包まれているというのは、まさにその通りだと思います。だからこそ私たちは日本に法人を作って、皆様と対話をする窓口を開きました。残念ながらWebサイトはまだ英語ですし、改善すべき点は多いです。
Microsoftとは素晴らしいパートナーシップがあり、Microsoftのおかげで当社はモデルを開発できているのは事実です。しかし、当社はChatGPTという独自のサービスを開発していますし、われわれ自身でサービスをお客様に届けています。
重要なのは、AIが正しく使われ、正しく世の中にインパクトを与えるということです。Microsoftは素晴らしいパートナーですが、当社はモデルを作っているメーカーとしての社会的責任がありますので、きっちりと企業や政府と対話をしたいと思っています。そのために法人を作り、顔が見えるようにしました。
髙橋氏:Office365とChatGPTのパートナーシップはもちろん素晴らしいですが、それとは別にOpenAIのAIをダイレクトに活用するための窓口があり、しかもその日本法人が立ち上がったということですね。
長崎氏:まさにその通りです。ただ、今まで日本語で情報を発信していませんでした。私たちはAIの会社で常にAIのことを考えているのですが、AIを活用してトランスフォーメーションを起こしたい日本のお客様にわれわれの知見をご提示して支援したいです。
髙橋氏:以前OpenAIの日本オフィスにお邪魔したことがあるのですが、海外のスタッフで日本のことが大好きな方がたくさんいることが印象的でした。日本が好きで日本の良い点を理解していて、日本らしいバリューを作りたいという思いをすごく感じました。
長崎氏:はい。日本に対する興味や日本の可能性を感じてくれているようです。ChatGPTのようなLLMは、言語を超えられます。これまで英語と日本語で言語の壁があったのですが、これを無くせます。私は英語もそこそこ話せますが、生成AIのおかげで日常のやりとりはすべて日本語で対応できています。
社内には海外から日本に来てサポートしてくれているメンバーがたくさんいますが、例えば居酒屋に行くと、メニューを写真に撮って英語に翻訳して注文しています。もはや私が英語で説明する必要がありません。この手法は、日本人が海外旅行に行く際にも同じように使えるでしょう。生成AIはどんどんマルチモーダル化していますので、人間の通訳をデバイスで代替できる日がいずれ訪れそうです。
髙橋氏:デバイスでもAIを活用できる未来は楽しみです。AIは消費電力の大きさが問題とされる場合もありますが、今後はエッジやオンデバイスでの省電力なAIもどんどん開発されそうです。このあたりのトレンドはどう読んでいますか。
長崎氏:正直なところ、まだ答えは出ていないと思います。AIはまだ始まったばかりです。当社はフロンティアモデルをひたすら改善して、より使い勝手の良いものを目指しています。当社はLLMのナレッジと経験がありますので、引き続きここに投資していきます。
ただし、コネクテッドカーやIoTなどが普及すると、エッジ側でも十分にパワーを発揮するAIが求められるようになるはずです。エッジやオンデバイスのAIは閉じられた環境ですので非常にセキュアですが、できることは限られます。一方で、大は小を兼ねるようなAIの使われ方がするかもしれません。このバランスはこれからお客様との対話を通じて適切なユースケースを生み出していく必要がありそうです。
髙橋氏:今後はAIの使い方もハイブリッドになり、そのバランスをどうするのかを考えていく必要がありますね。ただ「電力が足りない」と大きな声で言うだけでなく、当然技術者も問題を改善してきますし、今後が楽しみです。
長崎氏:歴史を見ると、テクノロジーとはイノベーションの連続です。現在は電力消費がAIの課題とされていますが、数年以内に想像以上のイノベーションが生まれるはずです。むしろ、イノベーションが生まれないとAIの進化がどこかで頭打ちになってしまうでしょう。