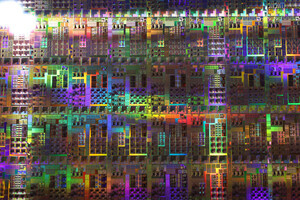ガートナージャパンは8月27日~28日、年次カンファレンス「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」を開催した。同カンファレンスでは働き方改革を推進する企業担当者や専門家、ガートナー アナリストなどが登壇。その中から本稿では、第一三共 DX企画部長の上杉康夫氏による「第一三共におけるDX推進の鍵となる人材育成」の内容を抜粋してお届けする。
変革期真っただ中にある現在
上杉氏は冒頭、DXや人材育成を推進するにあたり「重要となるキーワードは多様性」だと切り出した。第一三共の中期経営計画では製品、ステークホルダーに関する4つの柱が掲げられており、それを支える基盤として「DX推進によるデータ駆動型経営の実現と先進デジタル技術による全社の変革」がある。計画の第5期目に入った現在の状況について、同氏は「製品構成、事業規模が変化する、まさに変革期にあると感じている」と言う。
先進デジタル技術活用の具体例として挙げられたのは、AIだ。同社では2018年頃からデータ駆動型の創薬プロジェクトを開始。コールセンターへのAI実装も進めるなど、特定の領域でのAI活用に取り組んだ。2020年にはAIや機械学習の専門組織を立ち上げ全社での活用拡大をスタートし、2022年には画像AIの分野を強化すべく、エルピクセル社と包括提携を締結。2023年にはチャット型自社生成AIを導入するなど、取り組みを拡大させてきた。今後はコモディティ化した技術の積極活用とさらなる新技術導入を目指すという。特定の領域での活用から、社内の専門組織による推進や他の企業との協働により、活用範囲が拡大していく中で、今後重要になるのが「リテラシー向上やDX人材の育成」だと上杉氏は話す。
まずはトップ同士で課題を抽出
では、第一三共ではどのようにDX人材の育成を進めたのか。同社は2020年、デジタルやセキュリティに関する組織を一元化した「グローバルDX」を立ち上げている。
「DX人材を育成するために、まずは、グローバルDXのトップと、各組織のトップとの相互理解、連携を進めました」(上杉氏)
その過程で出てきたのは、「データ利活用」「コミュニケーション・コラボレーション」「人材の確保・育成」という3つの課題である。当初、業務組織においては、DXを担える人材が不足しており、DXを推進する立場にあるグローバルDXとのコラボレーションも限定的だった。また、当のグローバルDXも人材が不足しているような状態だったという。
ターゲットごとに設定した3つのプログラム
そこで同社では、それぞれの組織が自律的なDX推進を行える状態を目指し、人材育成をするためのプログラムを用意した。
人材育成のプログラムは、「組織独自の高度専門プログラム」「組織ニーズに応じたプログラム」「全社向けのITリテラシー向上プログラム」の3つから成る。
高度専門プログラムとしては、前述の創薬プロジェクトにおける、研究現場主導のAI活用のように、業務の専門性に応じたスキルの獲得などの例がある。また、データサイエンティスト育成のため、社外の育成プログラムに人材を拠出する取り組みにも力を入れた。
「高度な専門性を持つ人材の育成は、各組織から始まりました」(上杉氏)
組織ニーズに応じたプログラムの策定にあたり、グローバルDXはまず、社内の30ほどの組織と話し合いの場を設け、どんなDXが実現したいのか、そのためにどのような人材が必要なのかを可視化していくところからスタートした。しかし、「具体的な人材像は分からない」と言われることが多かったことから、上杉氏らはまず、デジタルスキル標準による人材類型を基に、DX推進リーダー、DX案件リーダー、DX案件担当者、データ活用リーダー、データ分析者という5つの人材群を用意。それぞれどのようなスキルが、どのようなレベル感で必要なのかを、ビジネススキル(ビジネススキル、DX推進スキル)、Techスキル(デジタルスキル、データ分析スキル)の4軸で可視化したそうだ。
これらをベースに、例えばDX推進スキルがレベル2の人材向けにはプロジェクト入門やDXトレンド、レベル3の場合はデザイン思考入門、Techスキルにおけるデジタルスキルがレベル2の場合は、AIリテラシー、RPA開発初級といったプログラムを用意。各組織が求める人物像に合わせて選択し、自律的に人材育成を進めるかたちを採った。
「2年ほどかかってようやく、社内の全てに近い組織でこういったプログラムを設定することができました」(上杉氏)
ITリテラシー向上プログラムについて、上杉氏は「人事と連携していくことが非常に重要」とした上で、人事部で用意している一般的な研修の中にデータ分析などの基礎的なスキル研修を組み込んでもらうようにしたと話す。また、Di-Liteを参考に学習プログラムを用意、資格取得受験の費用負担などの整備をしたそうだ。
「2023年度のITパスポート試験では、500名分の費用負担が可能な予算を用意しましたが、実際には2000人ほどの応募がありました。リテラシー向上のポイントになると感じたのは、本部長レベルの方も試験にチャレンジし、『なかなか難しかったけども、合格しました』と話してくださったことです。このような声が現場に広がっていけば、DXを推進する機運も高まっていくと思っています」(上杉氏)
DX推進に欠かせない風土醸成の取り組みとは
人材育成のプログラム整備とともに、風土醸成を進めるための取り組みも進めることにした。これは「底上げ」「DX機運向上」「トップコミットメント 」の3層から成る。
底上げについて上杉氏は「万人がデジタルに興味があるわけではない」と述べた上で、グローバルDX側で仕事に役立つガジェットやツールの紹介、パワーポイントの使い方などのTIPSを短尺動画で配信する取り組みを紹介した。2年間で約40本の動画を公開しており、コンテンツ満足度93%と評判も上々だという。
DX機運向上のため、社内オンラインセミナーの開催や社外ポータルの活用も行っているが、同氏が特に重視していると語るのは、社員を巻き込んだ取り組みである。Hubを利用したアイデアの共有に加え、生成AIやメタバースをテーマにしたアイディエーションワークショップの開催なども行っている。そこで出たアイデアを早期に実現することで、「アイデアがかたちになることを知ってもらい、さらに機運を高められる」とその意図を示した。
最後に上杉氏は「テクノロジーは日々進化して変わってきているので、人材育成プログラムについては常にアップデートが必要」だと述べ上で、改めて多様性について言及した。
「多様な人材に寄り添う、多様な興味を奮い立たせる、多様な施策でニーズに応じる。(人材育成を進める上では)多様性が極めて重要です」(上杉氏)