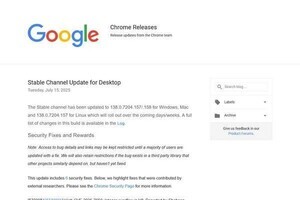SAPのERP製品「SAP ERP 6.0」の標準サポートが2027年に終了するという「SAPの2027年問題」が注目される中、TECH+ではこの問題に焦点をあてた「TECH+セミナー ERP 2024 Jul. 自社に適したERP実現へ」を7月10日にオンラインで開催した。
本セミナーでは、SAP ERPのシステムサービスを提供するソフテスの会長である鈴木忠雄氏が「経営革新 SAP ERPとDX 『データとデジタル技術の活用』」と題し、講演を行った。
SAP ERPとは
まず鈴木氏は、同社が扱っているSAP ERPの概要を説明した。
SAP ERPは統合基幹業務システムで、販売管理、在庫購買管理、生産管理、財務会計、管理会計を網羅している。業種、業態を問わず使える点やプログラミングを必要とせず、パラメーター設定だけでカスタマイズできる点、各基幹業務機能が1つのシステムとして構築されている点が特長だという。
各基幹業務機能が1つのシステムとして構築されているメリットは、業務機能間の誤差が生じない点だと鈴木氏は説明する。業務機能間の誤差とは、例えば、購買ではある部品がなくなったため注文を出しているが、生産現場では注文を出しているのかどうか分からず、その部品が欠品しているという情報だけを持っているといったことだ。SAP ERPの場合、機能間でこのようなタイムラグがないという強みがある。
一方で、1つのシステムとして構築されているからこその注意点もある。
「SAPは一つ一つの機能が全部連結していて、一つの世界として動いているというところが特長ですが、それを連携させて、適切に設定しないとうまく動かない、あるいは欠落が生じてしまうことがあるので、注意深く全体のビジネスモデル、ビジネスプロセスを反映させていかないと、うまく使えないということが起こります」(鈴木氏)
在るべきDXの姿とは
続いて、鈴木氏はDXについて触れた。
経済産業省は、「DXリテラシー標準(概要編)」の中で、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。
同氏は、この中の重要な部分は、デジタル技術を使うだけではなく、データを活用するところだと述べた。
データを活用したDXの成功例として鈴木氏が挙げたのは、気象予測だ。
「気象観測というのは、気象衛星あるいは地球上のいろいろな地点でのデータが綿密に取られており、データがどんどん蓄積されています。そのデータを使った長期予報や短期予報、あるいは台風の進路予測、海水温の予測などの精度が上がってきました。つまり、データやデジタル技術を活用して成果を出していくのが、一つのDXの姿ではないでしょうか」(鈴木氏)
また同氏は、データとデジタル技術の活用のモデルケースとして、無人決済コンビニを挙げた。
無人決済コンビニでは、カメラやセンサーを使って、顧客がどの商品を何個ピッキングしたかを把握、自動でクレジットカードから商品代金を決済する。また、在庫量や商品の供給必要量も自動的に把握できる。
そのほか、企業の役員会も、事業部長や部長が実績を説明するのではなく、リアルタイムの実績や今後の予測をモニターに表示しながら行えば、より早く、明確で正しい意思決定が行えるようになる。
「データとデジタル技術によって、このようなことが可能になるのです」(鈴木氏)
業務システムが持つ4つの課題
鈴木氏が次に触れたのが、業務システムの課題についてだ。同氏は4つの課題を指摘した。
1つ目は、業務システムが経営トップの意思(経営ビジョン)を反映した仕様になっていないという点だ。例えば、経営者は意思を持っているが、それが現場の人に届いていない場合、システムをつくるのは現場の人たちが中心になるので、経営ビジョンが反映されていないということが起こり得る。
2つ目は、必要な業務機能が網羅されていないという、システムの不完全さの課題だ。要件定義の際にユーザーからニーズを聞いた上でシステムをつくっていくが、そのシステムの中に全ての機能が網羅されていない、イレギュラーが発生した場合の処理がカバーされていないなど、業務機能の不完全さというのは「よくある」と鈴木氏は話す。
3つ目は、周辺業務機能の不足という課題だ。例えば、購買において多くの企業から見積もりをとって、一番安いところ、納期が確かなところに発注したいが、その情報は購買管理に使用しているものとは別のシステムを用いて探さなければいけない。あるいは、販売管理において、過去の経歴など顧客のデータベースを把握し、より細かなデータ分析をしたいが、そのためにはメインシステム内の情報だけでは足りず、外付けのシステムが持つ情報がさらに必要になるといったように、業務システムには周辺機能の不足という問題が散見される。
4つ目の課題は、ユーザーやマネージャー、経営者がSAPに蓄積されている関連データを使いこなすためのスキルがないという点だ。
原価がどういうふうに変化して、何が原因で原価が高くなっているのか。あるいはどのような顧客からの売上や収益性が高いのか、商品ごとの収益性はどうなっているのか。こういったことを各担当者が把握できておらず、システムで管理ができていないのではないかと同氏は疑問を投げかけた。
「ユーザダイレクト方式」によるシステム構築
ではこれらの課題を解消するためには、どのような方法を採るべきなのか。ソフテスがシステムの構築の際に採用しているのが、「ユーザダイレクト方式」である。これは同社独自の名称で、ビジネスデザインからスタートし、4段階のステップを踏んで最終的に稼働させるプロトタイピングによるシステム構築だという。
具体的には、最初におおよその業務を把握した上でプロトモデルを構築する。それをユーザーと一緒にオペレーションし、機能の不足、適切さなどを検証。直した方が良い部分があれば修正して、もう一度、業務の把握・プロトモデル構築から始める。こうしてできた2次プロトモデルを再度検証して直すというサイクルを何度か回し、最終的なかたちとしていくやり方だ。
この方式では、ユーザーとコンサルタントが直接コミュニケーションをとり、業務課題とシステム仕様を協議しながら一つずつ要件を定義し、仮運用をしていく。そのため、全ての業務プロセスを見直すことができ、「仕様が抜け落ちるようなこともない」と鈴木氏は言う。
「ユーザーの望む内容、あるいは新しい内容も織り込め、何度も何度もシステムに触るので、システムの品質も上がります。さらに本稼働したときには、全ての検証が終わっているので、何の問題もなく本稼働に移ることができます」(鈴木氏)
ユーザダイレクト方式で最初に行うステップのビジネスデザインとは何か。まず鈴木氏は現状の問題点に対策をしていく方式を採る場合、出来上がるものは「今のものとそれほど変わらないものになってしまう」と述べた。だが、経営者が求めるものはそうではない。本来は毎年課題を達成し、理想とする経営ビジョンを実現すべきなのだ。ここで描かれるプロセスこそ、ビジネスデザインである。
ビジネスデザインをすることで、業務課題が浮き彫りになり、それに対応するために業務プロセスや仕事のプロセスを新たにつくる必要が発生する。それがシステムデザインにつながっていくと同氏はまとめた。
鈴木氏はユーザダイレクト方式により、経営課題を反映したシステム仕様にすることができ、プロセスの検討・検証によって完成度の高いシステムが出来上がる。さらに、プロジェクトの過程でユーザーを参画させることにより、スキルを習得させることも可能だとし、この方式のメリットを強調した。