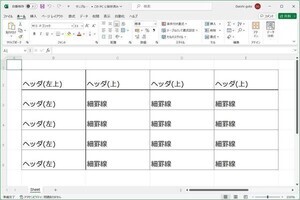「生成AI(人工知能)がもたらすインパクトは、短期的にも中長期的にも極めて大きい。事業機会を最大限獲得することが大切だ」
日立製作所社長兼CEO(最高経営責任者)の小島啓二氏はこう語る。
近年、日立は多様な機器を通信でつないで管理を効率化し、法人のデジタル変革(DX)を支援する基盤『Lumada(ルマーダ)』の普及に注力してきた。生成AIはルマーダの中核技術と位置付け、エンジニアや現場労働者の生産性向上に活用する。ソフトウエア技術者の不足の解消につなげたり、鉄道や原子力などにおける保守サービスの改善を図ったりする構想だ。
こうした青写真の実現に向けて、25年3月期は生成AIに3千億円を投資し、人材育成やデータセンター(DC)整備、研究開発などに充てる。28年3月期をめどに生成AIの専門家を5万人規模で確保する計画。21年に傘下に収めた米IT企業グローバルロジックが保有する技術や教育手法など、過去のM&A(合併・買収)の果実も生かせると見込む。
だが、生成AIを巡る国際競争は激化の一途を辿っており、日立が順調に存在感を高めていけるかは未知数とも言える。
米マイクロソフトは4月、日本事業に2年間で4400億円ほどを投資すると発表。米アマゾンウェブサービス(AWS)は27年までの5年間で2兆2千億円余り、米オラクルは24年からの10年間で1兆2千億円以上を投じる計画を示している。各社は日本のDCでAI向けの画像処理半導体(GPU)導入などを進めていく計画だ。
「現状に満足せず、アグレッシブに価値創造を続けられる企業でありたい」と語る小島氏。
1月に10兆円台だった日立の時価総額は6月中旬時点で16兆円近くに達した。日立の戦略自体は株式市場から評価を得ていると考えられるが、事業規模が海外のIT大手に見劣りする感は否めない。きめ細かい顧客対応で収益向上につなげられるか、今後の取り組みの実効性が問われる。