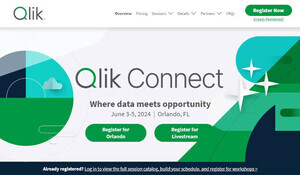クリックテック・ジャパンは6月19日、オンラインでメディア向けに「ビジネスにおけるSAPデータ活用のメリット」と題した説明会を開催し、同社 データ戦略コンサルタントの木口亨氏が説明した。
情報活用の変遷にみるビジネス環境の変化
まず、木口氏は情報活用の変遷にみるビジネス環境の変化について「経営者の意思決定を支援するための実績データだけを活用したMIS(Management Information System)による情報活用が1970年代にスタートし、企業情報活用を目指して管理部門に展開、そして2000年を境にBI(ビジネスインテリジェンス)というツールや考え方の登場により、実務部門によって活用されてきた。スタートは経営支援のための道具だった」と説明した。
こうした歴史的経緯をふまえ、経営者の意思決定支援自体は進化したのかと言えば、BIが浸透していく中で画面でダイナミックなデータが見えるという点では進化したという。しかし、昨今の経営会議ではPowerPointやExcelなどを用いており、静的なデータのため紙と変わりがないのではという疑問が木口氏にはあるとのことだ。
情報システム部門における従来の情報基盤構築におけるアプローチは、ソースシステムからBIシステムに入れていくデータは、旧態依然のウォーターフォール型の要件定義を行い、基本設計し、開発、テストするという流れでBIシステムを構築。同氏は「果たしてビジネスの速度に合った意思決定支援を行う仕組みかと言えば、そうは言えないのが実態だ。これはERP(Enterprise Resources Planning)に進化していく過程においても変わらない」と指摘。
最新のアプローチは実務に利用するデータからアプローチし、通常業務で扱う情報を次世代型BIツールでそのまま分析・可視化する。そして、データを特定して関連性を定義し、データの出自を明らかにすることでソースシステムを特定、定義を行い、管理することだという。
SAPユーザーが抱える課題とは?
同社では、実態を探るためAWS(Amazon Web Services)と共同でSAPユーザーに向けて意識調査をグローバルで行った。質問として「分析のためにSAPのデータをクラウドに複製することは組織にどのような影響を与えたと思いますか?」と尋ねたところ、データ分析能力やビジネスの有効性、デジタルオートメーション、収益創出などの項目で改善したと回答する企業が半数近くにのぼった。
また、SAPデータの活用によるメリットでは、意思決定を行う方法が一変した、分析により組織の俊敏性が向上した、といったポジティブな回答を得たという。さらに、SAPデータのオープン化による経済的メリットとしては、コストの削減と収益の増加を掛け合わせると年間100万ドル以上の効果がもたらされたとのこと。
その反面、時間や予算の不足、柔軟性に欠けるデータ形式など、SAP ERPデータの統合に伴う阻害要因も判明し、さらなるデータの活用に向けては、これらの課題を克服することが必須であるとの認識を木口氏は示す。
続いて、同氏はSAPユーザーに潜む課題に話題を移した。現状、SAPユーザーはSAP S/4HANA組み込みのオペレーショナルレポーティング機能「SAP S/4HANA Embedded Analytics」、SAP Enterprise Data Warehouse(EDW)ソリューション「SAP BW/4HANA」、BIフロントエンドツール「SAP BusinessObjects」、BIクラウドアプリケーション「SAP Analytics Cloud」の4つをBIツールとして使い分けている。
同氏は「SAPが描くBIの世界はクラウドベースが増えている。S/4HANAはクラウドで展開し、アドオンをさせないようになっている。そのため、データ活用基盤を別のクラウドで用意し、アナリティクスもクラウド、さらにはユーザーが持つ異なるクラウドベンダーのデータレイクやDWH(データウェアハウス)もあり、多くのクラウドを使い回している」と話す。
こうした環境のもと、ビジネス部門では各クラウドに分散しているデータをそれぞれのクラウドで閲覧しなければならないほか、SAPが推奨するフロントツールで閲覧するため労力がかかることから、最終的にはExcelにダウンロードし、分析しているのが実態だという。
一方、データ統合にも課題を抱えている。SAPではデータ連携ツールとして「SAP Data Intelligence Cloud」「SAP Data Service」「SAP Datasphere」「SAP S/4HANA」などを提供。
ただ、用途や目的に応じてツールを使い分ける必要があり、データ統合もさまざまなルート、方式、ツールを使い分けなければならなく、同氏は「ビジネスに変化に応じてシステムを変える時に、これらのツールを使い回してもスピードが向上するのか、また使い方に関してもガバナンスという意味では良いものではない」との見解だ。
Qlikが打ち出す、SAPデータの価値を引き出すデータパイプライン
そこで、QlikではSAPデータの価値を引き出すデータパイプラインという考え方のもと、ソリューションとその展開の方策を提言している。これは(1)ローコードでデータパイプラインをデザインし、(2)デザインにもとづいてSQLをDWHにプッシュダウン、(3)DWH上でSQLを実行してデータ変換・データマートの作成を実行するというものだ。
同氏は「データパイプラインはオープンでセキュアな環境で実現し、変化対応力を強化するための機能を備えている必要がある」と述べている。
現状のデータパイプラインはバッチ連携、直接参照、そのほかの連携など、さまざまな連携方式でデータが連携されており、主要システムへの付加が増大し、業務速度や変化対応力の低下を招いているという。そのため、同社ではデジタルツインでデータパイプラインを構築することを推奨している。
木口氏は「Qlik Replicateを用いて基幹システムを複製すれば、どのような使い方をしても基幹システムには影響が及ばない。密連携から疎連携に移行し、分析環境の高度化や分析業務の近代化が実現できる」という。
これにより、統合情報基盤には必要な情報がすべて集約されるため、データの準備やビジュアライゼーションのためのコーディングする必要なく、組織内外の膨大なデータを収集・統合・分析し、エビデンスにもとづく時事情報を可視化できるとのことだ。
こうした考え方をもとに、SAPデータ整備のひな型として「SAPアクセラレーターパッケージ」を提供しており、財務分析や在庫管理など対象となるSAP領域をプリセットしたものとなる。
同氏は「堅牢なシステム構築の手順を踏まずにデータの可視化が可能なため、ビジネス速度に追従できるソリューションパッケージだ」と説く。
Qlikを活用したデータパイプラインのユースケースとして、NECパーソナルコンピュータが紹介された。同社では「IBM Db2」にSAPを展開していたが、生産レポートなどが日次更新で利用率が向上しなかったことに加え、在庫所要量レポートといった数百のアドオン開発、データをSAPから直接ダウンロードしてExcelで加工していた。
そのため、Qlik Replicateでニアリアルタイムにデータ活用基盤をSQL Server上に複製して「Qlik Sense」で閲覧できるようにした。汎用性の高いデータベースのデータをBIツールで活用し、生産性・保守性を高めるとともに、データベースに格納されるデータをカタログ化することでBツールで広い裾野のユーザーで活用が可能になった。
最後に木口氏は「これまで取り組んでいなかったSAPデータに真正面から取り組みながら、データを活用するための方策として、さまざまなソリューションを展開している」と力を込めていた。