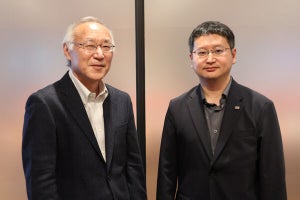ecbeing(イーシービーイング)が提供するECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」は、中堅大手向けのECサイト構築市場で圧倒的な実績を誇っている。構築実績は1600サイトを突破し、年間流通額は1兆円を優に超えている。機能を拡充し続けるコアのプラットフォームに加え、豊富なリソースを持つデジタルマーケティング支援でも差別化している。さらに、時流に乗ったソリューションを社内から生み出し、独立したサービスとして自走化させる体制が、独自の強みとなっている。コアの「ecbeing」や周辺ソリューションの強化策について、上席執行役員マーケティング営業本部 副本部長の斉藤淳氏に聞いた。
<流通額は1.2兆円超に>
――「ecbeing」の直近の実績は?
非常に堅調に導入企業数が伸びている。ECサイトの構築実績は、1600サイトを超えており、2023年の年間流通総額は1兆2405億円となった。ECサイト構築プラットフォームとしては国内で最も大きい規模にある。
2024年3月期における「ecbeing」自体の売上高は100億円を超えている。サイト制作やプロモーション支援などデジタルマーケティングの領域の売上高も非常に伸びており、3期前の売上高が27億円強だったのに対し、2024年3月期は35億円近い規模になった。
レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo(レビコ)」など、周辺ソリューションを提供しているECクラウドサービスも拡大している。この領域は最も成長率が大きく、過去3年間で30%以上の売上成長を継続している。
コアの「ecbeing」に加えて、デジタルマーケティング、ECクラウドサービスがそれぞれ成長し、相乗効果を発揮できていることが強みとなっている。
――ecbeingが提供する周辺ソリューションの強みは?
当社では社内ベンチャーのような形でサービスを立ち上げ、軌道に乗ってからは分社化して独立した形でサービスを運営している。
分社化している「ReviCo」は250社くらいにサービスを提供しており、そのうち4割くらいが「ecbeing」以外のECプラットフォームを利用している企業だ。
周辺ソリューションを運営する体制や本気度に違いがあると思う。
<他にはない仕組み>
――コアのプラットフォーム「ecbeing」と、クラウドで提供する周辺ソリューションの組み合わせが、差別化になっているのか?
一般的なクラウド型のECプラットフォームの場合、1つのプラットフォームが自動バージョンアップし、それにカスタマイズしたシステムを組み合わせている。コアのプラットフォームがバージョンアップすると、どうしてもカスタマイズ部分にも影響が生じるはずだ。カスタマイズによっては、自動バージョンアップを反映できないユーザーが出てくるなど、さまざまな制約が発生する。
「ecbeing」の場合、コアのプラットフォームはフルカスタマイズでき、クラウドで提供する周辺ソリューションが自動バージョンアップし、時流の変化に対応していくというスタイルだ。コアのプラットフォームはバージョンごとにガラッとモデルチェンジすることが可能で、最新のテクノロジーやインターフェイスを採用できる。
また、「ecbeing」自体にも、CDPやCRMの機能を持つ「Sechstant(ゼクスタント)」や、AIレコメンドサービス「AiReco(アイレコ)」の機能の一部を標準で組み込んでいる。周辺ソリューションが「ecbeing」の機能強化に貢献し、それらの機能自体も自動バージョンアップしていく。
<オムニチャネルで活躍>
――オムニチャネルの文脈でも周辺ソリューションが活躍しているのか?
比較的、新しい周辺ソリューションの一つに予約管理システム「RESOMO(リソモ)」がある。これはECサイトの顧客データや行動履歴とひも付けて、商品の店舗受け取りや、顧客の来店予約、イベント予約を受け付けることができるシステムだ。顧客をオンラインからオフラインに誘導するツールとして効果的に活用する企業が増えている。
レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」は、レビューを増やすことでECサイトだけではなく、実店舗の購入促進に活用する取り組みも増えている。店頭でQRコードからレビューを確認できるようにすることで、購入を後押ししている。実店舗やECで商品を購入した後に顧客がレビューを確認し、商品の使い方を参考にしたり、購入した商品に納得感を得たりするような利用シーンも増えているようだ。
実店舗を展開していて「Sechstant」を導入した企業は、必ず実店舗とECの売り上げをクロスで分析している。実店舗で購入しているけどECでは買っていないユーザーと、両方をクロスユースしているユーザーの違いを分析したり、ロイヤリティ化しやすいユーザーはどういう特性があるのかを分析したりしている。そこで得た結果を基に、メールだけではなく、LINE配信やアプリでのプッシュ通知でアクションを起こすことができる。
社長の林が日本オムニチャネル協会の専務理事を務めており、当社としてもオムニチャネルのトレンドや事例の研究は積極的に行っている。
<AI活用をさらに強化>
――今後、さらに強化していくソリューションは?
1つ1つの周辺ソリューションをさらに強化していく。特にAIを活用したソリューションには可能性を感じている。当社でも「ChatGPT」を活用したAIチャットボット「Ai DIGITAL STAFF(AIデジタルスタッフ)」を提供しているが、それ以外のソリューションにおけるAI活用も強化していきたい。
コアの「ecbeing」もさらに強化していく。BtoB領域の機能拡充にも注力する。デジタルマーケティングの支援も含めて、全方位的にサービスを強化していく。
■「ecbeing」
https://www.ecbeing.net/