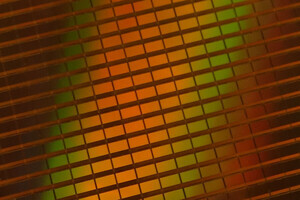ガートナー ジャパンは5月21日~23日、「ガートナー データ&アナリティクス サミット」を開催した。「AIのトップ・トレンド」と題したセッションに登壇したGartner ディレクター、アナリストのベン・ヤン氏は、2023年から始まった生成AIブームを振り返り、進化のトレンドを解説した。
速いペースで進行している生成AIの本番稼働
講演は、2024年1月にウェビナーで実施した「世界の生成AIの現状」を調査した結果(n=1,299)の紹介から始まった。同調査で生成AIへの投資状況を尋ねたところ、「調査中」「試験運用中」「本稼働中」への回答がそれぞれ35%、38%、21%となった。2023年3月時点で一桁%だった本番稼働が1年も経たないうちに2割を超えたのは驚くべきことだ。生成AIへの投資も増加傾向で、顧客対応部門やIT部門に限らず、多くの部署での利用が進んでいる。
ヤン氏は2023年と2024年を比べ、「2023年は調査や探索の年で、大規模言語モデル(LLM)に注目が集まっていた。これに対して2024年は実行して結果を出す年になった。また、テキストからテキストを生成するLLMから、画像、音声、動画も扱えるマルチモーダルモデルが登場している。それに伴い、生成AIを活用しようという企業の姿勢も変化した。目新しいおもちゃから、地に足をつけた活用に取り組もうとしている。実際に本番稼働が始まると、一部には思ったような成果を得られない企業も出てきた」とした。
先の調査結果から、自社がその21%に当てはまらないと焦る必要はない。先行している企業の中には、単純な生成AIツールを利用しているだけのところもある。本格的な活用に向けて検討を進めている企業の役に立つのが、生成AIのトレンドに目を向けることだ。ヤン氏はテクノロジートレンドとビジネストレンドの2つに分けて、それぞれを解説した。
マルチモーダルモデルが牽引するテクノロジートレンド
まず、ヤン氏は以下の5つのトレンドを取り上げ、企業が生成AIを本番稼動に移そうとするとき大きな影響を及ぼすことになるとした。
部門特化型モデルあるいは業界特化型モデル
ユーザーがプロンプトに質問を入力すると、通常のモデルはインターネットから得られる情報を基に回答を生成し、出力する。しかし、インターネットの中にあるものだけが専門知識ではない。今後、ドメイン知識を基に、タスクを実行するモデルが登場することになるだろう。
エージェントベースシステム
エージェントとは人間に代わって行動してくれるAIである。ユーザーがタスクをエージェントに指示すると、与えられたタスクをサブタスクに分解し、それぞれのサブタスクを実行してくれる。AIがタスクを解釈する分、現時点の自動化よりも一段上のレベルの自動化が実現する将来が見えてきた。
コンポジットAI
例えば、LLMにガードレールツールを組み合わせ、ハルシネーションを防止するなど、複数のAI手法を組み合わせ、より望ましい結果を得られるようにすることをコンポジットAIと呼ぶ。
役割の変容
LLMは人間の言語だけでなく、プログラミング言語も扱うことができる。データ&アナリティクスのエンジニアは、生成AIツールを使うことが前提の新しいAIエンジニアリングのプロセスで仕事をするように変わる。
オープンソースモデル
使いこなせるだけのスキルを持ち合わせていることが条件になるが、商用モデルと異なり、自社のデータセンター内での利用ができること、コストコントロールができることがオープンソースモデルの魅力だ。
テクノロジーの進化の影響を受けるビジネストレンド
テクノロジートレンドに続いて、ヤン氏が取り上げたのが4つのビジネストレンドである。
パワーバランスの変化
強力な生成AIツールの活用が従業員レベルで進めば、1人の従業員の生産性が、既存のチーム全体の生産性に匹敵するレベルになっても不思議ではない。それに伴い、社内の民主化も進むだろう。
リーダーシップの変化
全社的に生成AIツールを使うとは、出力した結果を採用する従業員1人ひとりが自分の仕事に対しての説明責任を負うことでもある。テクノロジーを使いこなすスキルの向上もさることながら、説明責任を全うできるまでの成長が求められる。
価値の透明性
生成AIのプロジェクトはリターンだけでなくリスクも伴う。想定していた財務的リターンを得られないことだけでなく、ブランドイメージが毀損することもリスクである。プロジェクトの計画時点でROIを算出するときは、リターンだけでなくリスクを含めた可視化が求められる。
トラスト(信頼)
前述のエージェントベースシステムのような高度な自動化を実現するには、生成AIが信頼できるものでなくてはならない。現時点ではエンタープライズレベルのユースケースに対応したエージェントベースシステムは登場していないが、エージェントからの提案を信頼できるようなシステムの構築が求められる。
コストは生成AIプロジェクトのアキレス腱
生成AIには大きなポテンシャルがある反面、本格的な活用を阻害する要因もある。「生成AIプロジェクトの最大の脅威の1つがコストである。組織の半数以上がコストの見積もり/計算を誤ったために、取り組みを断念している」とヤン氏は警告した。ガートナーの試算によれば、生成AIプロジェクトのコストは、当初から500〜1000%以上に膨張する可能性もあるという。
ソフトウエアから、インフラ、人材不足を補うためのサービス、データの整備、セキュリティ対策に至るまで、プロジェクトには多くのお金がかかるが、「この他に隠れたコストもある」とヤン氏は指摘する。その隠れたコストに該当するのが、データ&アナリティクス部門がビジネス部門と協力関係を構築しなくてはならないこと、業界特有あるいは部門特有の要件の明確化が必要になること、役員との信頼関係の醸成が必要になることなどだ。直接的な項目だけでなく、時間がかかることや労力が必要なことを含めた検証を事前に行うことが失敗リスクの低減につながる。
生成AIの全社活用は簡単なジャーニーではないが、企業が取り組むべきは価値創出にある。ヤン氏は3段階で企業がやるべきことを提言した。まず、トレンドから遅れをとらないかたちで活用を進めること、次に生成AIを使って差別化を図ること、最後に変革を成し遂げることだ。リーダーには、自社の取り組みの優先順位を整理し、プロジェクトポートフォリオを精査してほしい。