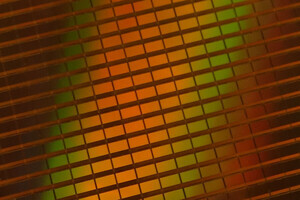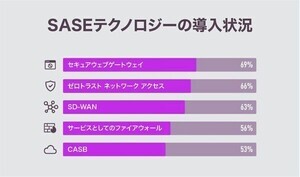チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは5月21日、事業戦略に関する記者発表会を開催した。同日、2024年第1四半期のサイバーセキュリティのトレンドに関するレポートも発表された。
同レポートによると、2024年第1四半期、グローバルで1組織当たりの週平均サイバー攻撃数は1,308件確認したという。これは2023年第1四半期と比べて5%の増加、2023年第4四半期からは28%の増加となる。国内では、1組織が1週間当たり平均1,066件の攻撃を受けたことが確認されている。
ランサムウェア攻撃に関しては、窃取した機密データのリークサイトへの掲載による公開を止める代わりに身代金の要求を行う「二重恐喝型ランサムウェア」が増加している。リークの被害に遭った業界は製造業が最も多く、世界では対前年比96%増加、日本では公開された業種の50%以上が製造業であることが確認されているとのことだ。
戦略のキモはプラットフォームによる保護
日本法人社長の佐賀文宣氏は、海外で実施された自社イベントで発表された戦略について、「プラットフォームとして守ることを発表したことが大切。われわれは7年前からInfinityアーキテクチャを掲げ、プラットフォーム企業としての役割を果たしてきたが、改めて明示的に発表した」と述べた。
同社のプラットフォーム「Check Point Infinity Platform」は、ネットワークセキュリティ製品「Quantum」、クラウドセキュリティ製品「CloudGuard」、ワークスペースセキュリティ製品「Harmony」から構成されている。これらの製品において「クラウドによる供給」「AI駆使」が特徴だという。
「われわれのソリューションの特徴はAIを駆使して、クラウドで提供すること。他社がマーケティングの観点から喧伝しているのとは異なり、われわれのAIはすでに具現化されおり、圧倒的な成果を出している」(佐賀氏)
そして、佐賀氏は「Check Point Infinity Platform」が実現する3つのCについて、説明した。3つのCとは、「Comprehensive(包括的)」「Consolidated(統合的)」「Collaborative(協働的)」だ。
「われわれはダッシュボードを統合して運用する。これにより、コスト削減 と運用効率向上を実現し、ユーザーは対処しなければならないことに集中できるようになる。また、XDRにおいてはシスコシステムズやパロアルトネットワークなど他社の製品とも連携して、Collaborativeを実現する」(佐賀氏)
さらに、佐賀氏は「われわれの特徴は、AIを脅威防止に利用するだけでなく、対話型で運用のために使う点」と、同社の生成AI活用についても言及した。
同社は、生成AIアシスタントとして、対話型でポリシー作成とセキュリティ分析を支援する「Infinity AI Copilot」をInfinity Platformに組み込んで提供している。佐賀氏は、「Infinity AI Copilot」について、「マイクロソフトなどの生成AIと連携可能ながら、データは共有しないし、セキュリティログはトレーニングに使わないなど、設計思想がしっかりしている」と述べた。
他社との違いは具現化されている生成AI
続いて、セキュリティー・エンジニアリング統括本部 執行役員 統括本部長 永長純氏が、「プラットフォーム」「AI駆使」といった観点から、製品の最新動向について説明した。
前述した3Cの実現においてカギとなる製品が、セキュリティの統合運用を実現する「Infinity Portal」だ。永長氏は、「昨今、サイバー攻撃が多様化しており、企業はサイバーレジリエンスを担保するために、さまざまなポイントソリューションを導入した上に統合運用ツールを導入する。これでは最近の攻撃を防御できない。複数の製品を協働させ、プラットフォームとして稼働させることが重要」と、セキュリティの統合化の重要性を指摘した。
また、永長氏は「他のベンダーもプラットフォームをアピールしているが、チェック・ポイントは何年も前からプラットフォームを進めている。アーキテクチャだけでなく 運用そのものも統合している。9個のUIを持つ製品で企業の資産を守れるのかは疑問だ。われわれは単一のUIで可視化できる」と、セキュリティの統合における同社の優位性を強調した。
「Infinity AI Copilot」については、「生成AIを使って運用を効率化するソリューション。佐賀が申し上げたが、われわれの生成AIはすでに具現化されていることを強調したい。真のプラットフォームとして重要なことは、協働的に動くか、防止する力が高いか、起きたことに対応するだけでなく、起きたイベントを正しく理解して、人が対応することを明確にすることが具現化されていること。われわれはこれらを具現化している」と、永長氏は説明した。