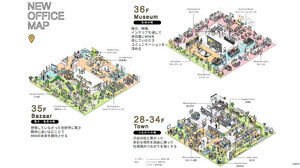突然だが、年末年始に我が家で活躍したスマホアプリがいくつかある。まずはNetflix。いつもより長めの休暇だったので、以前から気になっていたアニメ『リコリス・リコイル』を一気見した。千束ちゃんと友達になりたい。同様の理由でPrime VideoやDisney+も活躍した。それからStarbucksアプリ。モバイルオーダーは並ばずに受け取れるので、初売りで混んでいるショッピングモールでも便利だった。
そうした中でもおそらく最も活躍したのが、「家族アルバム みてね」(以下、みてね)だろう。2015年にリリースされたこのアプリは、子どもの画像や動画をアップロードして、リアルタイムに家族で共有できる。遠方に暮らす祖父母は孫の成長をリアルタイムに見られるとあり、いつも写真を楽しみにしているようだ。お正月には、帰省時に孫と一緒に記念撮影した写真を共有すると、とても喜んでいた。
みてねのユーザーは国内外で2000万人を超え、日本でも子どもを持つ親の約半数が使っているという。読者の中にも、年末年始に多数の写真をアップロードしたユーザーは多いのではないだろうか。
みてねを運営するのは、「モンスターストライク(通称:モンスト)」やビューティアプリ「minimo(ミニモ)」などを手掛けるMIXI。そして、ユーザー数が2000万人を超えたみてねを開発するエンジニアリング組織を束ねるのが、MIXIのみてねプロダクト開発部で部長を務める平田将久氏だ。
今回、みてね開発組織に見られるアジャイル型の組織文化の浸透と、DX Criteriaを活用した開発者体験の向上について、平田氏に話を聞いた。同氏は2011年にミクシィ(現:MIXI)に新卒入社し、エンジニアとしてSNSの「mixi」を担当。2014年に転職し複数企業でチームのスクラム導入やスクラムマスター、組織変革などのマネジメント業務に携わった。米国シリコンバレーのスタートアップ企業でプロダクト開発などを経て、2022年12月にMIXIに再入社。現在はみてねにおけるエンジニアリング組織全体のマネジメントを行っている。
開発組織にアジャイル開発が根付かない2つの大きな理由
平田氏によると、アジャイル開発を阻害する要因はいくつかあるが、大きく2つ挙げられるという。1つは組織構造の問題だ。アジャイル開発においては、同じチーム内に多様な職種の人がフラットな関係で集まった小さな1チームを作ることが理想とされるが、組織的な制約によって難しい場面もある。
それは、同じチームであっても特定の職能の人だけが別の組織に属していたり、社員としての格が異なっていたりする場合だ。これに対しみてねでは、チームを構成するメンバーが各チームのミッションにフルコミットできるような状態にしているという。兼務も出ないように配慮しているそうだ。
「チーム内の誰かが、兼務のために50%しか参加できません、となってしまうと、チームが一丸となって同じミッションを成し遂げるというカルチャーが生まれない原因にもなります。これではワンチームになりづらい」と、平田氏は語る。
もう一つの要因は、アジャイル開発を率いる経験豊富なリーダーの不足だ。アジャイル開発の経験を持つリーダーがいないと、メンバーの誰かが自身で書籍などで勉強しながら導入することになる。これではチームに対し細部まで情報が正確に伝わらず、メンバー間で前提知識やレベルに差が出る要因となる。
そうした場合に、開発を進める中で迷いが出る場面があると、どちらを選択してもうまくいかないような状態になりかねないのだという。迷いが出る場面に、どちらを選択しても前に進む一歩だという認識をチームに持たせることができるような専門人材が、求められている。
みてねの開発組織に芽生えたカルチャーとアジャイルのための取り組み
翻って、みてねの開発組織はアジャイル開発が定着しない2つの要因に対し徹底的なアプローチで対応している。組織構造の点では、「よほど最悪の状態でもない限りは兼務することはない」と平田氏が話すように、誰もがチームのミッションにコミットできる環境を作り上げた。
また、各メンバーのチーム内での働きを適切に評価できるよう、エンジニアリングの専門的な能力だけで評価するのではなく、チームメンバーとしてどのように貢献したのかや、他者とのコラボレーション、リーダーシップ、開発のマインドセットについても評価する仕組みを導入している。
さらに、みてねでは平田氏自身のアジャイル開発の経験に基づいて、チーム内でアジャイル開発やスクラムの研修を定期的に実施している。3日間で16時間の研修をするような、網羅的な内容が特徴だ。現在はシニアのスクラムマスター採用も並行して進めるなど、チーム内への引き継ぎも進める。
こうした取り組みの結果として、みてねでは仮説検証をしながら不確実性と戦おうとする大前提を全員で共有しているそうだ。また、みてねのユーザーが社内にも多いため、直接開発には関わらないユーザーの意見を聞きやすいという特徴もあるという。
「アジャイル開発に適した組織構造としたことにより、少しずつアジャイル開発のためのカルチャーが芽生え始めていると感じます。いろいろな会社でアジャイル開発に関する研修を実施してきましたが、みてねはその中でも意欲的に参加してくれるスタッフが多く、知識の習熟度や定着度のレベルが高いです」と平田氏は語る。
現在の組織構造とアジャイル開発について、メンバーの反応はどのようなものだろうか。まだ定量的に計測したことはないそうだが、1on1などのヒアリングの結果から、平田氏の研修によってチーム内の共通認識が作られ、適切な判断をすべき場面で迷いなく進める状態になったことが分かったという。
加えて、開発組織の拡大に伴ってLeSS(Large-Scale Scrum)というフレームワークを導入したところ、一つ一つのチームサイズが分割され、会議体での発言のしやすさやコミュニケーションの取りやすさなどにも良い影響が見られ始めているそうだ。
オープンな指標「DX Criteria」を活用し開発組織のDX定着度を評価
日本CTO協会はDXの進捗を評価するためのガイドライン「DX Criteria」(DXクライテリア)を監修している。これは、「チーム」「システム」「データ駆動」「デザイン思考」「コーポレート」の5つのテーマに対しそれぞれ64項目の設問があり、多角的に自社のDXの取り組みを可視化して確認できるガイドラインだ。
DXクライテリアは不確実性が高い時代において、勝てる事業を作るための仮説検証能力を組織が持つためにどう対応すべきかを評価する。評価シートは無料で利用でき、結果を公表している企業もあるので、自社の組織ケイパビリティを比較してみるのも良いだろう。
DXクライテリアに当てはめると、みてねの達成率は74.53%だ(2023年9月末時点)。スコアを公開している37社の平均は51.81%(2021年「DX Criteriaレポート 第二回」)、比較的DXが進んでいると考えられる企業でスコアの高かった5社の平均を取っても70.47%(同上)であり、みてねのDXが進んでいることが分かる。
「みてねの開発に携わる以前から、みてねはなんとなくスコアが高そうだと感じていたので、想定通りではありますが、今回改めてスコアを可視化できてよかったです。DXクライテリアは必ずしもすべての開発組織で達成すべき100点満点を定めているというわけではないと思うので、まずは80%くらいの達成率を目指したい」と、平田氏はさらに前向きな姿勢を見せている。
"文化は組織構造に従う"からこそ組織構造の変革に着手
みてねのDXクライテリアの達成率は74.53%であり、80%まであと5ポイントほど上昇の余地がある。そこで、この5ポイントのための次なる一歩について平田氏に聞いてみた。
まずはアジャイルな開発カルチャーについて。現在の開発チームにはエンジニアやデザイナーなど多様な職種のスタッフが所属するが、これから相互にどれだけタスクを取り合えるのかを具体化していくという。もちろん、エンジニアがデザイナーの仕事を完全に奪うような状態にするのではなく、異なる職種のスタッフが具体的にどのような作業を行っているのかを今以上に知り、業務を効率化できる余地を探していくそうだ。
また、データの扱いに関するリテラシーの底上げも図る。例えば、A / Bテストの結果を科学的に判断するためには統計や検定の知識が必要だ。これに対し、ツールなどを活用しながら誰もが正しく評価できるようなリテラシーを育むとしている。
加えて、デザイン思考についても改良していくという。これまでのみてねではUX(User Experience)に関する専門人材がおらず、定性的な調査や詳細なユーザーインタビューに着手できていなかった。新たな人材の採用などを通して、今後は定性的なデータをプロダクト開発に生かせるカルチャーを生み出すそうだ。
高いDXクライテリアの達成度がありながらみてねの開発組織としてさらなる成長をめざす平田氏に、他の組織でもアジャイル開発を取り入れるためのヒントを聞いてみた。すると、以下のように返事が返ってきた。
「まずは、アジャイル開発が根付かない2つの理由(組織構造、アジャイルリーダーの不足)に徹底的に向き合ってほしいです。特に組織構造は案外軽視されているような印象があります。アジャイル開発の世界で有名なCraig Larman(クレイグ・ラーマン)氏の言葉に『文化は組織構造に従う』というものがあります。最も努力して変えるべきは組織構造だと思います」(平田氏)