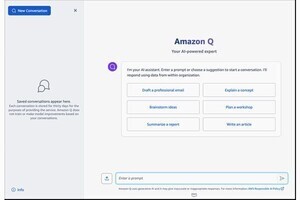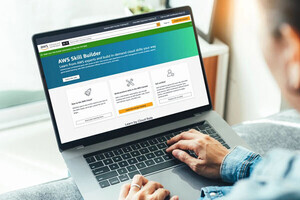AWSジャパンは12月6日、年次イベント「AWS re:Invent 2023」に関する記者説明会を開催した。今年は11月27日から12月1日までの5日間にわたり開催された同イベント。
長期間開催されたこともあり、会期中には5本の基調講演が行われた。これらすべての基調講演を聞くのも至難の業だ。今回、パブリックセクター技術統括本部長 瀧澤与一氏が5本の基調講演における注目点を紹介した。
Peter DeSantis氏:サーバレスと量子コンピューティング
ユーティリティコンピューティング担当シニアバイスプレジデントのPeter DeSantis氏は、サーバレスと量子コンピューティングを中心に講演を行った。
瀧澤氏は「データベースのサーバレスにおいては、データベースのノードが分散されることになる」と述べ、同社がそのための技術に取り組んでいると述べた。
同社は、Amazon RDSを発表して以来、スケーラビリティやパフォーマンスの運用負荷を軽減させることに取り組んでおり、データベースのサーバレス化はその一環となる。
瀧澤氏は、「データベースではログさえあれば、一貫性を保ち、スケールできる」とログの重要性を強調した。Amazon Auroraでは、サーバレスの取り組みとして、Caspianを開発し、ハイパーバイザー、ヒートマネジメント・プラニングシステム、データベースエンジンの組み合わせ、ms単位で、オーバサブスクリプションでサイズを変更できることが紹介された。
データベースのサーバレス化を実現するサービスとして、「Amazon Aurora Limitless Database」が発表された。
また、瀧澤氏は、分散システムを実現するには、ハードウェアレベルで開発を行い、キャッシュサーバもサーバレス化が必要だと説明した。そのためのサービスとしてリリースされたサービスが「Amazon ElastiChache Serverless」となる。
一方、量子コンピューティングに関しては、独自のチップ開発に取り組んでいる。量子コンピューティングではBit flipというエラーの訂正が必要であることから、これを是正するチップの開発が行われている。今後、「Logical Qubit」の発表が予定されている。
Adam Selipsky氏:さまざまなReinventing
CEOのAdam Selipsky氏は、ストレージ、コンピューティング、生成AI、NVDIAとAnthropicとのパートナーシップ、データの活用やAIを活用したガバナンスの確立などにおけるReinventingについて、講演を行った。
生成AIに関しては、3つの階層と人材育成について説明が行われた。AWSは、生成AIに対して、基盤、基盤モデルへのアクセス、アプリケーションという3つの層を用意している。
最下層の基盤層では、学習と推論を実現するインフラを提供しており、今回、コスト効果の高いインフラを提供するサービスが発表された。
真ん中の層の基盤モデルへのアクセス層では、ユーザーが業務に最適なモデルに使うことが求められて始めていることから、Bedrockの新サービスが発表された。
最上位層のアプリケーション層に関しては、生成系AIを活用するアプリケーションとして、「Amazon Q」が発表された。
Swami Sivasubramanian氏:生成AIとビジネス
データ&機械学習サービス担当バイスプレジデントのSwami Sivasubramanian氏の基調講演で、主に生成AIについて語られた。やはり、今年のIT業界は生成AI抜きには語れないといったところだろうか。
AWSは、生成AIの活用するにあたって、リスキリングが必要と考えており、例えば、AWS AI & 機械学習スカラシッププログラムを立ち上げて、無償で提供している。
瀧澤氏は、AWSのAIと機械学習分野のエキスパートをつなぎ、顧客による生成系 AI を活用した新製品・サービスやプロセスの構想から設計・立ち上げを支援するため、生成AIイノベーションセンターを開設したことを紹介した。
Ruba Borno氏:パートナーの重要性
Ruba Borno氏の基調講演では、「顧客の不可能を達成するためにパートナーがいる。パートナーは顧客が夢を見るためのCatalyst(触媒)でもある」として、96のパートナーの表彰が行われた。
リージョナルなパートナーとしては、クラスメソッド、富士通、GeekFeed、アクセンチュア、IBM、トレンドマイクロ、DataBricksなどが表彰されたという。
Werner Vogels氏:クラウドにおけるコストの重要性
CTOであるWerner Vogel氏は、基調講演において、コスト、The Frugal Architect、AIについて語った。瀧澤氏は、「オンプレミスではハードウェアの制約があるが、クラウドではその制約がない。しかし、コストを考慮することが重要であるため、われわれはコストを起点にアーキテクチャを考えている」と説明した。
Vogel氏は、以下の7つの原則から成るThe Frugal(倹約的な) Architectを紹介したという。
- コストは非機能
- ビジネス効果
- トレードオフ
- 監視されていないシステムは未知のコストにつながる
- コストコントロールをする
- コスト最適化を継続する
- 挑戦されない成功は思い込みにつながる
そして、瀧澤氏は「コストは、サステナビリティ(持続可能性)の考慮の指標とも言える」として、AWSのサービスにはそのための要素が随所に組み込まれていると説明した。