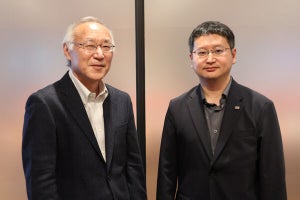「海外投資家の日本への見方は明らかに変わっている。今がチャンス」─三井住友信託銀行社長の大山一也氏はこう話す。「失われた30年」を経て、少しずつデフレのトンネルを抜けようかという日本経済だが、米国のインフレ、中国の不況など先行き不透明感も漂う中、大山氏は「いつの時代も不透明なのは変わらない」と話す。「金利が付く時代」を控え、「個人の投資機会を拡大したい」と話す大山氏が今後目指す姿は─。
【あわせて読みたい】三井住友トラストが日本の投資家に「未公開株投資」提供、米ファンドと提携
「マーケットの二極化」をいかに解消するか?
今、米国のインフレと、それに対応するFRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策、さらには中国の不動産バブル崩壊、不況局面など、世界経済の先行きには不透明感が漂う。
だが、欧米が「金利が付く時代」に回帰、日本も物価上昇が続くなど、徐々に世界はインフレに向かっている。2024年には「新NISA」がスタート、さらに政府は「資産運用特区」の創設を表明。そうした状況下にあって、日本でもかつてないほど資産運用への関心が高まる。
「社長に就任して最初に、『資金、資産、資本の好循環の実現』をトップアジェンダ(課題)に掲げた。それは今回の新中期経営計画にもしっかりと引き継がれている」と話すのは、三井住友信託銀行社長の大山一也氏。
信託銀行は、個人や企業の財産を受託して管理・運用する「信託業務」、預金・貸付・為替業務を行う「銀行業務」、そして不動産・証券代行・相続関連などの「併営業務」を担う存在。
つまり、銀行として金融市場、不動産を始めとする資産市場、有価証券を通じて資本市場という形で「資金、資産、資本のあらゆる市場に対して携わり、インフラを提供するエッセンシャル(必要不可欠)な存在」という大山氏の認識。
そして今は、インフラを提供するだけでなく「自ら先導役となって、能動的・主体的に資金を動かし、社会的な新たな価値を創出し経済の持続的成長を果たす役割を、マルチステークホルダーから託されている存在」
だが、これまでそうした役割を十分に果たせてきたかというと反省もある。過去において他の金融機関とのシェア争い、パイの奪い合いに力を注いできたのも、また事実だからだ。今は、単にパイを奪い合うのではなく、そのパイ自体を大きくすることで、自らも利益を得ていくという方向に考え方を変えている。
また、これまで日本は「失われた30年」と呼ばれ低成長状態が続いてきた。そのため、大山氏が21年の社長就任時に「資金、資産、資本の好循環の実現」を掲げた当初は、その実現に懐疑的な声も上がったという。
それに対して大山氏は「足元で世界経済自体は不透明だが、いつの時代でも不透明。ただ、日本は物価、賃金が上がり、次に金利が上がるという環境が見えてきている。また、世界の投資家からあまり注目されていなかった日本だが、海外の投資家と話しても、明らかに見方が変わってきている。ここが一番のチャンス」と話す。
資産運用に関して言えば、個人はこれまで主に株式や投資信託、一部不動産などに投資してきたが、どうしてもパッシブ運用、インデックス運用で市場指数と連動した保守的運用が主になり、投資先の多様性に欠けていたという声は根強い。一方でファンドなどの大口・長期の資金を扱える存在は、様々な対象に投資し、高いリターンを上げてきた。大山氏はこれを「マーケットの二極化」と呼び、資本市場の活性化を阻んでいる面もあったと指摘する。
そこで取り組んでいるのが、「プライベートアセット」への投資拡大。具体的には22年に米大手投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントと提携、未上場株式などオルタナティブ資産に個人が投資できるようにするために商品開発を進めている。
「これまで個人が投資できなかったプライベートアセットにアクセスできるような『投資の民主化、社会化』を図っていきたい」(大山氏)
日本ではこれまで働いた給与を積み上げていくことこそ大事で、資産運用は必要ないといった雰囲気が主流だった。これを、誰もが当たり前に投資する「投資の民主化、社会化」を進める方向に社会のマインドを変えていきたいという大山氏。
これまで年金運用を通じて約20年、オルタナティブ運用、プライベートアセットの運用を手掛けてきた実績、歴史があるが、これをマーケット全体に広げていくという方向性。
ここは信託銀行としての強みが生かせる分野でもある。プライベートアセットは流動性が低く、アセットマネジメント会社が投資家に販売するまでにタイムラグが生じることがある。それを一時的にバランスシートを使って抱える必要があるが、信託銀行はグループの中で、それを完結させることができる。
また、年金運用の世界でプライベートアセットへの投資を進める中で、まず自行の銀行勘定で分散投資をして、実績を積み上げた上で、顧客にそれを示し「自分達も投資しているので、投資しませんか」という「セイムボート投資」という考え方を基本にしてきた。これによって投資家に安心感を与えられる点が、投資銀行などとの差別化ポイントになる。
さらに次に見据えているのが「デジタルアセット」の世界。23年10月、三井住友信託銀行も出資した、デジタルアセットの「ナショナルインフラ」を目指す新会社「プログマ」が設立される。
この会社は元々、三菱UFJ信託銀行が開発してきた発行基盤を分社化したもので、ここに三井住友信託銀行の他、三井住友フィナンシャルグループ、みずほ信託銀行、NTTデータ、SBI PTSホールディングス、JPX総研、データチェーンという計8社が出資する。
また、暗号資産交換業者大手のビットバンクと提携し、機関投資家や事業会社向けにデジタルアセットを保管・管理する「カストディビジネス」の実現に向けた検討を進めている。
ビットコインなどの暗号資産は世界的に「分散」しており、それを管理するのは1社だけでは難しい。「この世界がどのように展開していくかというメインシナリオは不明瞭。プレーヤーが一緒になって参加して、トライアルアンドエラーを繰り返しながらアップデートしていくステージだと思う」と大山氏。
DXを進めて若年層にアプローチ
これまで信託銀行は主に、高齢者層の安心・安全確保のために、相続の際の資産承継サービスなどを提供してきた。
また、かつては退職金を金利の高い貸付信託に預ければ、一定の老後が保障されている時代もあったが、今はもっと若い時から、資産形成が必要になっている時代。信託銀行としても、顧客層を広げていく必要があるのだ。
とはいえ、いきなり広く個人に営業をすると言っても難しい。そこで、企業年金を通じて取引のある企業の従業員、職域を中心にアプローチを進めている。
ただ、生命保険営業などもそうだが、会社の食堂などでチラシを配り、説明会を開くといったスタイルでは非効率で制約があることが課題だった。
そこで22年4月にリリースしたのが、スマートフォンアプリ「スマートライフデザイナー」。このアプリは確定拠出年金(DC)の残高を確認できる他、他の金融機関とも連携しているため、自らの資産を統合して、資産・負債のシミュレーションをすることも可能になっている。
「今までは企業年金の取引先従業員の皆さんにDMさえ打つことができなかったが、クリック1つでアクセスできるようになった」。DC管理をしている従業員だけで約165万人いるだけに、潜在的価値は大きい。
これはDXに向けた取り組みでもある。大山氏は社内で業務効率化を「縦のデジタル化」、事業やチャネルの壁を超える事業横断融合のDXを「横のデジタル化」と呼ぶ。
これまでも三井住友信託銀行では、各事業のメンバーが擦り合わせをしながら、融合して新たなビジネスを作り続けてきた歴史があるが、どうしても時間がかかる。それがアプリを通じることで、年金事業と個人事業の融合がスピード感を持って実現できた。
「対面営業のビジネスモデルではスケーリングがなかなか難しかった信託銀行の仕事が、DXを使うことで一挙にスケーリングできるようになってきた」
また、三井住友信託銀行は06年にSBIホールディングスとの合弁で住信SBIネット銀行を設立するなど、ネット銀行にいち早く取り組んだ会社でもある。
この連携を生かし、23年9月29日から、「三井住友信託NEOBANK」のサービス提供を開始。前出のアプリ・スマートライフデザイナーを経由して口座開設をすることで、住信SBIネット銀行が提供する銀行サービスを受けることが可能。スマートライフデザイナーとの相互導線、ネット銀行のサービスを通じて、新たな資産形成層との接点を持つことを狙う。
時代の変化に合わせ変わるビジネスモデル
三井住友トラストグループでは今年、自らが目指すべき数値目標として「AUF」(Assets Under Fiduciary)という指標を導入した。この指標は「社会課題解決と市場の創出・拡大に貢献する取り組みの規模を示す残高」だとしている。
2030年度の目標として掲げているのが、現在約480兆円のAUFを800兆円、グループ資産残高を215兆円(現在約120兆円)、資産管理残高を460兆円(現在約250兆円)に拡大すること。
なぜ、AUFという概念を掲げたのか。「これまでのように、自らバランスシートを拡大するということではなく、全体のパイが大きくなり、資金が回っていけばいくほど、信託グループの機能を生かした接点が増え、資産管理残高や資産残高も伸びてくる」
AUFの導入は、同社が携わっている様々な資産を大きくし、全体のパイを大きくしていくことを目指す姿勢を表している。このAUFの拡大は、日本経済全体のマーケットが拡大しているという証でもあるということ。
このAUFを掲げられたのは、統合から10年以上が経ち、会社としてのステージが変わってきたことも背景にある。統合当初は、会社としてのステータスを上げるためにバランスシートの残高を伸ばす局面もあった。
だが、銀行業務ではバランスシートを増やすと、それだけ資本が必要になりROE(株主資本利益率)が上がりにくくなるというジレンマがあった。
しかし今は「統合から10年が経過した今、安定した手数料収入が結構なボリュームになってきた。銀行業務のバランスシートを拡大して収益を稼ぐだけでなく、オフバランスの資産運用管理残高で収益を稼ぐことが可能な収益体質になった」(大山氏)
今後、バランスシートは前述のように、プライベートアセットに取り組む際に一時的に抱えるなどといった戦略的な使い方になってくる。他にも、政策保有株式を削減して得た資金を生かして、脱炭素などにつながる「インパクトエクイティ投資」を2030年度までに5000億円行う考え。
「当社が投資することで、投資機会も生まれる。そこにお客様の資金を投入し、我々が管理、運用していく。バランスシートを戦略的に使うことで、資産運用管理残高を増やしていくことが、我々のビジネスモデル」
時代の変化に合わせて、信託銀行としての収益の上げ方も大きく変わってきている。
「独立系信託銀行」であり続けることの意味
これまで、三井住友トラストグループは独立系信託銀行グループとして歩んできた。この「独立系」であることの意味を、大山氏はどう考えているのか。
「信託の原点は委託者の思いを実現するということ。信託銀行が中心のグループであるということは、中立性や社会性を一番に大切にしないといけない。マルチステークホルダーに託された存在であるためには、我々自身が上場を維持し、市場の規律と直接対峙していることが必要。特定のグループに属することなく独立系の信託であることは、信託銀行グループとしての根本理念」
冒頭に大山氏が言及した「資金、資産、資本の好循環」を実現するため、三井住友トラストグループはその中核的役割を果たしていく存在になることを目指している。商業銀行を中核とするメガバンクグループとは進むべき方向が違うのだということ。
大山氏の原点には、1999年3月の旧住友信託銀行への公的資金注入がある。「生存本能を研ぎ澄ませておかないと、いつ潰れてもおかしくない」という緊張状態の中で金融再編が進んだが、当時から大山氏は「信託銀行中心のグループをつくって、中核的役割を果たしたいというのが夢だった」と強調する。
信託銀行中心のグループが誕生して10年、足場は固まった。今後はグループ一丸で大山氏が目指す「資金、資産、資本の好循環」の具体化に向かって走れるかが問われる。