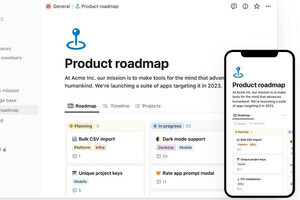8月21日、22日に開催された「TECH+セミナー Marketing Days 専門家とベンダーの対話 トップマーケターが語り合うBtoBマーケティング最前線」に、日商エレクトロニクス エンタープライズ事業本部 ビジネス推進部 部長 近藤智基氏が登壇。同社でクラウド事業の立ち上げからマーケティング組織の構築、拡大までを手掛けた近藤氏が、どのように自社の課題を解決したかを振り返った。
成長戦略を実行し、マーケティング組織を拡大
日商エレクトロニクスは、双日の子会社としてPCサーバ、ストレージなどのITインフラを提供している。ハードウエア、ソフトウエアに限らず幅広い商材を取り扱っており、ターゲットは年商1000億円以上のエンタープライズ企業だ。
社内の基盤となるITインフラを提供しているため、顧客の検討期間は最低でも数カ月、長い場合は数年かかるケースもあるという。商材単価が高いため、顧客側での社内稟議が必要となるのも特長的だ。つまり、受注までのリードタイムは決して短いとは言えない。
「BtoBマーケティングを始めた当初は、このビジネスで導入するは難しいと言われていました。現在はある程度結果も出ており、内部・外部の方々から高い評価をいただいています」(近藤氏)
同氏所属のマーケティング部から生み出された案件のLTV(Life Time Value)は130億円にまで上る。その実績が認められ、近藤氏がAdobeの「Marketo Engage Champion 2022 Marketing Executive of the Year」を受賞するなど、同部の取り組みは複数ベンダーから表彰され、対外的な評価も高まっているそうだ。
設立当初は5名からスタートした組織も、現在は20名まで規模を拡大している。では、どのような点にコミットして同社は組織の増強を行ったのか。
徹底的な数値化で営業部との連携を強化
近藤氏は、2つのポイントを重視しながらマーケティング戦略の立案・遂行したと説明する。1つは「数値コミット主義のマーケティング組織」の形成、もう1つは「顧客視点のマーケティング戦略」の遂行だ。
マーケティングを進めるうえで、まず整えるべきは社内の連携だろう。特に、最終的な受注に関わる営業部門との連携は必須だと言える。しかし、互いに異なるKPIを追う両者にとって、認識の齟齬が生まれやすい側面もある。
「マーケターはイベントやWebから新規の案件をつくりたいと奔走しています。そのため、生まれた案件をすぐに営業にトスアップしてしまうケースもあるでしょう。しかし、営業からすれば、どこの案件かも分からないとか、ターゲットが違うという風に感じて、対応をしてもらえないこともあります。マーケターも売上に貢献するためには、営業と同じ目線で会話をする必要があるのです」(近藤氏)
また、マーケティング組織が社内で“コストセンター”だとみなされやすいという課題もある。売上に貢献していない組織だと思われ、社内での連携に組み込まれないといったことが起きてしまえば、スムーズなマーケティング活動に繋がらない。
そこで、日商エレクトロニクスではまず、営業組織が掲げる戦略について積極的な情報収集を行った。マーケティングと営業が同じ目線を持つことが狙いであり、営業の最大目標である「予算の達成」にコミットできるマーケティング戦略の立案を目指したという。
次に近藤氏は「ターゲットの一致」「目標金額の策定」「トスアップするリードの目標件数の設定」を明確にした。
ターゲットの一致
ターゲットの一致においては、“営業が狙いたい顧客”のリードを獲得することが合意形成において重要だと近藤氏は話す。同社では先述のターゲット「年商1000億円以上のエンタープライズ企業」が共通見解を持ったターゲットになっている。
目標金額の策定
営業メンバーは設定された予算に対して、既存のクライアントからどれくらいの金額が受注できるかのイメージを持っている。既存金額と予算の差分を同社では「空白の金額」と呼び、この空白を埋めるために、マーケティングが営業の一翼を担っているそうだ。
トスアップするリードの目標件数の設定
空白の金額を埋めるためには、必要な案件数≒トスアップすべきリードの目標件数が自ずと設定されていく。「概算でも構わないので、営業に対して数値を伝えて約束することが大事」だと近藤氏は述べた。
こうして合意が取れた数値に対して、この目標が達成できなければ次年度以降の合意は形成できない。そのため、日商エレクトロニクスでは目標達成へコミットすべく、マーケティング部門、営業部門の業務を数値化。これにより「SQL(Sales Qualified Lead、営業部門が対応すべき見込み顧客)から商談への転換率」がボトルネックになっていることが判明したという。
同社の従来のフローでは、新規を開拓する際、まずはマーケティング部門で顧客をMQL(Marketing Qualified Lead、マーケティング部門が対応すべき見込み顧客見込み顧客)まで育て、営業にトスアップするかたちだった。ここにテコ入れを行い、マーケティング部門がSQLまで育成する形式に変更した。
これによって、SQLの商談率までをマーケティング部門が追うかたちになった。MQLへの育成までであれば、多少質が伴わないリードも成約に向けてマーケティングから営業へ託すケースがある。しかし、マーケティング部門が従来よりも一歩先のKPIを担うことで、結果的に営業へトスアップする案件の精度を高めることが可能になったそうだ。
「営業から見ると、受注に近い段階まで育っている、かつ自分たちが当たりたいターゲット顧客のリードが渡されることになります。この変更により、営業がトスアップされたリードをフォローすることにも協力的になっていきました」(近藤氏)
結果として、同社の商談化率は30%から80%に向上。トスアップ後の受注率も50%から70%へ高められているという。
先述のターゲットの設定からマーケティング活動、受注率に至るまで、日商エレクトロニクスでは徹底的な数値化を行った。近藤氏は「営業との連携はもちろん、数字を意識することで無駄なマーケティング活動が減る。成果に繋がらない“自己満足のマーケティング”からの脱却ができた」と手応えを語った。
顧客に適切なタイミングで適切な情報提供を行う
現在、近藤氏のミッションは「新規顧客の創出」である。一般的にはナーチャリング(育成)が重視される見方が強いが、同氏は「顧客のタイミングを押さえることが重要」だと考えているそうだ。日商エレクトロニクスでは、以下の2つのポイントで顧客のタイミングを計れるようなマーケティング活動を行っている。
製品推しではなく、顧客の課題感を訴求
1つ目のポイントは、顧客の課題感を訴求することだ。マーケティングコンテンツを例に挙げると、旧来は「この製品のここがすごい」というような製品のスペック、メリットを強調するものが多かった。一方、現在は顧客の持つ課題感に端を発し、課題解決のための策と製品のメリットを結びつける方向性に転換している。
日商エレクトロニクスでは「Value Proposition」というフレームワークを活用して、顧客の課題感と製品のメリットをマッチングさせているという。さまざまな要素から課題を洗い出すことで、「商材が顧客のニーズを満たしているか」を把握しやすくなるのがValue Propositionの特長だ。同社ではValue Propositionで得た結果を、マーケティング部門だけではなく、営業やインサイドセールスにも共有している。
また、コンテンツづくりの際にも「主語が顧客になっているか」などをチェックするコミュニケーションガイドラインが設定されているそうだ。これにより、顧客視点のコンテンツを制作、活用する意識を徹底させている。
カスタマージャーニーの設定
2つ目のポイントはカスタマージャーニーの設定だ。顧客視点のコンテンツをいかに適切なタイミングで情報提供ができるかを把握するためのものであり、どのタイミングで、どのチャネルに、どのような情報提供をすることが望ましいかを可視化できるという。
こうした顧客視点のマーケティングを徹底したことにより、これまでプロダクト思考を持っていたマーケターの案件創出率が「30倍に引き上がった」と近藤氏は胸を張る。メールの開封率やインサイドセールスへのトスアップ率も向上する結果が出ているそうだ。
組織を拡大した日商エレクトロニクスが目指すものとは
2021年に5人で始動した同社のマーケティング部門は今、事業のスケールアップへ向けて営業部門と統合されるなど新たな動きを見せている。近藤氏は、マーケティング部門の指揮を担い、今後は、新規顧客の開拓に限らず、既存顧客からのさらなる案件創出を目指すと言う。また、新たなマーケティングのチャレンジとして、カスタマーサクセス部門による既存顧客のファン化を目指していくそうだ。
「マーケティング部門が営業部に統合されたことで、両者がさらに一体となって顧客をつくっていこうという動きが活発化しています」(近藤氏)
* * *
売上の創出にコミットすべく、数値化や営業との連携を含めた社内調整、顧客視点のマーケティングを実現した日商エレクトロニクス。課題を抽出して適切な対策を打つ観点で、他の企業にとってもBtoBマーケティングの好例となるだろう。